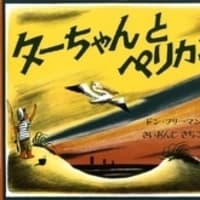| ふくろうのそめものや 作:松谷 みよ子 / 絵:和歌山 静子出版社:童心社  |
「ふくろうのそめものや」3分
むかし、カラスはまっ白でしたが、まわりの鳥たちの美しさに気付き、ふくろうのそめものやに色をつけてもらいに行きます。ところが、あれもこれも気に入らないと文句をつけると、ふくろうは怒ってすべての色をカラスにぶちまけてしまい、それで今までカラスはまっくろなのでした。というお話。
色をぶちまけるところはもっとウケるかと思っていましたが、どっちかというと皆「ひどいことになった」という心配顔だったような。2人が感想を聞かせてくれました。一生懸命あらすじをなぞり、「からすがむかしはまっしろだったこと、ふくろうがそめものやをやっていたことがわかってよかった」というようなお言葉をもらいました。
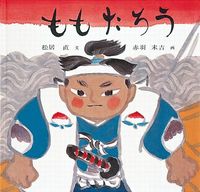 | ももたろう 作:松居 直 / 絵:赤羽 末吉出版社:福音館書店  |
「ももたろう」13分
言わずと知れた昔話の定番です。特徴的なのは、鬼退治に行くまでの過程・成長が丁寧に描かれ、「つんぶく かんぶく つんぶく かんぶく」など、擬音が新鮮で面白いこと。「どんぶらこ」ではないのです。
そして驚くことに、桃が流れてきてすぐ、おばあさんは桃を食べちゃうんですね。美味しいからおじいさんに持って帰りたいと、「うーまいももっこ、こっちゃこい」なんて唄をうたっていると、さらに大きい桃が流れてくる。うまいことやってるなあと微笑ましい感じです。
山から帰ったおじいさんに、「みずよりよいものを かわからひろってきたで それをおあがり」とすすめるところは、2人の仲の良さが伝わってきてこれもまたほのぼのです。
と思ったらそこから急展開、桃をわろうとすると、桃が「じゃくっとわれて」中から真っ赤な男の子が「ほおげあ ほおげあっ」と生まれました。ここで少し、子どもたちは笑っていましたね。
成長を描いた場面で、ごはんを食べれば食べただけ大きくなる、という所や「一おしえれば 十までわかる」で、「ほーおぅ」みたいな空気が生まれました。
次にカラスが村々の異変を伝えに来て、桃太郎が鬼退治を決意して爺婆を説得する場面があり、爺婆はそれを泣く泣く受け入れるという展開です。これは、子供の自立を描いているのですね。親は「にっぽんいちのきびだんご」を作って送り出してやらなくてはならないと思うと目頭が…。
犬、猿、キジをお供にする旅路では、子供たちはちょっとそわそわ身体が揺れていました。知っている展開だし、飽きたかな?本の方も、それまでの丁寧な描写は無くなり、必要最低限のセリフでさっさと目的地にいくよ!って感じの流れではあります。
松居版ももたろうの一番の特徴は、鬼退治をしても宝物はとらず、お姫様をもらうところです。一番最初に感想を言ってくれた男の子も、「ほかのしっている話では、たからものをとって帰るけど、おひめさまをとってきたのがちがうとおもった」と言っていました。違うから間違ってる、という風ではなく、単純に違いに気づいて驚いた、という感じでよかったです。
これは、以前松居直の著書を読んだときに松居氏がこだわりポイントとして挙げていて、(ウロ覚えですが)あえて宝物はとらず、嫁取りの話にしたんだとか。お嫁さんをもらって子宝を得るほうが、人生の目的?だか宝、みたいなことを書きたかったようです。
知っている話だけれど、改めて読んでみると面白かったですね。前日練習していたら、息子も「絵がきれいだし(いいね)」と言って自分でも読んでいました。