マルクス剰余価値論批判序説 その3
第一章、社会とその上部
1、生産関係としての社会
『経済学批判要綱』と『資本論』とを、それ以前のマルクスから区別づけるものは、マルクス独自の剰余価値論の存在である。マルクスの剰余価値論は!古典派政治経済学の労働価値論に対する批判であり、その労働価値論に基づいた社会主義や共産主義に対する批判である。
マルクスは、古典派政治経済学の労働価値論の批判において、まず労働価値論そのものを完成させる。そして、自ら完成させた労働価値論が、いかに「狂った」観念であるのかを、論証したのである。
マルクスは労働価値論を提唱しただけではなく、それ自体を解体しようとしたのであるが、後者については前者ほどには注目されなかった。それは、マルクスの剰余価値論が、あまりにも社会的だったからである。
『経済学批判要綱』における、社会についての記述を見て
みよう。
われわれがプルジョア社会を全体として観察するときには、社会的生産過程の最後の結果として、つねに、社会そのものが、すなわち、社会的諸関連のなかにある人間そのものが現われる。(1)
このように、社会は、生産過程における人間の連関の様態として捉えられている。だが、そのような人間が、階級関係に規定されているものであるという以前の見解は、特に強調されてはいない。もちろん、階級関係が忘れられているわけではない(2)。しかし、階級関係を社会関係としてみる姿勢
も現われている。(3)
階級関係にもとづいて社会関係があるとする中期マルクスの見解から、階級関係をも社会関係として見てしまうような、階級関係についての位置づけの揺らぎはあるものの、社会についての見解に、変化は見られない。
もう一つ、社会についての記述を見てみよう。
社会は、諸個人から成り立っているのではなくて、これらの個人がたがいにかかわりあっているもろもろの関連や関係の総和を表現している。まるで、社会の見地からすれば、奴隷や市民は実在しない、つまり両方とも人間だ、と言おうとする人がいるかのようである。そうではなく、彼らが人間であるのは、社会の外部で、なのである。奴隷であり市民であるのは、AおよびBという人間の社会的規定、社会的関連なのである。人間Aは、人間そのものとしては奴隷ではない。彼が奴隷であるのは、社会の中で、また社会を通じてである。(4)
ここでも社会は、生産の総過程としての社会的連関にある人間(個人)として、捉えられている。だが、ここで注目すべきなのは、マルクスが、社会ではないことについて語っているところである。










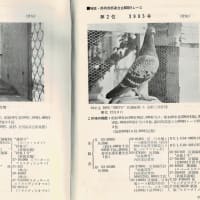

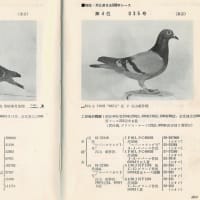







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます