330円のコーヒーに対して生産者が受け取る対価はわずか3円から9円・・・ほとんどはカフェ、小売り、焙煎業者、輸入業者の儲けに消えていく・・・。グローバリズムの歪さを浮き彫りにした作品「おいしいコーヒーの真実」のDVDをようやく観た。
舞台はコーヒー発祥の地・エチオピア。不公平な貿易システムに依って、生産者は貧困に喘いでいる。そのコーヒー農家を救おうとする一人の男の戦いを描くことで、その理不尽な構図を描き出すこの作品は実に面白い。
生産者に適切な対価が払われていたなら・・・飢餓の苦しむことなく、子どもに教育を提供出来、持続可能な農業が成り立つのだ。飢餓援助ではなく、生産者は自立出来る。そのためには企業の収奪ではなく、公正な取引(フェアトレード)が必要なのだと主人公は世界を飛び回る。
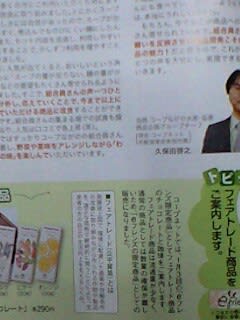
フェアトレードについては、何度も書いたので繰り返さない。ATJなどを通して、一部の生協では、長い取り組みがされてもいる。みやぎでも取り組みが進んでいる。ただ、生協全体で取り組むとなると課題は山積み・・・正月明けの1月3回でインターネット限定商品で、コーヒーとチョコレートの扱いが始まったばかりだ。
日生協が、そして拠点の大規模生協こそが、こうした取り組みを進めていくこと。こうした取り組みを先駆的に行って市場を切り開いていくこと。低価格競争も重要(暮らしに貢献するって意味で絶対に否定しないさ)、それとともに“車の両輪”で、生協としての“価値”を貪欲なまでに追求してって欲しいんだ。
「協同組合は、自助、自己責任、民主主義、平等、公正、そして連帯の価値を基礎とする」という協同組合の価値にも合致する活動だ、って、地域生協の一担当者が書くのはおこがましいんだけど、書生論であることを承知の上で、書いておきたい。




















