人は死を目前として何を見るのか? ― 実地調査でわかった“死ぬ直前の光景”

理想国家日本の条件 自立国家日本記事
http://blog.goo.ne.jp/sakurasakuya7/e/374b93b55e79ff5ab49524fc5a3c175e
2014.05.29
転載、させていただいた記事です
http://tocana.jp/2014/05/post_4185_entry.html
臨終を前にして本人は何を知り、何を思うのか…。愛する人間の死の間際に、親類や親しい知人友人は
何を感じるのか…。身近で死に立ち会う医師や看護婦から見て、人間の死の直前には、何か共通する
現象が起こっているのだろうか。人間の死生観にとってあまりにもデリケートな問題であるが故に、これまで
省みられることなかったこの領域に、本腰を入れて取り組んでいるのがカナダ人女性作家の
パトリシア・ピアソン氏である。
■父と姉の死に直面して得た体験とは
死期を迎える本人とその身近な人々の神秘体験を、実地に調査して考察した新作ノンフィクション
『Opening Heaven's Door』を5月に出版したパトリシア・ピアソン氏が、自著の内容について綴った
記事を「Daily Mail」紙に寄稿している。
記事の中でピアソン氏は、手はじめにかつて自らの身辺に起こった“神秘体験”を述べている。
彼女の父は、ある日の早朝に家族(母と彼女)の者には全く思いがけない形で急死を遂げてしまった。
暫くして、実家から100マイル離れた土地で別居している姉に、母から電話で父の死が伝えられのだが、
驚いたことにちょうど父が旅立った明け方、ベッドの中で姉は父の存在を確かに感じたのだという。
「ベッドの中で幸せな感覚が押し寄せ、私の頭に父の手が触れるのを感じたの。そして次に、私たちの
幸せな未来を写した映画のような映像を見たのよ」
家族はすぐにはこの話を信じなかったが、今ではきっと父があの世へ旅立つ前に、離れて暮らす娘のもとへ
立ち寄ったのだ、と考えるようになっているという。
この話は、悲劇的な後日談を交えてさらに続くことになる。実は離れて暮らす彼女の姉は末期がん患者で
あったのだが、父の死後ひと月ほど経った頃、姉の病状は致命的なまでに進行し、末期医療病棟の入院ベッド
で死を待つだけの容態になってしまったのだった。ピアソン氏をはじめ家族は、足繁く彼女のもとへと通う
日々が続いていた。
病魔と治療で衰弱しきっていた彼女ではあったが、死亡日の10日ほど前から、どういうわけかその容貌が
血色を帯びて幸せそうな表情へと変化し、家族には見えない誰かに向かって語りかけていることが多く
なったという。
幸せそうにする一方で、彼女は正確に自分の死期を把握していたふしがあったという。死亡時刻の
48時間前になって彼女は、「私は出かけます」と口にしたのだ。さらに逝去の数時間前にも同じ発言を繰り返し、
それから暫くして息を引き取ったのだった。病院の判断では、彼女の余命はおよそ2年以内という大まかな
予測しかなかったという。
本格的なフィールドワークを前に、自身の死生観を揺がしたこれらの出来事を今一度反芻するピアソン氏
であったが、この体験が皮肉にも他の人々の体験談を聞き出すのに非常に役立ったという。彼女のこの話を
聞いてから、「実は今まで誰にも言ったことのない話だが…」という決まり文句の後、各々が体験した神秘体験
を語り出す人も決して少なくなかった。
あの世はどんな光景なのか… 画像は「Daily Mail」より
■さっきまでそこにいた父
ピアソン氏の友人である大手音楽会社のディレクターも、子供の頃に体験した“神秘体験”を語って
くれた一人である。
少年であった彼はある朝、自室で目覚めてからいつものように朝食をとるべく一階のダイニングキッチン
におりていったのだった。そこには、いつものように先にテーブルに着く父の姿があったのだが…。
父がテーブルを離れて暫くしてから、彼の母が衝撃的な発言をしたのだった。
「実はお父さんは昨晩亡くなったんだよ」
彼はもちろん驚いたが、母の気が確かなのか心配になったという。
「父さんは今までそこに座ってたじゃないか!」
と彼は訴えるが…。しかし確かに父は昨晩亡くなっていたのだ。この朝の一件は、これまでの彼の人生の
中で最も強烈で不可思議な体験であったという。
■娘の事故を夢で体験した母
また、ある知人の女性は、彼女の姉の体験談を語ってくれた。
姉はある深夜、砕けたガラスが辺りに散らばる感覚に襲われて不意に目覚めたという。寝室の窓ガラスが
何らかの理由で砕け散ったのだと思ったということだ。
飛び起きた姉は慎重にベットから立ち上がり、周りに散乱するガラスの破片を集めようとしたものの、全く
何もなかった。窓を確認してみても、ヒビひとつない無傷の状態であり、単なる悪夢を見ただけだと自分を
納得させて再び床に就いたのだが…。
朝になり、姉はショッキングな一報を知らされることになる。
なんと昨夜、彼女の娘が自動車事故を起こしていたというのだ。車のフロントガラスが粉々に砕け散る
ほどの事故だったという。
このように、ある人物が死や危険に直面している際、親類をはじめとする身近な関係者に起こる奇妙で
不可思議な体験談は、実際に聞き出してみれば非常に多く、「もはや無視することができないものである」と
末期医療に携わる医師、ミシェル・バーバト氏は語っている。
■旅の支度 ― 死期は本人が一番知っている
カリフォルニア州の末期患者ケア施設の前代表であるデイビッド・ケスラー氏は、施設内で死期の迫った
患者が“旅支度”を始める様子を何度も見ているという。
「興味深いことに、バッグに詰める荷物を指示したり、交通機関のチケットを確認したりするなど、実際の旅支度と
なんら変わることはないんです」と、彼はかつて担当した96歳の患者を思い出す。その患者は病床で寝たままで
あるにもかかわらず、看病に来ていた娘に「もう行く時間だ。車は来ているか?」と尋ねたという。
気丈な娘さんは父に逆らわず、「車はいつでも出せるわよ」と話につきあい、「でも、お父さんはどこに行くの?」
と思わず質問してしまったという。
すると父は「場所はわからんが、行き先はわしの目の前に広がっておる。もう時間だ」と言い、
それから息を引き取ったという。
このように、死が訪れる正確な時間は本人が一番よく知っているように思われるケースが多いとのことだ。
2006年のクリスマス・イブに亡くなった著名ミュージシャン、ジェームス・ブラウンは、緊急入院したときには
命に別条のない単なる肺炎だと見なされていた。
しかし、彼本人は死期の訪れを知っていたのではないかといわれている。
彼は病院で「今夜出かけるよ」と娘に言い残し、その通りにその晩、あの世へと旅立ってしまったのだ。
■デスベッド・ビジョン
女性産科医のフローレンス・バーネットは、不幸にしてお産の後に亡くなってしまったドリスについて語っている。
難産の末、赤ちゃんは無事であったのだが、その命と引き換えのように死の淵へと向かいつつあったドリスは、
部屋の一点を見つめながら、うわごとのような言葉を口ずさんでいたという。そばにいたバーネットは、
聞き役に回って彼女の言葉に応えていたとき、
「お父さん! 今から私がそっちへ行くから喜んでいるのね!」
…とつぶやくドリスの言葉を聞き、彼女があの世の父親の姿を見ているのだと理解した。
「お父さん、ヴィダ(ドリスの姉)も一緒なのね…」
と、姉の姿も見えているようだったが、ドリスの表情は明らかに訝し気であったという。
それから暫くしてドリスは息を引き取った。
その後バーネットが知って驚いたことは、実はヴィダは3週間前に亡くなっていたのだが、出産を目前に控えた
ドリスがショックを受けないよう、周囲の取り計らいによってドリスには姉の死が隠されていたということだった。
死を目前にして図らずもヴィダの姿を見たドリスが、戸惑いの様子を見せたということの説明もつくし、ドリスが
見ていたと思われる人物は確かに2人ともこの世にはいない人々であることから、
本当に死後の世界を見ていたと判断できなくもないのだ。
天国への扉が開かれた! 画像は「Daily Mail」より
死の間際に見る、あの世のものとしか考えられないような不思議な光景「デスベッド・ビジョン」は、
実に末期患者の41%が見ていると、バージニア大学の心理学者エミリー・ウィリアムズ・ケリー氏の
研究論文では報告されている。
また、末期患者を現場で担当する看護婦たちの間では、正式な診察ではないものの、患者がこれらの
「デスベッド・ビジョン」を見ているかどうかが、死期が差し迫っているかどうかの判断材料になるともいわれている。
精神科医のカーリス・オアシス氏とエランドル・ハラルドソン氏は、共同研究の中で「およそ8割の
『デスベッド・ビジョン』の内容は、患者本人に付添い人がやって来たり、本人をどこかへ
連れていくようなストーリーです」と語っている。
■死の直前に言語明瞭&動作機敏に
精神疾患や認知症などの患者が、死期を目前にして突然、明瞭な話口調になるケースも数多く
報告されている。記憶障害の患者ですら、死期の直前には家族の顔と名前を理解して会話に応じ、
個々に最期の言葉を伝えることも珍しくないという。
スコット・ヘイグ医師は、2007年に担当した患者のデイビット氏について書き残している。
デイビット氏は肺がんを患った末、がん細胞が脳にまで転移している重症患者であった。
既に彼の話し口調は不明瞭で、動くこともままならなかった。頭部をスキャンしたところ、脳はほとんど
機能していないということも分かり、暫くして植物人間状態になってしまった。
ある日ヘイグ医師は、午後の検診を終えたとき、デイビッド氏が懸命に呼吸をしているのを認めた。
これは臨終が迫っていることを示すサインであることを医師は経験的に知っていた。しかし次の瞬間、
長い昏睡からデイビッドは目覚め、看病していた妻と3人の子供に向かって静かに、理路整然と別れの
言葉を述べ、笑顔で手の平を叩き合ったという。そして彼は息を引き取った。
ヘイグ医師は「これは決して彼の脳が行った言動ではない。このとき既に彼の脳は機能して
いなかったのだ」と書き記している。
精神科医のラッセル・ノイズ医師は、2度の脳梗塞で喋ることも動くこともできなくなった91歳の老女が、
死を目前にして急に満面の笑顔を浮かべて頭を起こし、両手をあげて彼女の亡き夫の名を叫ぶ様子を
現場で目撃した。そして次の瞬間、グッタリと頭を枕に沈め息を引き取ったという。彼女がデスベット・ビジョン
を見ていたのかどうかは別としても、この一瞬、彼女が喋る能力と手を動かす力を取り戻して
いたことだけは確かである。
倫理的、宗教的なハードルもあり、今まであまり積極的になされてこなかった人間の臨終にまつわる研究だが、
ピアソン氏によって集められた過去のケース・スタディから、いくつかの傾向がはっきりと浮き彫りになってきた
といえるだろう。今後、この分野での新たな発見が我々の死生観に多大な影響を及ぼすのではないだろうか。
(文=仲田しんじ)
















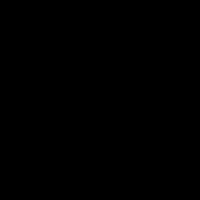
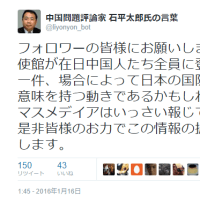

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます