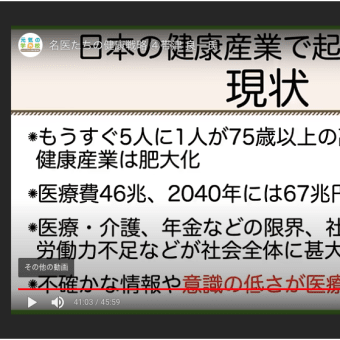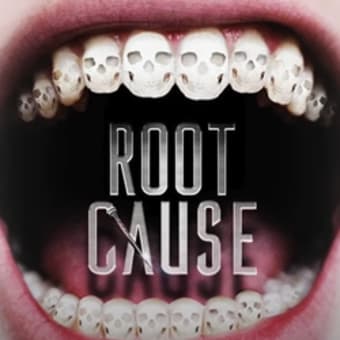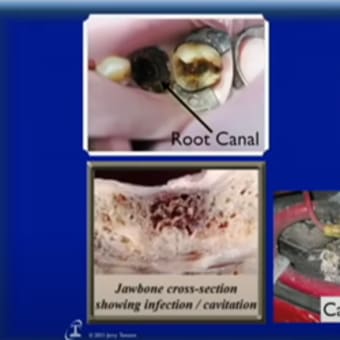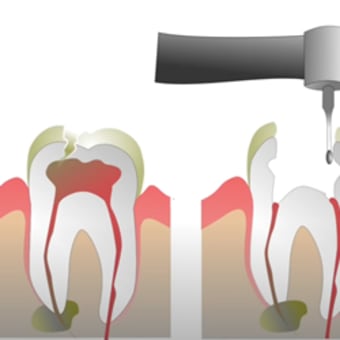私はもともと東洋医学から入ったので、陰陽五行論はいつも参考にしている。もちろんこれは科学的というより社会的であり統計的なのだが、けっこう参考になるものである。たとえば身体器官との関係では
肝が悪いとでは筋(スジ)が傷む、肩などがこる。
心が悪いとでは脈が乱れる、動悸がする。
脾が悪いと脂肪が減る、もしくは増える。
肺が悪いと皮膚が弱り皮膚の毛も弱る。
腎が悪いと骨が弱る。
となる。
これを現代西洋医学の病名と照らし合わせると面白い。たとえば・・・
パーキンソン病、筋ジストロフィー、眼瞼痙攣、子宮内膜症や月経前症候群、更年期症候群、その他もあるが肝臓とあまり関係なさそうにみえて東洋医学では肝臓病ともとらえる。
更年期、不安神経症、パニック障害、遺伝的な新生児の心臓病、なども心臓と関係する。心の経絡は悦楽、嫉妬、恨みなどを司るが、新生児の心臓病などは親が悦楽を求めることにより最たるもの。妊娠前の体の状態や精子卵子の状態が悪く、悪い食べ物を食べる(=悦楽)により起こるのだが、人類とやらは遺伝病という言い訳にすがるのが常である。
虚弱体質にとどまらずあらゆる体質的な問題は、東洋医学では胃(脾)から起こると考えることが多い。これは食べ物が体を作るという考えにも通じるだろうし、東洋医学ではたとえば病名が○○病であっても、胃が弱い人はまずそこを立て直すことを重視する。
アレルギーやアトピーに代表されるものはまさに肺の病気の筆頭である。喘息もアレルギーであることを考えれば理解しやすいだろうが、肺は排泄と入れ替えの臓器であり肺とつながる大腸の経絡も排泄の臓器。さらに腸内細菌が免疫に関係するという話は聞いたことがあるだろう。呼吸の仕方も関係してきるし、アレルギー、アトピー、喘息などの人は内向的な人が多い傾向にある。
骨粗鬆症や老化に関する病気は腎臓の病気とよく捉える。尿の排泄に関する臓器も腎臓が関係しており、腎臓は血の流れにも関係する水溶性毒物の解毒臓器(脂は肝臓)、老人が腰を痛めやすいのも腎臓の場所とつなげて考える。実際は腰の骨や関節が傷んでいるのだが、腎臓を立て直すことが腰痛をよくするのにも必要だと考えるのだ。
こういうことを解剖学的な西洋医学や栄養学と組み合わせると、治療効果が上がっていくのである。(写真はネットからお借り)