70歳も目の前になった。私が長年、アンプ作りで参考してきたブロガーの先達も身辺整理を始められたようだ。理由の第1は耳の聴力だ。特に年齢と伴に衰えていく高音の聴力の低下。これに抗うことはできない。
私も、アンプの仕上げのときに、オシレータを使って周波数対出力を測る。
出力端子にダミー抵抗を繋いで両端の電圧を測るのだが、出力が大きくなると
出力トランスが唸る。一応 15Khzくらいは、その唸り音が聴こえているつもりだ。
でも、健康診断で聴力を測定すると、明らかに10Khzの感度は低下している。
もう、いまの「MJ誌」の金田式アンプには、付いていけないし。
少なくとも、石アンプのパーツ類はトランスを始めとして、小物を含め断捨離すべきかと思い始めている。一番、心配なのは日常的に使っている電池式のEQアンプと同じく電池式のDCコンバータだろうか。故障したら修理する気力がない。
そうなると、DCコンバータは、何か購入するとして、EQアンプは、球を使ってオーソドックスに作るしかないだろう。DL-103用の昇圧トランス、AU-103?を残しておいて良かった。これがあれば、WEの球でCR型イコライザ・アンプくらいは作れるだろう。
フラット・アンプもシンプルな回路で作れるだろう。
当面の悩みは 手持ち最後の球、EL156をどうするかだ。一応、モノラルPPを2台作る予定でパーツは集めてある。今、バラックでシングル・アンプを2台鳴らしたりしているが、
サブ・ウーファーを使えばなんとかなりそうな気もしている。
でも、やはり、ちゃんとEL156pp×2台の音を聴いてみたいとも思っている。
明らかに6384ppの音とは違うので、悩ましい。
最新の画像[もっと見る]
-
 プレーヤー復活へ
2ヶ月前
プレーヤー復活へ
2ヶ月前
-
 プレーヤー復活へ
2ヶ月前
プレーヤー復活へ
2ヶ月前
-
 ORANGE社の小さなアンプ
2年前
ORANGE社の小さなアンプ
2年前
-
 MDギターの改造
2年前
MDギターの改造
2年前
-
 MDギターの改造
2年前
MDギターの改造
2年前
-
 MDギターの改造
2年前
MDギターの改造
2年前
-
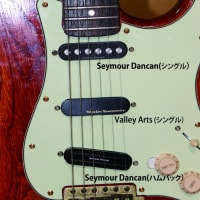 Schector改造記 番外編 その2
2年前
Schector改造記 番外編 その2
2年前
-
 Schector改造記 番外編 その2
2年前
Schector改造記 番外編 その2
2年前
-
 Schector改造記 番外編
2年前
Schector改造記 番外編
2年前
-
 Schector改造記 その5
3年前
Schector改造記 その5
3年前









