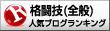みなさん、こんにちは。
”脚下照顧(きゃっかしょうこ)”とは、元々は禅の言葉で、良く禅寺の玄関などでみられる言葉です。
「脚下」は足元のこと。
「照顧」は反省することや、しっかりと見ること。

日常生活の中で、「履物をきれいに揃える」「トイレのスリッパがキチンと揃う」など、些細な事ですが、そういうことが、ちゃんと出来ていることが大切です。

いい道場か、そうでないかは、生徒さん達が履物をキチンと揃える習慣があるか、そうでないかでわかるそうです。
このようなマナーは、むしろ海外の道場の方が徹底されており、日本人の方が出来ていないそうです。

「合気道 真風会」に入門した人に、初めに必ず指導するのは、道場内に限らず、日常生活の中できちんと「あいさつ」が出来ること、加えて「履物を揃えること、下駄箱へ納める時は、頭を前に向けて、きれいに納めること」です。

合気道の稽古以前に、まず、そういうことがキチンと出来るようになりましょう。

以上は”脚下照顧”の表面的な意味であり、心掛けの事です。
しかしの本来の意味はもっと深いものです。
足元に気をつけろ、身近なことこそ気をつけるべきということです。
自分の足下(あしもと)を顧(かえり)みるとは「我が身」や「我が心」を振り返れ、自分が今どういう立場にいるか、よく見極めて事に当たれと言うことです。
つまり、他人を批判したり、論じたりするよりも、まずは自分の足下を見つめること、自分を顧みることを忘れぬようにと言う意味です。
禅では日常の全てが修行であり、日常の中や身近な足下にこそ心理があると考えるそうです。

「合気道 真風会」の道場生ならば、より足下の氣を抜いてはいけません。
道場だけが修行の場所ではなく、日常生活も修行の一部と考えて、どんなに忙しいときでも、履物はそろえて脱ぐという、心のゆとりが欲しいものだと思います。
”他人を批判したり、論じたりするよりも、まずは自分の足下(あしもと)を見つめること、自分を顧みることを忘れぬように。”
これが本当の”脚下照顧”です。


「脚下照顧」の本当の意味を踏まえた上で、まずは「履物を揃えること」から実践しましょう!
”継続は力なり”
”努力に勝る天才なし”
そして、
「強くなければ生きていけない。
優しくなければ生きて行く資格がない。」
では、また!
2023年5月8日新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について
<会員および体験希望者の方へお願い>
☆37℃以上の発熱や、咳、くしゃみ、のどの痛みなど、風邪のような症状がある場合は稽古の参加をお控えください。
☆コロナに罹患した場合は、発症後10日間を経過するまでは稽古の参加をお控えください。
☆道場へは、各自で施設に備え付けのアルコール消毒を使用、または石鹸で手洗いを行ってご入場ください。
☆マスクの着用については、窓を開けて十分な換気を行えていることを前提に、個人の判断で自由と致します。
(苅田町総合体育館改修工事について 工期:令和5年7月1日~令和6年7月31日)
改修工事終了までの間、下記の施設へ稽古場所を移転致しております。
期間 :2023年7月6日(木)の稽古より改修工事終了までの間
場所 :苅田町立 三原文化会館 2F和室大会議室 (苅田町富久町1-19-1)
稽古日時:稽古日、稽古時間は現行通り変わりません。(毎週木曜日 午後7時~)
日によっては、稽古場所が変更の場合もあり得ますので、体験入門をご希望の方は、事前に電話で稽古場所を確認の上、来られてください。
【ホームページ】