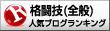向かって左端から私(上土井)、隣はI指導員(真風会)、3人目が上和田義秋先生、右端が修理氏。
2008年3月15日(土)、”合気道 真風会”会員の修理(しゅり)氏の自宅道場にて「修理道場 マイ道場まつり」が開催されました。
この修理氏は、真風会で合気道の稽古に励むかたわら、剣術なども稽古されており、昨年11月に自宅の一室を改造して、自身の個人稽古場である”マイ道場”を造られました。
今回、その”修理道場”のイベントに「力のない者の合気道」の著者”上和田義秋(かみわだよしあき)先生”をお招きし”合気道セミナー”が開催されました。
上和田義秋先生は、現在、年齢60代半ば、身長160センチ、体重57キログラムと、やや小柄な方です。
合気道歴は30年以上になり、塩田剛三先生の”養神館合気道”で稽古に励み四段まで取得されたそうです。
航空自衛隊に所属していた30歳近くの頃、養神館合気道の先生が転勤されてきたのをきっかけに合気道を始めたそうです。
その合気道部の一番弟子の一人として、稽古に励み”誰にもできる得意な技”を一つ身に付け、自信を持って後輩の指導もされていたそうです。
ところが、転勤で大阪のある道場へ入門したその日に、力が同等と思われる人に両手首をがっちり握られ、”誰にもできる得意な技”を行おうとしたけども、全く出来なかったそうです。
この出来事で上和田先生は、合気道部時代の自分の”誰にもできる得意な技”は、”教えられる者が、教える者に恥をかかせてはいけない。”の思いやりであったのだと回想されております。
それからは、力のない自分に出来る合気道の技を求めて、創意工夫、努力し、”力の出し方(丹田力)”と”力の抜き方”を身に付け「力のない者の合気道」を「丹田合気道」と名付け、その稽古方法を著書に記されております。
私も、上和田先生の著書は拝読したことがあり、力を抜くという事と、丹田を重視している事などが、非常に私達の合気道と似ており、興味を持っておりました。
たまたま、修理氏と上和田先生とは、同じ、元航空自衛隊出身の同僚であり、今でも友人同士であった為、私が紹介をお願いしたところ、上和田先生は、わざわざ遠い岐阜県から出向いて来てくださり、今回のセミナーとなりました。
楽しい雰囲気の中、上和田先生は、「丹田合気道」の技を、色々と披露してくださり、説明をしてくださいました。
上和田先生が、長年修行されて来た「養神館合気道」と「丹田合気道」とは、まさに正反対のスタイルのように思います。
「養神館合気道」のような力強い”剛”のイメージは全くなく、想像していた通り「丹田合気道」は、力を抜いた柔らかい動きの”柔”の合気道でした。
イメージ的には、「合気道真風会」の合気道と似ていると思います。
長年学んで来たスタイルに疑問を持ち、研究した結果、180度違うスタイルに行き着いた上和田先生は、私達「合気道真風会」と同じく、”力を抜く事”と、”丹田”の重要性を唱えております。(もちろん、”合気道真風会”とは、”丹田”の位置など、違う点は多々ありますが、発想が良く似ています。)
そういった意味で、私は、非常に上和田先生の合気道について共感出来る事が多く、本当の合気道の技とは、”力を抜いて、力を出す事”だと再認識する事が出来ました。
力を入れて技を掛けていては、本当に力が強い人には、技は掛からないのです。
力を抜くからこそ、合気道の技は掛かるのです。
だからこそ、非力な女性や、体力的に劣る人でも合気道は出来るのです。
セミナーの後は、修理氏の奥様が、たくさんの、おご馳走とお酒をご用意してくださり、楽しく、大変有意義な時間を、過ごさせて頂きました。
上和田先生、本当にありがとうございました。
また、修理さん、奥様、大変お世話になり、ありがとうございました。
この場を借りて、お礼申し上げます。
 |
力のない者の合気道上和田 義秋新風舎このアイテムの詳細を見る |
【ホームページ】