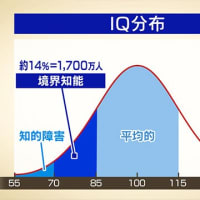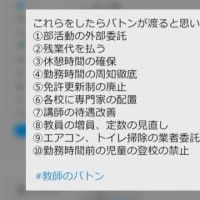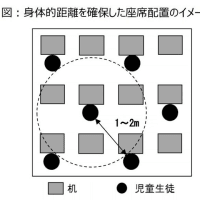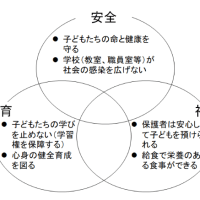(ここでいう、初期理科教育とは、小中学校レベルの理科教育のことです。)
最近の理科教育のはやりは、「科学的思考」と「表現力」です
要するに、生徒に「なんでこーなんの?」って考えさせることと、「私はこう思う」と発表させることをちゃんとやりなさい、ということです。
ただ、はっきり言って、私はこの方針に懐疑的です。
公の場で言うと怒られるでしょうけどね。
良い議論とは、基礎的基本的な知識があって成立するものです。
小中学校段階では、基礎基本の習得を重視するべきだと私は考えていますし
同じ学級内で、基礎基本の習得具合にばらつきが生じる、今のクラス編成のシステムとの相性も悪いと思っています。
だから、私は、アクティブラーニングに対しても、同様の理由で、懐疑的です。
考えさせる、議論させるって、大変なことなのですよ。
私は、現在中1に理科を教えています。
そして、私が使用している教科書には、このような問いかけがあります。
筆箱をつかんでいる手を離すと、筆箱は落ちる。どうしてだろうか?
これを考えろ、そして議論しろって、なかなか難しい事だと思いませんか?
シンプルに答えるなら、「重力がはたらいているから」でありましょう。
ただ残念ながら、この程度の回答は、小学生でもできるから、価値がない。
では、なぜ重力ははたらくのだろうか?と掘り下げてしまうと、あまりに高度すぎて中学生にはふさわしくない。
そんな議論をするよりも、ニュートン登場以前の、アリストテレス的な考え方を生徒から引き出し
「でも、ニュートンは、そうじゃないって言い出したんだわ」
という話に持って行った方が良いと思うんですよね。
先の話は、物理に関する例ですが
次は化学について話をします。
中学校理科では、原子のつくりについて
原子核のまわりを電子がクルクル回っている
と説明します。
化学について詳しい方には、ラザフォードモデルだと言った方がわかりやすいかも知れません。
そして、これは現在の理解とは大きなギャップがあります。
何と言っても、ラザフォードモデルは100年前の代物ですからね。
(別に、ラザフォードを馬鹿にしているわけでは無いですよ。
そのような経緯があって、現在の化学や量子力学の発展があるわけで、大切な歴史です。)
そして、高校に行くと、高校の化学教師に
「実はな、原子のつくりはそんなに簡単では無くてな……」と、ボーアモデルを教えられ
さらに大学に行くと、また同様に「そんなに簡単では無くてな……」と、オービタルによる考え方を教えられるわけです。
だったらもう、これも科学史的に
20世紀の初頭、人類は原子のつくりについて、こんな感じだと解釈した
とラザフォードモデルを提示し、それ以降のことは高校、大学でやればよいとしてしまえば、違和感がない気がします。
ですから、自分は錬金術だって教科書に載せりゃ良いと思っています。
まとめると
小中学校では、一般教養として
いつ頃、だれが、どんな研究をして、どんな知見が得られたのか
それは現在どのように利用されてるのか、または現在のどのような研究につながったのか
を教え、それでおなかいっぱいになる生徒はそれでOK、自然科学とは無縁の人生を送れば良いし
(決してそれは悪いことでは無い)
そんな話を聞いて、テンション上がって
「俺も研究者になりたい」
「何か発見をしたい」
「もっと先を知りたい」
と思う生徒は、高校でより自然科学的な理科を学び、理系大学を志せば良いんじゃないでしょうか。
文科省の人に知れたら怒られるでしょうね。
ああ、匿名って素晴らしい。
最近の理科教育のはやりは、「科学的思考」と「表現力」です
要するに、生徒に「なんでこーなんの?」って考えさせることと、「私はこう思う」と発表させることをちゃんとやりなさい、ということです。
ただ、はっきり言って、私はこの方針に懐疑的です。
公の場で言うと怒られるでしょうけどね。
良い議論とは、基礎的基本的な知識があって成立するものです。
小中学校段階では、基礎基本の習得を重視するべきだと私は考えていますし
同じ学級内で、基礎基本の習得具合にばらつきが生じる、今のクラス編成のシステムとの相性も悪いと思っています。
だから、私は、アクティブラーニングに対しても、同様の理由で、懐疑的です。
考えさせる、議論させるって、大変なことなのですよ。
私は、現在中1に理科を教えています。
そして、私が使用している教科書には、このような問いかけがあります。
筆箱をつかんでいる手を離すと、筆箱は落ちる。どうしてだろうか?
これを考えろ、そして議論しろって、なかなか難しい事だと思いませんか?
シンプルに答えるなら、「重力がはたらいているから」でありましょう。
ただ残念ながら、この程度の回答は、小学生でもできるから、価値がない。
では、なぜ重力ははたらくのだろうか?と掘り下げてしまうと、あまりに高度すぎて中学生にはふさわしくない。
そんな議論をするよりも、ニュートン登場以前の、アリストテレス的な考え方を生徒から引き出し
「でも、ニュートンは、そうじゃないって言い出したんだわ」
という話に持って行った方が良いと思うんですよね。
先の話は、物理に関する例ですが
次は化学について話をします。
中学校理科では、原子のつくりについて
原子核のまわりを電子がクルクル回っている
と説明します。
化学について詳しい方には、ラザフォードモデルだと言った方がわかりやすいかも知れません。
そして、これは現在の理解とは大きなギャップがあります。
何と言っても、ラザフォードモデルは100年前の代物ですからね。
(別に、ラザフォードを馬鹿にしているわけでは無いですよ。
そのような経緯があって、現在の化学や量子力学の発展があるわけで、大切な歴史です。)
そして、高校に行くと、高校の化学教師に
「実はな、原子のつくりはそんなに簡単では無くてな……」と、ボーアモデルを教えられ
さらに大学に行くと、また同様に「そんなに簡単では無くてな……」と、オービタルによる考え方を教えられるわけです。
だったらもう、これも科学史的に
20世紀の初頭、人類は原子のつくりについて、こんな感じだと解釈した
とラザフォードモデルを提示し、それ以降のことは高校、大学でやればよいとしてしまえば、違和感がない気がします。
ですから、自分は錬金術だって教科書に載せりゃ良いと思っています。
まとめると
小中学校では、一般教養として
いつ頃、だれが、どんな研究をして、どんな知見が得られたのか
それは現在どのように利用されてるのか、または現在のどのような研究につながったのか
を教え、それでおなかいっぱいになる生徒はそれでOK、自然科学とは無縁の人生を送れば良いし
(決してそれは悪いことでは無い)
そんな話を聞いて、テンション上がって
「俺も研究者になりたい」
「何か発見をしたい」
「もっと先を知りたい」
と思う生徒は、高校でより自然科学的な理科を学び、理系大学を志せば良いんじゃないでしょうか。
文科省の人に知れたら怒られるでしょうね。
ああ、匿名って素晴らしい。