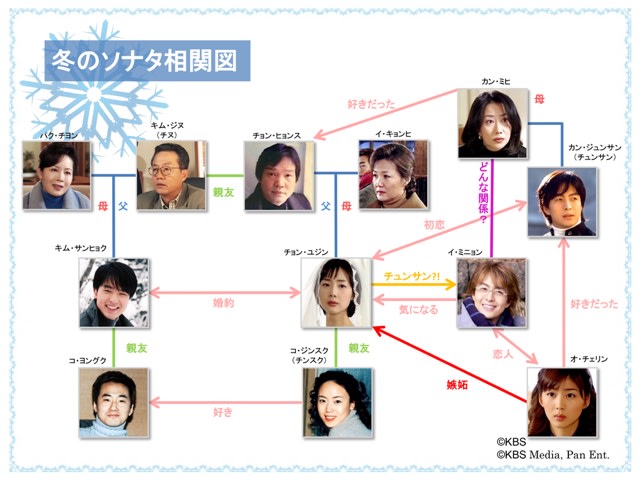
ユジンとサンヒョクは、チンスクとヨングクと一緒に久しぶりにお酒を呑んでいた。
はじめはチンスクがチェリンのブティックに就職出来たことで、みんなおめでとうと盛り上がっていた。しかし、ヨングクは
「チェリンの下で働くなんて俺なら恐ろしくて嫌だ」と叫んでいた。もっともチェリンはユジンを監視するために、一緒に住んでいるチンスクを情報屋として雇ってみただけなので、その感は当たっているのだが、チンスクは利用されているとも知らず、浮かれていた。
しかし、そのうち悪酔いしたチンスクが
「ミニョンさんと働くなんて、ユジンは酷すぎる。サンヒョクがかわいそうよ」と喚きだしたので、ヨングクにチンスクを頼んで、サンヒョクとユジンの2人は先に店を出ることになった。

サンヒョクはユジンと歩きながら、穏やかな顔で微笑んだ。昔からユジンは高いところを歩くのが好きだった。サンヒョクはよくハラハラしていたが、自分もユジンのようにやってみたくなって、道端の花壇にのって歩いてみた。
「なあ、ユジン、昔君がこうやって高いところを歩いてると、心配で心配で手を握ってあげたかったんだ。だから、いつでも必要な時に僕の手を握ってよ。僕はいつでも側にいるから。でも僕が君を必要なときはちゃんと握ってくれよな」

そして手を握ったあと、ユジンをぎゅっと抱きしめた。ユジンは遠い昔、サンヒョクの手を拒んでおいて、チュンサンが差し出した時には握ったことを思い出して、申し訳ない気分になった。今度こそサンヒョクと幸せになろう。そう考えて慌ててぎゅっと抱きしめ返したのだった。

一方で、ユジンはミニョンとの打ち合わせも回数を重ねていた。少しずつ頑なだった心がほぐれて、まあまあ会話が出来るようにはなってきた。ユジンが一生懸命書類を読んでいると、ミニョンがふいに
「ユジンさんはいいにおいがしますね。ああシャンプーか。」と微笑んだ。ミニョンは急にドキッとする事を言うので、戸惑ってしまう。ミニョンは続けて
「そうだ。週末に会社のパーティーがあるんですよ。ユジンさんも来ますよね?」と振ってきた。
「さあ、わたし着ていく物もないですし」
というユジンに
「ユジンさんなら何でも似合いますよ。だから大丈夫です」とたたみかけてくるミニョンだった。
そこに、キム次長、チョンア、差し入れを持参したチェリンまで来たので、話は終わった。ミニョンはキム次長とチョンアと出て行くユジンに向かって
「期待してますからね」と念押しをしてきた。
そんなミニョンを見て、チェリンは不安そうに聞いた。
「ねえ、ユジンと話してた期待してるって何のこと?」
「ああ、会社の創立記念パーティーだよ。ユジンさんを呼んだんだ。チェリンも来るだろ?」
「わたし、ミニョンさんに買ってもらったドレスを着るのやめようかな。ユジンに見せちゃったのよ。そうしたら、似合わないって言われて。他のを着るわ。」
「ユジンさんがお前の彼氏じゃないだろ。なんで言うことを聞くの?」
「そうね、やっぱりあれを着ていくわ。でもわたしもファッションショーに行かなくちゃいけないから、少ししたら帰るわね」

チェリンは、先日ミニョンに胸元と背中が開いた黒のドレスを買ってもらっていた。当日はそれを着て行く約束になっていた。
チェリンにはある企みがあり、わざと言われてもいない悪口を言ったと吹き込んだのだ。
チェリンは密かにほくそ笑んだ。





















