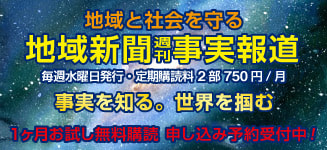(記事中の写真はクリックで拡大します。プライバシー保護等の為、人の顔部分に修正を加えていることがあります)
どうも、こんにちは。
本シリーズで何度か紹介しました‘神様のデパート’粟田神社。今回はこの古社で行われる神事「夜渡り神事」を、今回を含めて3回に渡って紹介します。
(※何故私が、粟田神社を‘神様のデパート’と呼ぶのか、興味ある方はシリーズ第81回、第82回、第83回をご覧下さい)
また、有名な青森県ねぶた祭りの元になったという説もあるという、「粟田大燈呂(あわただいとうろ)」も観て回ります。
さて本題の前にまず、粟田神社の大祭「粟田祭」についての解説を。
粟田神社HPの「粟田祭」紹介ページには以下の様な記述が(以下、引用)。
>粟田祭のはじまりは、長保3年(1001)の旧暦9月9日の夜、一人の神童が祇園社に現れて神人に「今日より7日後に祇園社の東北の地に瑞祥が現れる。そこに神幸すべし」と告げられました。7日後の9月15日にお告げのとおり瑞光が現れたため御神幸が為されました。その瑞光が現れた場所が当社であり、これが粟田祭の始まりとされています。
(引用ここまで)
その神託のお告げどおり瑞光(ずいこう。吉兆を示すめでたい光)が粟田神社に現れた旧暦9月15日頃が大祭の行われる10月半ば頃というわけです。
この大祭は4日間にわたって行われ、その中の神事のひとつが「夜渡り神事」と「れいけん祭」です。
この「夜渡り神事」と「れいけん祭」についても、粟田神社HPの「粟田祭」紹介ページには以下の様に記述があります(以下、引用)。
>体育の日前夜には「夜渡り神事」「れいけん」が執り行なわれます。約400年前の旧暦9月14日の夜、おおきな石の上に瓜が覆っており、そこに御金札(金のおふだ)があって光り輝いていた。その金札には「感神院新宮(粟田神社の旧社名)」と銘があったため神の御降臨であると金札は神社に納められ、金札の現れた石は「瓜生石(うりゅうせき)」と名付けられました。
この故事により毎年、御神宝の阿古陀鉾と地蔵鉾が「夜渡り神事」とよばれる行列を為し、金札の現れた瓜生石の周りを三度巡拝する「れいけん」の神事を執り行います。「れいけん」とはおそらく「霊験」ことであり、粟田の大神様が御降臨されたことを畏れ敬い感謝を表す祭りです。「れいけん」の後氏子町内を巡ります。
(引用、ここまで)
シリーズ第88回で紹介した「瓜生石(うりゅうせき、かしょうせき)」。


1300年以上前に、「この石の上に一夜にして胡瓜が芽生え、成長して、花が咲き、実がなった」「祇園社の祭神・牛頭天王が降臨した」などの伝説が残る石ですが、この霊石を巡る神事が行われるのです。
またこの「夜渡り神事」で巡行する「大燈呂」には、粟田神社に関連深い神話や伝承をテーマにしたものがほとんどですので、本シリーズでもとりあげてみたいと思いました。
まずは交通アクセスから。

今回は京都市営地下鉄「蹴上(けあげ)」駅から、三条通りを西へ。
他にも、市営地下鉄「東山」駅や、市営バス「神宮道」停留所などがあります。
三条通りを歩きますと、あちらこちらで祭の準備が始まっていました。





粟田神社境内にも訪れます。





本殿に礼拝して、境内を見渡しますと、いろいろなものが。


今年(令和元年、2019年)の10月12日は大型台風が関西地方を通過しましたので、翌13日に予定の「夜渡り神事」は無事開催されるかを心配しましたが、台風通過後の天候は荒れておらず、予定通り開催されるようで、少しほっとしました。

一旦離れ、夜渡り神事と巡行が始まる18時頃に再び粟田神社付近を訪れます。
日が沈む前から、もう既に「大燈呂」が準備されています。



巡行が開始される18時頃になりますと、次第に日が沈み、暗くなってきます。


いよいよ巡行が始まります。



次に今年(令和元年、2019年)に巡行した「大燈呂」も紹介していきたいと思いますが、長くなりますので、ここで一旦切ります。

今回はここまで。
続きはシリーズ次回に。
*粟田神社へのアクセス、周辺地図はこちらをご覧下さい。
*粟田神社のHP
https://awatajinja.jp/
*『京都妖怪探訪』まとめページ
https://kyotoyokai.jp/