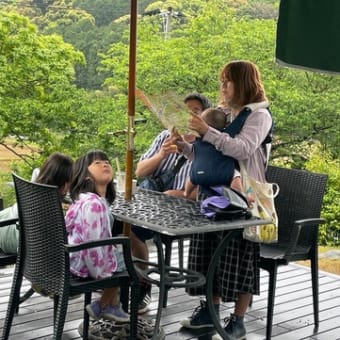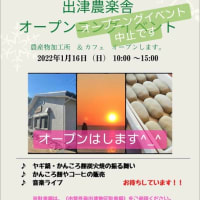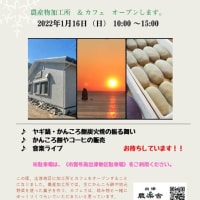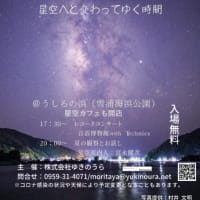雪浦くんちは、雪浦の氏神様を祀っている熊野神社の秋の大祭です。江戸時代から400年近く受け継がれてきました。

13時から、上のお宮で厳かに「神幸祭(しんこうさい)」と呼ばれる、神事が行われました。

境内の広場では、砂切(しゃぎり)と西区による奉納踊り 獅子舞。

その後、お宮からの急な階段を、お神輿、舞姫、砂切の一行の行列が続きます。おくだりです。

今年は、6年ぶりに西区の獅子舞が奉納されることで、たくさんの人が楽しみにしていました。
また、福岡からのくんちツアーも企画されていて、お宮の下の広場は、たいへんな数の人で埋め尽くされています。

お宮の階段を下ったところで、奉納踊り 獅子舞の披露。
獅子舞 かっこいい

お下りの一行は、しゃぎりながら、下宮(川上神社)まで続きます。

下宮に御神体が安置され、参着祭(さんちゃくさい)と呼ばれる神事が行われます。

今年の舞姫は、5・6年生の4人。舞姫による「浦安の舞」は、全国的に浦安の舞が広められた最初の年である昭和15年から、雪浦でも奉納されるようになり、その歴史は75年に及びます。
神事の間に、砂切があります。
雪浦くんちの砂切は、子供たちが主役です。低学年の子供が締太鼓をからい(担ぎ)、高学年の子供が叩きます。
この締太鼓に中学生の打つ大太鼓が加わります。くんち笛の、美しい物悲しい調べが、秋の空に響き渡ります。
雪浦くんちのシャギリは、「砂切」と書きます。このように書かれるシャギリは、雪浦だけだそうです。(長崎のくんちは、「シャギリ」とカタカナで書かれます。)
担がれた大太鼓を宙を舞いながら跳ね回るようにして叩くのが雪浦の独特なスタイルで、この激しい動きが、砂を切るようであることから、「砂切」と書かれるようになったようです。

境内も、たくさんの人

そして、西区の奉納踊り 獅子舞 今年は、二人の女性が大太鼓を叩きました。
今年は、二人の女性が大太鼓を叩きました。

太鼓の軽快なリズムと、迫力の舞。集まった人々は、笑顔と手拍子で見守りました。
素晴らしいくんちです。かっこいい

一日目の締めは、祝い餅まきでした。

雲一つない空 これぞ くんち晴れ


お上りは、10月18日 10時からです。
・・・・・・・・・・・と終わらないのが雪浦くんち。
くんちの夜の 無礼講の直会(なおらい)が、またすごいんです

各家々では、このようにご馳走が並びます。
上の写真のお椀は、「がねじる」といって、雪浦くんちの名物です。つがねというカニをすりつぶして作った汁物です。珍味です。おいしい
一昔前までは、次から次へ、お客さんが入ってきて、家のご主人も知らない人も、一緒に飲んだり食べたりしていたそうですが、今は、事前に声をかけていただき、お伺いするようになってきています。

私は、この日は3軒のお宅をまわらせていただきました。


どこでも、すごいご馳走です。ありがとうございました。


こうして、長い長いくんちの一日目は更けていきました。