kurogenkokuです。
245冊目は・・・。
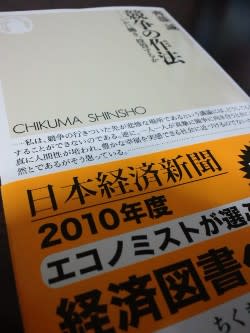
競争の作法
齊藤 誠 著 ちくま新書
アマゾンの書評が大きく2つに分かれていたので、逆に興味が沸き購入しました。
著者の主張をおおまかに纏めてみると。
2002年から2007年の期間実質GDPは505兆円から561兆円へと11.1%成長。
↓
実質家計消費は、291兆円から310兆円へと6.5%しか拡大していない。
↓
この期間の経済成長を支えたのは純輸出と設備投資。
↓
「目に見える円安(対ドルの為替)」、「目に見えない円安(日本の消費者物価が横ばいだったのに対して、米国の消費者物価は10%上昇していた)」によって、20%の価格競争優位を持った輸出企業(製造業)が好調で、景気回復に貢献した。
↓
2つの円安が生まれた原因は、日銀のゼロ金利政策によるものが大きい。
↓
円安バブルがいつかははじけることが分かっている。
でも輸出企業は利益を株主に還元することなく生産拡大のための設備投資を続けた。
↓
コストカットのために人件費は絞られ、一部労働者は貧困化へ。
↓
それが「幸福なき豊かさ」の実態
↓
豊かさは幸福を支えるが、豊かだからといって幸福であるとはかぎらない
ここまでが第3章までの要約です。統計から考えられる具体的な考察は素人の私にもわかりやすかった。
⇒ただし、特定企業に対して攻撃的な論評が気になりましたが・・・。
一方、第4章「豊かな幸福を手にするための投資方法」については、第3章までの内容と異なり、具体性な見解が少ないなぁと感じました。
その辺に後味の悪さも残してしまったのかなという気がします。
(勇気を持って)かなりズバッと切り込んだ内容なので賛否両論おこるのは当然かと。
逆にそこが新鮮でもあって、一読の価値はあるかなというのが個人的感想です。
そういえば診断士受験の際、「経済学は仮説の学問だ」とおっしゃっていた講師がありました。
「仮説」であるがゆえに賛否両論真っ二つに分かれる。
当時を思い出しながら、感じるものがありました。
【目次】
第1章 豊かさと幸福の緩やかな関係
第2章 買いたたかれる日本、たたき売りする日本
第3章 豊かな幸福を手にするための働き方
第4章 豊かな幸福を手にするための投資方法
<SCRIPT charset="utf-8" type="text/javascript" src="http://ws.amazon.co.jp/widgets/q?rt=tf_mfw&ServiceVersion=20070822&MarketPlace=JP&ID=V20070822/JP/kurogenkoku-22/8001/969032b5-0c01-4d4e-984c-779523fc4aa3"> </SCRIPT>











