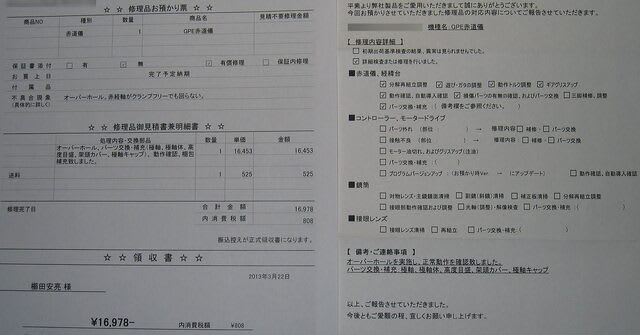さて、3月9日の鳴沢村遠征は、コーン星雲を撮影した後、鏡筒を7cmから13cmに載せ替えて、北天の銀河を狙ってみた。
今まで、未撮影の中から、なるべく構造が判る銀河をと思ってターゲットをNGC2336にしてみた。

【↑NGC2336 きりん座の渦巻き銀河】
Vixen SM-R125S D:130 f:720 UW9mm 80倍 35mm版換算2240mm相当
SP赤道儀+AL90+SkySenser2 PowerShotS90+CHDK ISO:3200 F:2.0 f=6mm
コリメート法 合成F=3.7 S:80秒x21 Noise減算:ON
撮影場所:山梨県鳴沢村 撮影日:2013/3/9 22:10-23:14
Registaxでコンポジット→FlatAideで除算補正→GIMPでトーンカーブ
・43%にトリミング(35mm版換算5243mm相当)・サイズ調整
NGC2336は、明るさは10.5等級で大きさは約7分角程である。しかし北極星の比較的近くにありそれ程高度が高くない。お陰であまり露出時間を長くするとちょっとかぶりの影響が大きかったので80秒露出で撮影した。
本当なら、もう少し銀河の腕が何本もくるくる巻いている画像1、画像2、を期待したのだが、残念ながら、その腕のうち、何本かは腕状に分離せずに埋もれてしまっただろうか。
それでも、渦巻き銀河として、形はしっかり捕らえることは出来たと思う。
近くにIC467と言う銀河もあるのだが、残念ながらギリギリ画角から半分はみ出ていた(汗)
もう少し露出時間を延ばしていれば、腕の様子はしっかり写った気もするが、一年中沈まない銀河なので、又露出をのばして撮影するチャンスもあるだろう。
2013.3.9(3/31)
今まで、未撮影の中から、なるべく構造が判る銀河をと思ってターゲットをNGC2336にしてみた。

【↑NGC2336 きりん座の渦巻き銀河】
Vixen SM-R125S D:130 f:720 UW9mm 80倍 35mm版換算2240mm相当
SP赤道儀+AL90+SkySenser2 PowerShotS90+CHDK ISO:3200 F:2.0 f=6mm
コリメート法 合成F=3.7 S:80秒x21 Noise減算:ON
撮影場所:山梨県鳴沢村 撮影日:2013/3/9 22:10-23:14
Registaxでコンポジット→FlatAideで除算補正→GIMPでトーンカーブ
・43%にトリミング(35mm版換算5243mm相当)・サイズ調整
NGC2336は、明るさは10.5等級で大きさは約7分角程である。しかし北極星の比較的近くにありそれ程高度が高くない。お陰であまり露出時間を長くするとちょっとかぶりの影響が大きかったので80秒露出で撮影した。
本当なら、もう少し銀河の腕が何本もくるくる巻いている画像1、画像2、を期待したのだが、残念ながら、その腕のうち、何本かは腕状に分離せずに埋もれてしまっただろうか。
それでも、渦巻き銀河として、形はしっかり捕らえることは出来たと思う。
近くにIC467と言う銀河もあるのだが、残念ながらギリギリ画角から半分はみ出ていた(汗)
もう少し露出時間を延ばしていれば、腕の様子はしっかり写った気もするが、一年中沈まない銀河なので、又露出をのばして撮影するチャンスもあるだろう。
2013.3.9(3/31)