1 子どもの言語発達過程(概略)
・1歳前後、最初の言葉(初語)を話す。
・その後しばらく、話せる単語の増加ペースは月3~5語程度。
・2歳近く、月30~50語の増加ペースへとスピードアップ。(語彙爆発)
・1歳代、一度にひとつの単語を言うだけ。(一語発話)
・2才ごろ、2語かそれ以上の数の単語をつなげた文での発語も。
(二語発話、多語発話)
・3歳過ぎ、正しい助詞が使われるようになる。
「~したから~」等、文と文をつなげた発話も可能になる。
2 言語習得のメカニズム
1)言語音の習得
・誕生直後の子ども:喉の奥の空間が狭いため、
全身に力を入れて絞り出す叫喚発声。
・生後2・3カ月:喉の奥が広がり、リラックスした状態での発生(クーイング)
・0歳半ばごろ:様々な音声を出してみて遊んでいるように見える。(声遊び)
・8カ月過ぎ:「バババ・・」のような「子音+母音」の繰り返し音声(基準喃語)
を発することができるように。
・聴覚障害児では、基準喃語への移行が見られないことから、
音声発達には、自分が発した声を聞くという経験が重要であることが分かる。
・0歳半までに:自分の名前など、単独かつ高頻度で耳にする単語が
再認できるようになる。
・0歳後半:音のつながる確率や、その言語における音のつながり方の
特徴などを手掛かりとして、発語中の単語を見つけ出せるようになる。
・1歳までに:自分の母語では区別しない音どうしを違う音として聞かなくなる。
異なる話者が異なる音質で話す同じ単語を
同じものと聞くことができるようになる。
2)単語の学習
・単語の意味の学習のために、以下の2点の理解が必要。
①話者は何を伝えようとして(何に注意を向けて)その単語を発したのか。
・他者が注意を向けている対象に、自身も注意を向けること(共同注意)
・・・1歳前後からでき始める。
・話者が注意を向けている対象に、単語を結び付けて覚えられるようになる。
・・・1歳半ごろ。
②単語に対応付けるべき概念はどのようなものか。
・1歳前半:1つの単語が指す範囲はどこまでか理解できず試行錯誤。
(ex.ある犬を「ワンワン」と覚えると、他の動物も「ワンワン」)
・1歳後半:対象と結びつけられた単語は、
その対象と形のよく似た物体のカテゴリーの名前と見なせばよいと理解。
正確に単語の意味を推測できるようになる。
・①②などがそろうことで、
1歳後半になると、爆発的な勢いで語を獲得していけるようになる。
参考記事 こちら → 「ことばの発達」
(カテゴリー「学習ノート」の記事)
3)文法の獲得
・文を話すためには、単語のつなげ方についてのルール(文法)を知る必要がある。
・子どもは
文とそれが話された状況との組み合わせを覚えていく。
そこから推測したルールを明らかにしていく。
・状況のどこと文構造のどこをどのように対応付けるかについては、
無数の可能性があり、
子どもが何の知識や構えもなしに学習に取り組むとすれば、
文法獲得は非常に困難なものになると予想される。
・大人は子どもの文法間違いをほとんど直さない。(否定証拠の欠如)
子どもの文法獲得を説明するには、素朴な条件付けではなく、
もう少し具体的な獲得メカニズムが想定されるべきだと考えられてきた。
・文法とは、
文の中で似た働きをする単語(名詞や動詞など)を
どのようにつなげるべきかに関する抽象的なルール。
・文法を身に着けるために、
①単語を文の中で似た働きをする語の種類(名詞、動詞など)へと分類し、
②文を作るためにそれらをどのようにつなげるべきかを見つけ出す。
・子どもは、発語に登場する単語どうしの共起確率を分析して
単語を文類しているのではないかと考えられる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『ボクは、単語も文法も覚えないけどね~』

スネてる ( *´艸`)
・・単語は、5つぐらいは覚えてるんじゃない?
(本年 6月上旬 夜)
(人間のベッドのシーツ上で、だらけるマリン)
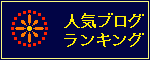
・1歳前後、最初の言葉(初語)を話す。
・その後しばらく、話せる単語の増加ペースは月3~5語程度。
・2歳近く、月30~50語の増加ペースへとスピードアップ。(語彙爆発)
・1歳代、一度にひとつの単語を言うだけ。(一語発話)
・2才ごろ、2語かそれ以上の数の単語をつなげた文での発語も。
(二語発話、多語発話)
・3歳過ぎ、正しい助詞が使われるようになる。
「~したから~」等、文と文をつなげた発話も可能になる。
2 言語習得のメカニズム
1)言語音の習得
・誕生直後の子ども:喉の奥の空間が狭いため、
全身に力を入れて絞り出す叫喚発声。
・生後2・3カ月:喉の奥が広がり、リラックスした状態での発生(クーイング)
・0歳半ばごろ:様々な音声を出してみて遊んでいるように見える。(声遊び)
・8カ月過ぎ:「バババ・・」のような「子音+母音」の繰り返し音声(基準喃語)
を発することができるように。
・聴覚障害児では、基準喃語への移行が見られないことから、
音声発達には、自分が発した声を聞くという経験が重要であることが分かる。
・0歳半までに:自分の名前など、単独かつ高頻度で耳にする単語が
再認できるようになる。
・0歳後半:音のつながる確率や、その言語における音のつながり方の
特徴などを手掛かりとして、発語中の単語を見つけ出せるようになる。
・1歳までに:自分の母語では区別しない音どうしを違う音として聞かなくなる。
異なる話者が異なる音質で話す同じ単語を
同じものと聞くことができるようになる。
2)単語の学習
・単語の意味の学習のために、以下の2点の理解が必要。
①話者は何を伝えようとして(何に注意を向けて)その単語を発したのか。
・他者が注意を向けている対象に、自身も注意を向けること(共同注意)
・・・1歳前後からでき始める。
・話者が注意を向けている対象に、単語を結び付けて覚えられるようになる。
・・・1歳半ごろ。
②単語に対応付けるべき概念はどのようなものか。
・1歳前半:1つの単語が指す範囲はどこまでか理解できず試行錯誤。
(ex.ある犬を「ワンワン」と覚えると、他の動物も「ワンワン」)
・1歳後半:対象と結びつけられた単語は、
その対象と形のよく似た物体のカテゴリーの名前と見なせばよいと理解。
正確に単語の意味を推測できるようになる。
・①②などがそろうことで、
1歳後半になると、爆発的な勢いで語を獲得していけるようになる。
参考記事 こちら → 「ことばの発達」
(カテゴリー「学習ノート」の記事)
3)文法の獲得
・文を話すためには、単語のつなげ方についてのルール(文法)を知る必要がある。
・子どもは
文とそれが話された状況との組み合わせを覚えていく。
そこから推測したルールを明らかにしていく。
・状況のどこと文構造のどこをどのように対応付けるかについては、
無数の可能性があり、
子どもが何の知識や構えもなしに学習に取り組むとすれば、
文法獲得は非常に困難なものになると予想される。
・大人は子どもの文法間違いをほとんど直さない。(否定証拠の欠如)
子どもの文法獲得を説明するには、素朴な条件付けではなく、
もう少し具体的な獲得メカニズムが想定されるべきだと考えられてきた。
・文法とは、
文の中で似た働きをする単語(名詞や動詞など)を
どのようにつなげるべきかに関する抽象的なルール。
・文法を身に着けるために、
①単語を文の中で似た働きをする語の種類(名詞、動詞など)へと分類し、
②文を作るためにそれらをどのようにつなげるべきかを見つけ出す。
・子どもは、発語に登場する単語どうしの共起確率を分析して
単語を文類しているのではないかと考えられる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『ボクは、単語も文法も覚えないけどね~』

スネてる ( *´艸`)
・・単語は、5つぐらいは覚えてるんじゃない?
(本年 6月上旬 夜)
(人間のベッドのシーツ上で、だらけるマリン)
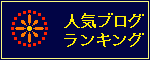




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます