※「DSM-5」の分類に基づいた説明。
訳語は、日本精神神経学会の「DSM-5病名ガイドライン」による。
(( )内は、ICD-10の病名)
4 抑うつ障害群
(うつ病エピソード、反復性うつ病性障害)
・日本のうつ病12カ月有病率(過去12カ月に診断):1~2%
生涯有病率:3~7%
・一般に、女性、若年者に多いとされるが、
日本では、中高年でも頻度が高く、うつ病に対する社会的影響が大きい。
・うつ状態が
「ほとんど一日中」「ほとんど毎日」「同じ2週間の間に」継続し、
以下のうち、5つ以上ある場合(①と②のどちらかは必須)に診断される。
①抑うつ気分
②活動への興味、喜びの減退
③大きな体重変化(1カ月で5%以上)、食欲減退又は増加。
④不眠または過眠。
⑤精神運動焦燥または制止。
⑥疲労感または気力の減退。
⑦無価値感、過剰か不適切な罪責感。
⑧思考力・集中力の減退、決断困難。
⑨死についての反復思考、反復的な自殺念慮または自殺企図。
・思考障害、妄想が出現して、自殺への志向が強まるため、
健康な状態に比して、およそ5倍の自殺リスクがある。
・自殺防止を念頭に置く必要がある。
・治療は、
①休養を優先した環境調整。
②心理支援・心理療法(認知療法・認知行動療法を含む)
③セロトニン系・ノルアドレナリン系を調整する抗うつ薬を中心とした薬物療法。
・うつ病は再発・再燃しやすい疾患であるため、
3~4カ月の急性期(症状改善)を経て、
最低6カ月(高齢者は1年以上)の維持期の間は、治療継続が必要。
*慢性うつ病:病状が6カ月以上遷延した場合。
*気分変調症(持続性抑うつ障害)
2年以上軽鬱・気分変調(不機嫌も含む)が遷延する病態。
5 不安症群、強迫症、および関連症群
(恐怖性不安障害、全般性不安障害、その他の不安障害、
強迫性障害、パニック障害 等)
・日本の不安症12カ月有病率(過去12カ月に診断):5.5%
生涯有病率:9.2%
・不安症は、
心因が中心でなく、身体的要因(脳機能異常)が関与していると考えられている。
〇パニック症
・大脳辺縁系(特に偏桃体)の機能異常があり、
恐怖が誤作動しやすい。
・繰り返される予期しないパニック発作が特徴で、
しばしば広場恐怖ないし、これに準じる回避行動をきたす。
・また起こるのではないかという不安(予期不安)や広場恐怖などが、
1カ月以上継続している場合にパニック症と診断される。
・特に女性に多く、青年期に増加して成人期にピークを示す。
・未治療で経過すると、慢性経過(憎悪寛解の繰り返し)を呈する。
*パニック発作
激しい恐怖または、強烈な不快感が突然生じ、数分以内にピークに達する。
息切れ、吐き気、胸痛、「死んでしまうのではないか」という恐怖感。
*広場恐怖
店や雑踏、公共交通機関など、逃げ出すことができないと感じる状況に
対して、不安や恐怖を感じ、その利用を回避する。
・標準治療は、以下の組み合わせ。
①選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)と
長時間型抗不安薬を中心とした薬物療法。
②認知行動療法
〇全般性不安症(全般性不安障害)
・慢性の生活全般にわたる不安や心配があり、
苦痛と生活機能の障害をきたしている場合に診断される。
・パニック症同様の治療が標準的。
〇社交不安症(社交不安障害)
・家族研究から直接血縁者の発症率が4~5倍、
一卵性双生児での一致率30~40%で、
・遺伝的要因があり、偏桃体の過敏反応が見られるなど、
生物学要因のある病態が想定されている。
・パニック症同様の薬物療法と認知行動療法(暴露療法)が標準治療。
〇強迫症(強迫性障害)
・強迫観念・強迫行為のため、苦痛と生活機能の障害をきたす病態。
・薬物・身体疾患や他の精神疾患の除外を行った上で診断される。
・チックの有無、病識(自分自身の強迫観念・行為の洞察)の程度も診断基準に。
・セロトニン系の関与と前頭葉-皮質下回路の機能異常が想定されている。
・うつ病の合併が多い。(3割程度)
・パニック症同様の治療が標準的。
・認知行動療法としては、暴露反応妨害法が用いられる。
・強迫観念の治療は強迫行為の治療に比べて困難。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
もう、、、リラックスし過ぎじゃない? 1Fのソファなのに・・

『・・・だって、、』
前記事画像より、ちょっとだけ左手が上に上がっています。
(2018年 5月下旬 夜 撮影)
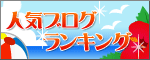
訳語は、日本精神神経学会の「DSM-5病名ガイドライン」による。
(( )内は、ICD-10の病名)
4 抑うつ障害群
(うつ病エピソード、反復性うつ病性障害)
・日本のうつ病12カ月有病率(過去12カ月に診断):1~2%
生涯有病率:3~7%
・一般に、女性、若年者に多いとされるが、
日本では、中高年でも頻度が高く、うつ病に対する社会的影響が大きい。
・うつ状態が
「ほとんど一日中」「ほとんど毎日」「同じ2週間の間に」継続し、
以下のうち、5つ以上ある場合(①と②のどちらかは必須)に診断される。
①抑うつ気分
②活動への興味、喜びの減退
③大きな体重変化(1カ月で5%以上)、食欲減退又は増加。
④不眠または過眠。
⑤精神運動焦燥または制止。
⑥疲労感または気力の減退。
⑦無価値感、過剰か不適切な罪責感。
⑧思考力・集中力の減退、決断困難。
⑨死についての反復思考、反復的な自殺念慮または自殺企図。
・思考障害、妄想が出現して、自殺への志向が強まるため、
健康な状態に比して、およそ5倍の自殺リスクがある。
・自殺防止を念頭に置く必要がある。
・治療は、
①休養を優先した環境調整。
②心理支援・心理療法(認知療法・認知行動療法を含む)
③セロトニン系・ノルアドレナリン系を調整する抗うつ薬を中心とした薬物療法。
・うつ病は再発・再燃しやすい疾患であるため、
3~4カ月の急性期(症状改善)を経て、
最低6カ月(高齢者は1年以上)の維持期の間は、治療継続が必要。
*慢性うつ病:病状が6カ月以上遷延した場合。
*気分変調症(持続性抑うつ障害)
2年以上軽鬱・気分変調(不機嫌も含む)が遷延する病態。
5 不安症群、強迫症、および関連症群
(恐怖性不安障害、全般性不安障害、その他の不安障害、
強迫性障害、パニック障害 等)
・日本の不安症12カ月有病率(過去12カ月に診断):5.5%
生涯有病率:9.2%
・不安症は、
心因が中心でなく、身体的要因(脳機能異常)が関与していると考えられている。
〇パニック症
・大脳辺縁系(特に偏桃体)の機能異常があり、
恐怖が誤作動しやすい。
・繰り返される予期しないパニック発作が特徴で、
しばしば広場恐怖ないし、これに準じる回避行動をきたす。
・また起こるのではないかという不安(予期不安)や広場恐怖などが、
1カ月以上継続している場合にパニック症と診断される。
・特に女性に多く、青年期に増加して成人期にピークを示す。
・未治療で経過すると、慢性経過(憎悪寛解の繰り返し)を呈する。
*パニック発作
激しい恐怖または、強烈な不快感が突然生じ、数分以内にピークに達する。
息切れ、吐き気、胸痛、「死んでしまうのではないか」という恐怖感。
*広場恐怖
店や雑踏、公共交通機関など、逃げ出すことができないと感じる状況に
対して、不安や恐怖を感じ、その利用を回避する。
・標準治療は、以下の組み合わせ。
①選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)と
長時間型抗不安薬を中心とした薬物療法。
②認知行動療法
〇全般性不安症(全般性不安障害)
・慢性の生活全般にわたる不安や心配があり、
苦痛と生活機能の障害をきたしている場合に診断される。
・パニック症同様の治療が標準的。
〇社交不安症(社交不安障害)
・家族研究から直接血縁者の発症率が4~5倍、
一卵性双生児での一致率30~40%で、
・遺伝的要因があり、偏桃体の過敏反応が見られるなど、
生物学要因のある病態が想定されている。
・パニック症同様の薬物療法と認知行動療法(暴露療法)が標準治療。
〇強迫症(強迫性障害)
・強迫観念・強迫行為のため、苦痛と生活機能の障害をきたす病態。
・薬物・身体疾患や他の精神疾患の除外を行った上で診断される。
・チックの有無、病識(自分自身の強迫観念・行為の洞察)の程度も診断基準に。
・セロトニン系の関与と前頭葉-皮質下回路の機能異常が想定されている。
・うつ病の合併が多い。(3割程度)
・パニック症同様の治療が標準的。
・認知行動療法としては、暴露反応妨害法が用いられる。
・強迫観念の治療は強迫行為の治療に比べて困難。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
もう、、、リラックスし過ぎじゃない? 1Fのソファなのに・・

『・・・だって、、』
前記事画像より、ちょっとだけ左手が上に上がっています。
(2018年 5月下旬 夜 撮影)
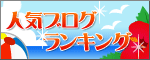




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます