9月30日、関西のメディアは前日の堺市長選で日本維新の会が擁立した候補が敗北したことを大きく報じていた。維新の橋下代表は大阪都構想で「堺はなくならない。変わるのは役所組織だ」と訴えたそうだが、堺市民は、名前だけ残して統治機構を変えてしまうことに不安を抱いたのではないか。真っ当な判断だったというべきだろう。元町に向かう電車の中でそんなことを考えていて、ふと山崎豊子さんが長年、堺市に暮らしておられることを思い出した。何かコメントが出ていないか携帯で調べてみたら、速報で訃報が流れていた・・・
今から書こうとしているのは、堺市長選のことでも山崎豊子さんのことでもない。もっとローカルでぼくにとって切実な話題だ。この日、世の中を知るリアルな情報源として頻繁に利用していたジュンク堂明石店と元町の海文堂書店が閉店したのである。
ぼくが元町に向かっていたのは、海文堂書店を最後に訪れておきたかったからだ。地域版を除いて大きなメディアに報じられることはなかったが、大勢の人が詰めかけていた。レジには長い行列ができている。こんなに混雑したのは阪神淡路大震災後に再開して以来のことではないだろうか? カメラをもった人や大きめのバッグをもった遠方から来られたらしい人も多い。それなのに、店内はざわついていなくて、むしろ人の気配が心地よい。たぶん、みんなの呼吸が深くなっていたからだろう。だれもが愛おしそうに棚を見つめ、本を手に取り、店員さんと言葉を交わし、この店の空気に触れて、その感覚を皮膚に沁み込ませようとしていた。9つに分かれている各ゾーンの担当者はほぼ全員が店に出ておられたようだ。児童書の田中さんは、いつも通り棚の前でお客さんの相談に丁寧に応じておられた。そして、人文書の平野さんの姿も見られる。
店に入ってすぐ、ブックフェアのコーナーには、各分野の担当者が選んだ、多種多様な本が並んでいる。その中で、ぼくの目に留まったのは『「本屋」は死なない』(石橋毅史、新潮社)、『理想の書店』(青田コーポレーション出版部)、『名物「本屋さん」をゆく』(井上理津子、宝島SUGOI文庫)、『書店の棚 本の気配』(佐野衛、亜紀書房)、『本の声を聴け』(高瀬毅、文藝春秋)・・・『疎開した40万冊の図書』(金謙二、幻戯書房)は中田邦造をはじめとする太平洋戦争末期の戦災から本を守った日比谷図書館員をはじめとする人々の記録だ(この本が映画化されていることは今日になって知った)。少し移動すると『さようなら、うにおこる』(小島水青、中央公論社)、『さようなら、手をつなごう』(中村航、集英社文庫)、『さようなら、愛しい人』(レイモンド・チャンドラー、村上春樹訳、ハヤカワ・ミステリ文庫)、『さようなら、オレンジ』(岩城けい、筑摩書房)、『さようなら、私』(小川糸、幻冬舎文庫)、『さようなら、コタツ』(中島京子、集英社文庫)・・・『みなさん、さようなら』(久保寺健彦、幻冬舎文庫)、『日本人はなぜ「さようなら」と別れるのか』(竹内整一、ちくま新書)。それにしても、よく集めたものだ! さらに目を転じると「いっそ この際 好きな本ばっかり」のコーナー。担当者が好みの本を選んでコメントを添えているのだが、ほとんど完売していた。店員と客の想いが響きあっていた証だろう。振り返ると「いっそ この際 好きな本 うらばん」の張り紙。官能小説を集めたこの棚と平凡社在庫希少本は人文書の平野さんが担当したそうだ。「海文堂の棚は私にとって、社会のいろんなことへ興味を広げてくれる学校でした」という、神戸新聞の田中伸明記者のコメント(「<きょういく部屋>〝色気〟のある本屋の閉店」)が、この書店の人文書コーナーファンの気持ちを代弁してくれている。
海文堂と言えば海事関係の品揃えが豊富なことで知られているが、ぼくにとっては一階奥の人文書コーナーと、2階奥の美術書コーナーとギャラリーが魅力だった。一般の書店では、けっして目立つところには置かれないであろう本が、しっかりと面出しで並んでいたりする。掲示はあっても多くは地味なもで、本そのものより目立つことはなかった。本自体に語らせる。本の力を信頼して、その力を最大限に引き出す。だから心が動く。棚と向き合っていると、その時々の自分にとって刺激的な本が自然に目に飛び込んでくる。ここは、ぼくにとって自分を発見する場所でもあった。特定の本や展示を求めて行くのではなくて、ふらりと立ち寄って意外な発見をする喜びがそこにあった。
児童書も充実していた。当初は元社長の島田誠さんが担当しておられて、専門家に選書を依頼し、読書相談、こどもの育児教育相談コーナーも作られたそうだ。その後、島田さんは社長を継ぎ、ギャラリーを運営。各ゾーンの担当者は仕入れから陳列まで大きな裁量権が与えられて「専門店の集合」を目指したという。本は、売れ筋だけではなく、担当者のセンスで選ぶ。9部門の各ゾーンにそれぞれ担当者のデスクがあって、未整理の本や書類が無造作に積まれていた。担当者デスクのほかに一階の中央にカウンター、レジではない、申し込みや相談コーナーになっている。従業員は月替わりのブックフェアを順に任され、担当分野とは関係なく好きな本を自由に仕入れることができたという。中には本すら並べない猛者もいたという逸話が、朝日新聞(兵庫)「消える灯火 海文堂書店閉店」(3)『従業員は「棚の社長」』で紹介されている。
(1)老舗にネットの荒波
(2)1・17感じた本の力
(3)従業員は「棚の社長」
(4)「海の人」集い育った
(5)惜別「心のふるさと」
神戸・海文堂書店、99年の歴史に幕 数百人に見守られ
「マニアックになってもいい」「棚に思いをぶちまけろ」という、この書店の経営が利潤追求のための効率化と相反することは明らかだ。同じ元町から三宮に出て全国に広がったジュンク堂とは逆に、中心街から少し外れた同じ場所で「神戸の文化拠点」を目指した海文堂が私たちに伝えようとしたメッセージとは何だったのだろう?
ジュンク堂は元町にあった大同書房が1976年に名前を変えて三宮センター街に移転したのが始まりである。店内で立読みをする客のために腰を掛けて読める場所を提供したのは画期的だった。大阪の堂島に進出した時は、立派な机と椅子が用意されていて客は競って場所取りをし、図書館のように本を積み上げて読んだ。海文堂とジュンク堂は共に神戸の書店文化の象徴的存在だったが、まったく異なる運命をたどることになった。
ジュンク堂の仙台ロフト店に勤めておられる佐藤純子さんの「神戸の夜は車窓めし 女のひとり飯」には海文堂訪問記が愛情深く描かれている。
ツイッターにも海文堂の閉店を惜しむ声があふれた。
「愛されるという勝ち方がある」ってなんかのCMで言ってたけど、海文堂書店さんほど愛されてる書店もないと思う。(海乃宝石+紫電改 @marine_garnet)
海文堂の最後のシャッターを閉めるとき、待っていた多くのお客さんの前で、「リアル書店でもっと本を買ってください。そうでないと、この国から本屋がなくなってしまいます。」と店長の福岡さんがおっしゃった。町に本屋さんがあることが、生活をどれだけ豊かにするか。聞いていて、涙が出てきた。(夏葉社 @natsuhasha)
この時の様子が動画「神戸元町海文堂 閉店の挨拶」に残されている。
これほどまでに愛され、求められた海文堂の経営を圧迫した要因は何だったのか。街の本屋さんが、利潤を出すことを第一義的に考えるのではなく、人と本を直接つなぐという理念を貫いて本屋が生き残るには、どのような条件を満たせばいいのだろうか。それは、ネット社会や市場経済の壁をどう乗り越えるかという問題でもあるだろう。「時間泥棒」に憑りつかれた人や街に豊かな時間を取り戻す手立ては、きっと見つかるはずだ。
翌日、海文堂のホームページに以下のような挨拶が掲載された。
海文堂書店は、2013年9月30日をもちまして閉店いたしました。長年にわたりお引き立てくださいまして、本当にありがとうございました。本と人、人と人の息づかいに満ちた本屋さんに、どうかこれからも足をお運びください。そして、皆様お一人おひとりにたくさんの本とのよい出会いがありますことを願っております。海文堂書店一同
海文堂に先立って、9月25日には紅茶専門店の草分けだった大阪・堂島のムジカが閉店し61年間の歴史に幕を下ろしていた。ムジカには、毎日新聞ビルの地下にあった69年頃から通い始め、すぐそばの路地に移転してからもよく訪れていた。神戸店は営業を続けるようだし、茶葉は、これまで通り我が家に近いアリエルで求めることができる。だが、海文堂と時期を同じくして、自分が生きてきた足跡を辿る目印が消えていくのは、自分の存在の実感が薄れていくようで、とても寂しい。










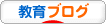

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます