年の瀬に届いた『図書館雑誌』(2012.12)に「IFLAヘルシンキ大会レポート」が掲載されていたので、ざっと目を通した。8月14日の全体会でヘルシンキ大学のユリア・エンゲストローム(Yrjö Engeström)教授がおこなった"Towards knotworking : Designing a new concept of work in an academic library"(「ノットワーキングに向けて:大学図書館の仕事にたいする新しい構想を描く」)と題する講演についてのコメントを探したのだが、7件の報告のうち、これに触れているものは見当たらなかった。
講演のベースになっているのは、2009年から2010年にかけてヘルシンキ大学の図書館員たちが研究者と共同で新しい図書館サービスの開発に取り組んだChange Laboratoryである。当時、わたしは、この取り組みに注目して、学校図書館にかかわる人たちの集まりなどで何度か紹介してきたが自分たちに引き寄せて関心をもってくださる方はほとんどおられなかったようだ。その理由が図書館界の事情に疎いわたしにはよくわからない。
取り組みの概要はこうだ。情報の電子化が進んだことで研究者は研究室にいながら新しい情報の水脈を求めて直接的に情報にアクセスしてリサーチを行い、学生たちも電子書籍や電子情報にアクセスして読書や勉強をするのが普通になった。ヘルシンキ大学Viikki Science Libraryの職員たちは、そうした情報行動をとる研究者や学生と直接的に触れ合う機会が少なくなっていくことに危機感をいだくようになる。自分たちの仕事は、単にデジタル情報を仲介するだけでいいのだろうか? 図書館員に求められる専門性とは何か? これから自分たちのやるべき仕事は何か? かれらは単なる技術論を超えて自らのアイデンティティにかかわる根源的な問題意識をもって同大学のCRADLE(Center for Research on Activity, Development, and Learning「活動、発達、学習に関する研究センター」)のエンゲストローム教授とともに「図書館におけるノットワーキング」というプロジェクトをはじめた。
ノットワーキングとは、境界交差すなわち越境することであり、相手の領域に相互に踏み込む協働のかたちである。電子化への対応として取り組んだノットワーキングは、図書館サービスの質的な転換を生みだすことになる。それは単なる資料・情報の仲介者にとどまらず、研究者のパートナーあるいはクライアントとして研究により深くかかわっていくことであった。それには徹底的な現状分析と拡張的な再設計、そして粘り強い取り組みが必要であることはいうまでもない。
エンゲストロームの講演の様子とパワーポイントは下記で見ることができる。
The plenary talk online in video
Viikki Science Libraryの取り組みが生み出したのは、利用者が抱えている課題の解決に資すると思われる「資料・情報を提供する」サービスから一歩踏み込んで、利用者の「問題解決に直接的にかかわる」サービスへの転換といっていいだろう。それは大学図書館ばかりでなく、当然、公共図書館でも検討されるべき課題でもあるはずだ。この点に関しては、私が非常勤講師を務める大学でお世話になっている歌野博さんが『人文会News』(no.113 2012.9)に寄せられた「公共図書館のディストピア、その傾向と対策」と題する論考に注目したい。この論考で歌野さんは、国会図書館法が改正されてデジタル資料の国会図書館への電子納本が義務付けられ、図書館における電子書籍利用モデルの実現に向けて一歩を踏み出したことによって、やがて公共図書館(職員)の存続そのものが危ぶまれることになるとして、やはりサービスの見直しを提案しておられる。歌野さんは、1970年代に確立された「貸出パラダイム」(貸出を公共図書館サービスの中核に据える路線)が「市民の図書館」の形成に果たした役割を高く評価しながらも、時代の変化に応じた転換が必要だという。資料と利用者を媒介し、資料提供をとおしてクライエントの課題解決を「支援」するといった従来の図書館サービスから脱却すべきだというのだ。それは「間接性から直接性の方向へ舵を切る。資料からの相対的な自立を図ること。ライブラリアン自身が資料代わりになること」(p.34)である。資料依存から脱却して図書館のありようを変えようという試みなら、すでに始まっている。たとえば「場所としての図書館」、あるいは「図書館の触媒機能」を発揮して他の機関との連携・コラボレーションによって地域文化を掘り起し、住民・市民の間に文化的発芽を促す試みなどがある。しかし、その場合、提供したサービスをどのように利用するか(しないか)、そして、それがどのような効果をもたらすかは、全面的に利用者に委ねられていて、そのかぎりにおいて「図書館サービスの間接性」は維持されたままである。歌野さんによれば、図書館のサービスも一般の行政サービスや弁護士のように高度の専門性もってクライエントが抱える課題を「(資料に委ねるのではなく)人が直接的に解決するサービス」へ転換することが必要だという。たとえば国立国会図書館の「調査及び立法考査局」の仕事がある。これをモデルにして公共図書館がシンクタンクとなって自治体行政への直接的なサービスをおこなう、いわば地方議員の政策秘書的な機能を担うといったことも考えられるという。この考えを敷衍すれば市民への直接的なサービスの可能性も見えてくるだろう。市民や住民が日常生活の中で抱える問題に対して直接的な解決策を提案するサービスはできないものだろうか。それは、ただ回答や資料を提供するだけでなく、さらに利用者のふところ(コンテクスト)に踏み込んだ相談業務となるだろう。図書館の調査能力を駆使して提案や選択肢を提供することで問題を抱えた住民のパートナーとなるのである。その萌芽は、たとえば鳥取県立図書館におけるビジネス支援にみることができる。県内の企業家がシャッターガードという軽量シャッター補強材の開発と事業化に成功した事例では、図書館は資料情報の提供ばかりでなく人の紹介もおこない、さらに事業展開の戦略にまでかかわっておられる。また、これまで資料提供を軸に行われてきた公共図書館と学校との連携についても、提案型の新たな協働を創出することも可能になるはずだ。たとえば、ただ教師の依頼によってテーマに沿った資料を提供するだけでなく、授業事例やレッスンプランなども収集して授業づくりの相談にも応じるなど。この点でも鳥取県立図書館の場合はすべての県立高校に司書を出向させていて、現場のニーズに即応するとともに新たなニーズをも創出しながら従来よりも踏み込んだ連携を可能にする条件がととのっているといえる。こうして地域行政への関与から地域産業の振興や市民性の育成、学校教育にいたるまで、図書館が従来よりも一歩踏み込んで深くかかわることによって、その機能はいっそう拡張、強化され、専門職の雇用促進にもつながる道筋もできるだろう。
資料・情報や場所を提供するだけでなく利用者と直接的にかかわって課題解決のパートナーとして協働する図書館員の姿は、学校図書館においてこそ、もっとも求められ、優れた実践の中にその事例を数多く見ることができる。司書教諭であれ学校司書であれ、何らかの形で学校図書館に配置される教職員がその職務を果たそうとすれば、必然的に子どもや教師との直接的な触れあいを持続させないわけにはいかないし、三者相互の関係性の中で自分自身をふくめた当事者すべての学びと成長にかかわることになる。そのことを明確に意識化している図書館担当者であれば、何よりも自らが子どもの学びを左右する情報源として信頼に足る存在であろうとするだろう。それは、レファレンスでも授業支援でも図書の整理でも、図書館業務のあらゆる局面において、その時々の子どもの学びや教師の教育活動に深くかかわって自らの専門性を活かすところからもたらされる。そこに、それぞれの局面で固定化された役割分担を超えて課題解決のために協働するノットワーキングを生む余地がある。
利用者に「資料・情報を提供する」だけでなく利用者の「課題解決に直接的にかかわる」サービスをめざす図書館員に求められるのは、図書館業務に関する知識・技能の画一的な行使ではなく、当事者間の関係から生じる多様なコンテクストに対応できる「流動的な知性」(Fluid Intelligence)であろう。その育成と行使を阻害している諸々の要因、とりわけ制度やシステム、そして慣行や自らの行動の前提となっている認識をどのように変えていくか、その具体的な方略を立てて実行していくことが、これからの図書館の課題になるのではないだろうか。










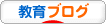

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます