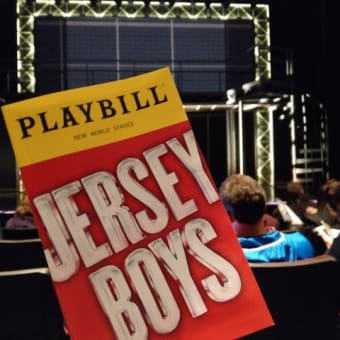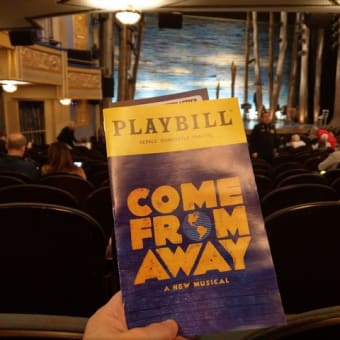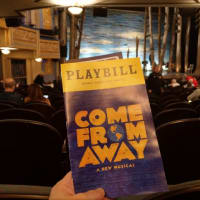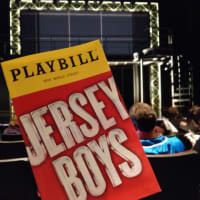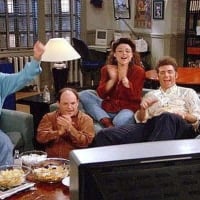NYにおける前衛芸術の殿堂といわれるBrooklyn Academy of Music, その中の一施設であるHarvey Thaetreは本部ビルに程近いところに建てられている円形劇場。(しかし、この辺りの道も分かりにくかった。建物が見えるのに、辿り着けない、という…笑)
ここで現在上演されているシェイクスピア劇MACBETHは大人気を博しており、連日チケット完売。来月にはBroadwayの劇場へと「進出」します。私の席は(前日に窓口で買った)、少し右よりではありましたが、前から6列目で、視線の先に役者の顔が来るのが何とも幸運でした!
御存知のとおり、MACBETHはシェイクスピア四大悲劇のひとつとされています。11世紀のスコットランドの武将マクベスが、魔女にそそのかされるままに、血で血を洗う抗争の果てに王位に就くが…
シェイクスピアの作品は、それ自体が史実に基づいていたり、古い伝承を材源にしているものが多く、そこにシェイクスピア独特のセンスを盛り込むことで、普遍の人間性を描くことに成功しているのですが、MACBETHの場合はちょっとユニークというか…これ、そのものが「素材」となる魅力にあふれている作品と言われます。
MACBETHは「まるでスターリン体制下のソビエト連邦だ!」と指摘する演劇関係者も以前から存在していたそうですが、今回の舞台は、まさにそういう解釈になっています。
マクベスを演じるのはピカード艦長の(?)Patrick Stewart。元は英国の名門Royal Shakespeare Companyの出身俳優でもあります。
今回は明らかに20世紀の恐怖政治下におかれた全体主義の国を舞台にしています。ただ、具体的な人名・地名はオリジナルのままですが、カーキ色の軍服、無彩色の部屋にむき出しのシンク、ステンレスの冷蔵庫、これも剥き出しの鉄骨のエレベーター…観ている者にとっては、いやでも「ある世界」のイメージが焼き付けられます。また、カーキの軍服の襟元の突出した「赤」には特別な恐怖を感じるようで…
さて、MACBETH自体は、他のシェイクスピア作品と比べても、台詞が非常に様式化されているといわれます。実際、台詞一つ一つを聞き取るのは至難の業だったし、オリジナルのとおりWhich thou dost glare with.などと言っているのか、はたまた現代英語でWhich you do glare withと言っているのか…シェイクスピアものの場合は現代劇のスタイルをとりながらオリジナルの台詞をかぶせても不自然さはないのか…などなど、私には不勉強で分からないことも少なくなかったわけですが、ただ言えるのは、台詞がclusterになって舞台を・客席を・観客の間を疾風のごとく駆抜けていくようで、…そんな感覚が実に心地よく、そして、それが視覚刺激と一緒になって、見る側の五感を瞬く間に支配してしまうような圧倒的な力を感じました。私自身も、瞬きするのも惜しい思いで舞台に見入っておりました。
最初の場面は、原作のように「荒野」ではなくて、病院。反乱軍制圧で負傷した兵士の断末魔の叫びから始まります。介抱に当たっているのが「魔女たち」。独特のマスクとメイク。やがて彼女たちに見取られて、兵士の心臓の鼓動は消えます。(このモニターはステージの背景として大きく映し出される)彼女たちは「死の番人」であることが印象付けられます。原作では、この負傷兵はあくまでも「美談の英雄」であり、マクベスから「彼に医者を呼べ」と言われて退場するのであって…だから、彼の「死」というのはイメージされていない(と思う)のですが、いきなり、彼の絶命が見せられるのは衝撃でした。
さて、魔女にそそのかされ、マクベス夫人の野望のままに、王、武将、政敵の家族を次々とその手にかけるマクベスですが、Patrick氏の醸し出すどこか飄々とした空気は、観ていると、普通に人間の中にある悪魔性というよりは、彼という人間の実体のなさの表れだと解釈した方がいいのではないかと思えてきました。彼は常に眠りと覚醒の境界がはっきりしないところで生きていたのだという~
(実際、インターミッションのとき、私の後ろの座席の人たちの間では「優しすぎるマクベスだね」なんて感想が話されておりました)
舞台中央に、二つの蛇口のついた「不気味な」白色のシンク。マクベスは殺戮を繰り返し、血にまみれた手は海で洗っても落ちない、海自体が赤く染まるに違いない!と混乱するのですが、夫人の方は「そんなものは洗面器で荒い落とせる」と言い放つのです。
灰色の床の上にある、不気味に光る白磁のシンク、そして二本の蛇口と、血に染まった人間の罪を冷ややかに見据えているようで怖い。マクベス夫人の残虐性を表す台詞「私は授乳しながら、赤子の頭を捻りつぶすことだって出来るのだ」には観客から笑いが起きたのにはちょっとびっくりしましたが…
また、マクベスの仲間の武将である清廉の士バンクォーは原作のイメージにぴったりの役者が演じていました。心に邪なものがある者にとっては、バンクォーの澄んだ瞳を直視できるわけがない…マクベスが彼の存在を受け入れられなくなっていくところは非常に説得力がありました。
あとは、ダンカン王殺害が発覚する前の場面、門番がおどけるコミック・リリーフの場面ですが、この門番役の役者さん…クレジットに載ってないような気がするのですが(?)とにかく、究極のキャラクター役者というか、ほんの数分で場の空気を100パーセント支配してしまったというか、生で○×するシーンは初めて見せていただいたというか(観た人はワカル…笑)まさに、「どれだけ人材がいるんだ」って感じですね。
さて、ところが二幕になるとですね…マルコム王子とマクダフが完全にマクベス夫妻を食ってしまいましたね。
マクベスが敷く恐怖政治下で衰退するスコットランドを何とかしようと、家族を残して国を出た貴族のマクダフが、亡命中のマルコム王子と訪ねる長いシーンがあります。
また、「恐怖政治下のスコットランド」を象徴する「映像」として、舞台背景には、あきらかに「スターリン体制下」のソビエトの映像が映し出されます。
マルコムは、最初はマクダフを信用していないのですが、話の途中に、マクダフの妻子が粛清されたという一報が入ります。悲しみにくれるマクダフを慰めながら、やがては、マクベス征圧への思いはマルコム王子の方が積極的になり、逆にマクダフを説き伏せていくようになっていくのです。
とのかく、このあたりの凄さは「ストレートプレイの醍醐味」と言う他はない…
原作では、マルコム王子の本心というのが今ひとつよく分からなかった…
「私は根っからの淫※乱なのです。それと比べると、マクベスの悪事などどれほどのものだというのか」などとマクダフの申し出を断るのですが、その後は「私は女性をまだ知らない」と告白するのです。このあたりは、私には理解不能だった部分でありまして(…)、
しかし、このマルコム王子を演じたScott Handy(MATCH POINTなどにも端役で出ていたんですね)一つの類型を的確に演じていた気がしました。非常に直向で潔癖、男性的な魅力はむしろ乏しい印象、そして内なるコンプレクスと常に隣り合わせにいる…という。(結局、やはり自分はヴァージンであるというのが本当ではないかと解釈したのですが)
とにかく、このシーンからは、このScott Handyに持っていかれてしまったような印象のまま、一気にクライマックスへと駆抜けました。
「魔女」というのは「荒野」にいるのではなくて、人の死を間近に感じられるところ、または、寝る・食す…という人間の営みのすぐ傍にいる。
Fair is foul, and foul is fair.
しかし、劇場を出て時間がたつにつれて…このMACBETHが20世紀のある時代のある体制を取っていた国のイメージに余りに強く結び付けられていたことを(そう、「余りに強く!」)振り払ってしまいたくて仕方がない気持ちに襲われてしまいました。
あれはあくまでも「ひとつの解釈」
だけど
あれは「ひとつの解釈」 あれは「ひとつの解釈」
あれは「ひとつの解釈」 あれは「ひとつの解釈」
あれは「ひとつの解釈」 あれは「ひとつの解釈」
常に自分に言い聞かせていないと「あの解釈に支配されてしまいそう」で…
近くには、アフリカ系アメリカ人のファッションやオピニオンの発信地としても知られるFulton Mall