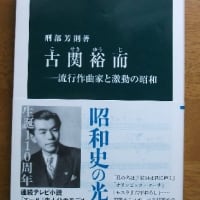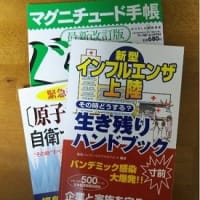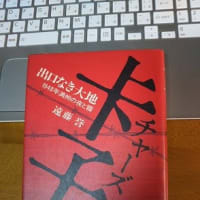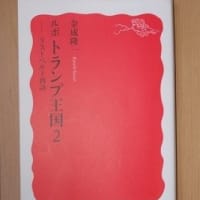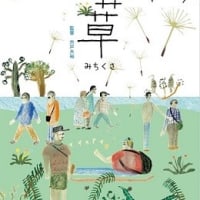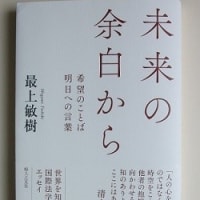下巻の前半は、大学管理者側の立場に立たされた中で、関わった東大紛争を、医学部処分問題から、安田講堂の終焉、不法占拠をした学生の裁判に証人として立たされたつらさ、そうした紛争の傷跡を、時を追って、述べられている。学生側のリーダー山本、今井両氏のその後の生き方を評価され、定年時、私大から研究者を招聘されたが、大学紛争で端緒となった大学改革への一つの答えをなされている。
下巻の後半は、著者が働かれた国際的な共同研究、平和研究の推進、東西冷戦と終結後の国際政治と平和に関わる会議、民際外交※としての国際会議、中国と隣国南北朝鮮と日本にある人権問題。そこにて訪ねたその国、土地、アメリカ全土、東西ヨーロッパ、中東、インド、南北朝鮮、そこで出会いのあった人、アリ・マズルイ(ケニア)、シャムヤリーラ(ジンバブエ)、コンスタンチン・ゲーベルト(ポーランド) ヴァイツゼッカー(ドイツ)、金大中(韓国)…についてのエピソードが述べられている。誰とどのように関わり、提言されてきたか。巻末に、著者略年譜と主要人名索引が用意されているが、その働きの広さと多方面にわたり出会われた方々の記述に圧巻される。最後の2章は「日本社会への訴え」と「冷戦終焉と21世紀」で締めくくられる。
15章日本社会への訴え
「理想主義」は非現実的な夢であり、「現実主義」とは「リアリズム」であると言われるがそうではない。理想を目指し、現実を少しでも変えて生きていくのが、人間の現実。
人間の目的・価値志向の主体的行動によって動かされているのが「リアリズム」。
国際政治での「現実主義」と言えば、無政府状況の中で、実力・暴力行使がされる最悪事態を、国家という抽象的な実体を視点に想定するのが「リアリズム」。一方、「理想主義」では、身体を持った市民の視線で最悪事態を捉える。 自分が焼き殺される立場で見て抗議の声を上げる。それゆえ「ヒロシマリアリズム」「 ナガサキリアリズム」という言い方をしてきた。そうした立場から、沖縄の非軍事化の声明の草稿作業、 軍事大国化に抗して(GNP1%枠を守る)、非核五原則の提言、国際貢献、戦争責任を問いなおしてこられた。ここでは、
大江健三郎、安江良介、金子勝、高橋哲哉、小森陽一…など多数の方々と行動を共にされている。
第16章 冷戦終焉と21世紀
冷戦終了後、振興大国の権力拡大と、核の拡散、文明・文化や価値観に関わるアイデンティティの多元化、戦争地域と平和地域の分離と局地化、いわゆる「相対化の時代」が、「資本と市場」を力として進んだ。この「資本と市場」における競争のグローバル化は、不公正な政治的、経済的社会的格差を生み出し市民の人間性喪失と地球の荒廃を生んでいる。だが、こうした状況に抗して人間らしく生きるために闘っている人々がいることをグローバルなコミュニケーションの発達により知ることが出来るようにもなった。この闘いに、市民社会が連帯出来るのか。そこには、次の観点が必要。
「人権の普遍化」、「他者の人権の承認」の基礎に、さらに、他者の尊厳、他者のいのちへの感性、他者の命にたいする尊厳を据えねばならない。
また、人間の同士の共生から自然との共生、エコロジーも重要。地球の限られた資源を格差なく公正に分配することが、人間を「自由」にする。この、近代の「自由」の再定義が必要。連帯の最高の共同体は主権国家ではなく、地球的、広域的、市民的共同体であり、その連帯は、閉鎖・排除ではなく開かれた連帯。また、他者への無関心を克服する連帯でなければならない。
地球規模の環境破壊、3.11後、新たに脅威となった核の問題。この1年を見る限りでも、数々あるが、そうした平和、核、環境も問題において、著者が、追求されてきた、国家がなしえず、人類としての人間、その人間が創る市民社会がなしえるもの。この本を通じて受け止めた。
下巻の後半は、著者が働かれた国際的な共同研究、平和研究の推進、東西冷戦と終結後の国際政治と平和に関わる会議、民際外交※としての国際会議、中国と隣国南北朝鮮と日本にある人権問題。そこにて訪ねたその国、土地、アメリカ全土、東西ヨーロッパ、中東、インド、南北朝鮮、そこで出会いのあった人、アリ・マズルイ(ケニア)、シャムヤリーラ(ジンバブエ)、コンスタンチン・ゲーベルト(ポーランド) ヴァイツゼッカー(ドイツ)、金大中(韓国)…についてのエピソードが述べられている。誰とどのように関わり、提言されてきたか。巻末に、著者略年譜と主要人名索引が用意されているが、その働きの広さと多方面にわたり出会われた方々の記述に圧巻される。最後の2章は「日本社会への訴え」と「冷戦終焉と21世紀」で締めくくられる。
15章日本社会への訴え
「理想主義」は非現実的な夢であり、「現実主義」とは「リアリズム」であると言われるがそうではない。理想を目指し、現実を少しでも変えて生きていくのが、人間の現実。
人間の目的・価値志向の主体的行動によって動かされているのが「リアリズム」。
国際政治での「現実主義」と言えば、無政府状況の中で、実力・暴力行使がされる最悪事態を、国家という抽象的な実体を視点に想定するのが「リアリズム」。一方、「理想主義」では、身体を持った市民の視線で最悪事態を捉える。 自分が焼き殺される立場で見て抗議の声を上げる。それゆえ「ヒロシマリアリズム」「 ナガサキリアリズム」という言い方をしてきた。そうした立場から、沖縄の非軍事化の声明の草稿作業、 軍事大国化に抗して(GNP1%枠を守る)、非核五原則の提言、国際貢献、戦争責任を問いなおしてこられた。ここでは、
大江健三郎、安江良介、金子勝、高橋哲哉、小森陽一…など多数の方々と行動を共にされている。
第16章 冷戦終焉と21世紀
冷戦終了後、振興大国の権力拡大と、核の拡散、文明・文化や価値観に関わるアイデンティティの多元化、戦争地域と平和地域の分離と局地化、いわゆる「相対化の時代」が、「資本と市場」を力として進んだ。この「資本と市場」における競争のグローバル化は、不公正な政治的、経済的社会的格差を生み出し市民の人間性喪失と地球の荒廃を生んでいる。だが、こうした状況に抗して人間らしく生きるために闘っている人々がいることをグローバルなコミュニケーションの発達により知ることが出来るようにもなった。この闘いに、市民社会が連帯出来るのか。そこには、次の観点が必要。
「人権の普遍化」、「他者の人権の承認」の基礎に、さらに、他者の尊厳、他者のいのちへの感性、他者の命にたいする尊厳を据えねばならない。
また、人間の同士の共生から自然との共生、エコロジーも重要。地球の限られた資源を格差なく公正に分配することが、人間を「自由」にする。この、近代の「自由」の再定義が必要。連帯の最高の共同体は主権国家ではなく、地球的、広域的、市民的共同体であり、その連帯は、閉鎖・排除ではなく開かれた連帯。また、他者への無関心を克服する連帯でなければならない。
地球規模の環境破壊、3.11後、新たに脅威となった核の問題。この1年を見る限りでも、数々あるが、そうした平和、核、環境も問題において、著者が、追求されてきた、国家がなしえず、人類としての人間、その人間が創る市民社会がなしえるもの。この本を通じて受け止めた。