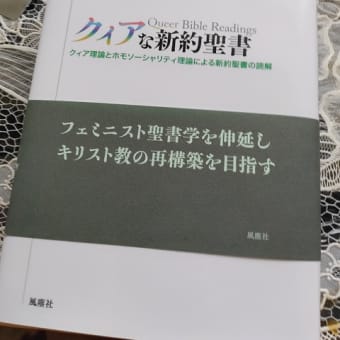なんかやる気がなくて、ぼんやりした日々を過ごしていた。
たまたま付けていたJ-comで黒澤明『生きる』を放送していたので、なんとなく視聴。多分随分昔に視た事はあったように思うのだが、志村喬の名演は印象に残った。
「生きる」という事が、癌で「死ぬ」を意識する事で浮上する、そんな仕掛けで問うてくる面があったと思う。つまり「生」の対立項として「死」、そういう構図である。哲学的には「生」の対立項として「死」が位置付けられるかいなかは議論の余地があるが、我々一般の人々の理解としては、訴えてくるものがあるのだろう。もちろん僕にだって、感じる事はあった。
僕たちは、「死」を見据える事ができない。というより怖い。おそらく、志村喬演じる主人公も同様である。そこで「死」を見据える事ができないので、やりなれない遊興に身を任せる。というのは、実はゴマカシなのである。「死」は末期癌にならずとも、平等に人間に分配されている。ただ忘却して生きる。
なぜゴマカスか。それはそれまで築いてきた生活の全てが崩れてしまうからだ。それが怖いという事だ。キルケゴールは、死をしっかり見据える事、その恐ろしさに正面から対峙する事、そのようにするしか、そのような状況から脱却する事はできないと喝破する。
それが「生きる」という事があらわになる事である。志村喬演じる主人公は、癌であることを知り、最初はゴマカシに身を任せる。キルケゴールが言うように、最大の精神的悲惨のうちに自ら入るしかない。主人公は、内に入っていく。それがこれまでハンコを押すだけの仕事を脱却する「生きる」事に向かわせる。
人間は「死」に対しては、都合のいい薬はない。当たり前だが、対処療法的な薬は副作用がある。この場合、副作用は「生きる」の真の意味(こういう言い方にしておく)からの遠ざけである。いい加減な薬など使用しなくても、人間には自己治癒能力がある。
「生」に関しても同様である。その意味に気づくか気づかないか、そして行動に向かうか否かである。治る見込みがないとしながらも、その根源的事実を引き受けるか否か、そこに人間の意味が立ち上がる。主人公は引き受けたかのように見える。
そして、僕が考えたのはこの生と死の根源的事実に対する人間のありようを表現しているという点だけではなく(これも根源であるから重要である事は強調しなければならない)、1952年の作品だというのに、なんら現代も変わらない日本人の在り方であった。
(続く)