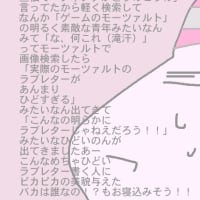ちなみに三話の人たちは小学五、六年くらいです。ビジュアル初めて出したときに、彼らは高校生くらいだと思ってたよ!と言われたので一応かいておきます。
うーん、相馬の台詞なんかちょっと子供が小難しい本読んでかぶれてるみたいな感じ丸出しだと思ってたのですけども。
三話の霞は二話の霞と姉妹です。多分この姉妹はどっちもショートカットですね。
で、三話まで地味につながってるのに四話は孤独な荒川君と。
まあそんなかんじで。
草下美苗は異物だ。少なくとも、クラスの皆はそう思っているに違いない。
どこかおびえた様な表情、どこを見ているか解らない瞳。そして手首にはいつもリストバンドをつけている。その下には、きっと無数の傷があるんだろうと噂す る物も、多数。更に中途半端に整った顔の所為で、女子にはものすごく評判がわるい。
俺から見れば…まあ、ギリギリ可愛い顔だと思うけど。
そんな彼女と席替えで隣の席になった。
草下は早速教科書を忘れていたのだが、なかなかそれを言いださず、結局教師二見つかって俺が見せてやる事になったのだが、なかなか彼女はそれを見ない。ち らちらっと横目で見るだけ。授業自体まともに受けているのかどうかも怪しい。せっかく見せてやってるのに、なんなんだ、その反応。いらつく。
授業が終わってから、「ありがとうね…矢吹君」といつもの小さな声で言われたが、それだって本気かどうか疑わしかった。
「なあ、矢吹。お前さ、草下のリスバンの下見る気ねえ?」
「ないよ。」
「仲良くなったら、見せてくれるかもよ?」
「見せないだろ、普通。」
相馬という男子が声をかけてきたので、邪険に追い払う。何で隣の席になったくらいでそこまで関わらなきゃ行けないんだ。めんどくさい。
と思っていたのだが。
帰りがけ、校門前で草下を発見してしまった。外は涙雨。当然のように傘を持っていない彼女は行き場の無いウサギの様な顔をして、玄関前でたたずんでいた。
俺は傘を持っている。軽く嘆息して、俺は彼女に声をかけた。
「草下。この雨、止みそうにないぞ。」
「…」
「まあほんとはいれたくないんだけど、途中までなら送って行ってやる。」
「いれたくないんなら、いれなければいいじゃない。私だって入りたくないし」
ふい、と草下は横を向いた。
「もう少し待ってみる」
「無理だよ。天気予報見てなかったか?今日はずっと雨だって行ってたぞ」
「…そうなの?」
「風邪ひかれちゃ、寝覚め悪いしな。ほら、入れ」
「………そういう優しさが、私一番嫌い」
「好かれても困るよ。ぐだぐだ言うなら、ほんとに濡れて帰れよなてめえ」
見た目は大人しいくせに、何だこの意地のはり用は。なんだか余計イライラする。
「………でも、ほんとに迷惑じゃないんだったら」
「うん?」
「優しさに甘えても良い。」
なんだ、結局甘えてくるのかよ。仕方ない奴だな。だから嫌われるんだぞ。
「ああ、でも次はないから、今度から天気予報はちゃんとみろよな」
「うん、そうする。…ありがと、矢吹君」
「お前、家はどっちだ?」
聞くと、そんなに遠くない、と呟くように草下は言った。
「5分くらい」
「ふうん、学校から近いなんていいじゃねえか」
「よくない。この学校、不良多いからうちの近くよくたまり場になってるもの」
「…それ、大丈夫なのか?」
「恐いけど、我慢しなくちゃしょうがない。生きて行くのとおんなじ」
何か全然別の次元の話だと思うが…まあ、草下次元ではそうなのかもな、と思い、適当にうなずいた。
「そっか…ま、絡まれないように気をつけろ?ただでさえ、お前クラスの連中にも評判悪いんだぜ」
「私は、私が嫌いな物からも好かれたくないよ」
それは、強がりだろうか。横顔がふと涙目に見えた。雨の所為かもしれない。
「………お前、見た目と違ってだいぶ性格きついな。おい、もうちょっとこっちよれよ、肩が濡れてる」
「あ、うん…ごめん、今の…」
「解った解った、聞かなかった事にするから。でもそんな態度、ほめられたもんじゃねーぞ?」
「………」
草下は何やら黙り込んで、考えている。
なんか、めんどくさいコメント聞いちまったなあ。ただでさえ席となりになっちまって、休み時間にこいつに絡んでる女子とかって見るかもしれないとか思うだ けでもかなりいやなのに。
「早くキラーワーズが全部、終わらせてくれればいいのに」
「なんだ、そのキラーワーズって」
聞いたけど、草下は答えなかった。
「なあ、キラーワーズって何だ?」
翌日、例の相馬ならしってるだろうと思い、声をかけてみる。
「へ、お前しらないの?都市伝説だよ。あのな、言霊使いの一種かなんかでさ、呪いの言葉を吐いただけで聞いた奴を殺しちゃうって奴」
「え…?」
それが、一体何を終わらせると言うんだろう、まさか、草下の奴…クラスの皆、死んじまえば良いって思ってるのか?いや、なんでもそこまではいかないだろ う。
「で、何でそのキラーワーズをしってる訳、お前」
「いやあのな…草下が、キラーワーズが全部終わらせてくれればいいのに、って言ってたんだ、昨日」
「………草下が?やっぱ、死にたがってんのかな。ああ、顔は好みなのにもったいない」
「だったら、お前が助けてやれよ」
「やだよ、俺が好みなの顔だけだよ」
なんて奴だ。と、考えてるのが顔に出てたらしい。
「そんな顔すんなよ。だいたいな、俺もお前もそこまで他人に関心無いはずだろ?だからこうやって話ができるんじゃねえか」
「………」
と、そこに噂の草下が登校してきた。
「………おはよ」
「おはよう、矢吹君、相馬君。結局、風邪引かないですんだみたい」
まるで他人事のように、草下は言った。俺もおざなりな笑みを返す。
「それはよかったな。」
「矢吹君のおかげ」
「え、な、何お前らそんな仲だったん?」
「昨日傘にいれてやっただけだよ。帰りがけで途方にくれてたからな、こいつ」
「相合い傘!やるじゃん」
げ。相馬が騒ぐので、みんな気づいてしまった。草下の方を見ると、顔を真っ赤にしてうつむき、唇をかみしめている。や、やめろよなその反応。余計皆にいぶ かしまれるじゃん。
「あのな、お前ら。草下は傘持ってなかったから、仕方なく…」
「へえ、ずいぶんお優しいんのねー。矢吹君私たちだったらいれてくれないのにね」
霞と言う女子がサディズムたっぷりの笑みを浮かべてそんな台詞を吐いた。こいつ、草下を一番苛めてる奴だ。俺も一番嫌いな奴だが。なんたって、教師にはこ びてるもん。
「それとも何?女の子だったらどんなにかわいくない子でも入れてあげる訳?そういう男が一番駄目なのよ」
「お前にとやかく言われたくねえよ。…お前の場合は性格でアウトだな。」
「な、なによ…!私のどこが悪いって言う訳」
「そうして何もかもにいちゃもんつけるわりには自分がちょっとでも言われると傷ついたそぶり見せるとこ。お前に比べれば可愛げない草下でもずいぶん可愛く 見えるよ」
女子どもが「えー」と次々にブーイングの言葉を述べる。ああ、もう知ったもんか。だいたい俺女子ども好きじゃないし、この機会にきっぱり決別したれ。
「まあとにかく、他の女をあしざまに言う女は好きじゃない。ま、そんなわけでオッケー?」
「どこがオッケーなのよ…!これから校舎を一人で歩くときは注意しなさい!」
「悪人な台詞どうも。でも俺も空手やってるからな。手加減できんかもしれん」
草下の事はともかく、霞をこうして黙らせた事で俺はずいぶんと高揚していた。ありがとう、草下。こいつに面と向かって文句を言える機会を与えてくれて、と 言っても良いくらいの気分だ。草下に向かって微笑むと、草下はやっぱり目をぱちぱちさせて、しかしやっぱり下を向いてしまった。
しかし。
その次の日、やっぱり机の中が荒らされてたり。ノートに落書きされてたり。何かまあ色々してた。うん、まあ、勉強熱心でない俺にとってはどうでもいいこと だが。しかし、まあ朗報もある。例の霞を嫌ってる男子も多いから男子にはむしろ尊敬のまなざしを送られることも多くなった。草下も結構嫌われつつ人気があ るからねちねちっとした一言を言われる事も多くなったが。空手やってなけりゃ、喧嘩沙汰とかもあったかもしれん。まあ、そんな訳で俺の生活は一変して(微 妙にいやな方向に)華やいでしまった。
まあ、俺なんかとくっついてる容疑をかけられてしまった所為で、草下はいつもぎくしゃくしていたが。俺は三日後くらいに、ようやく謝る事を思いついたの で、移動教室の合間に声をかけた。声をかけると草下はおびえる小動物のような目を向けてきたが、まずは頭をさげる。
「ごめんな、こんなことになって。」
「…ううん、私が不注意だった。傘、持ってきてればよかったね」
「そんなこというなよ。俺、霞に文句言えてすごい気持ちよかったんだぜ。まあ、…くっついてると思われるのは、お前も不満だろうけどさ…」
「………矢吹君もいやでしょ?」
「いや…こないだも言ったけど、霞や他の女に比べればお前は可愛いさ」
「………!」
「あ、悪い。比較対象が悪かったな。…うん、ごめん」
「………そんなこと、ないよ」
草下は少したよりなげに微笑み、ありがとう優しいんだね、と言った。ん?今の、どの辺がどう礼を言うところで、どの辺が優しいんだ?
「そんなことより、お前大丈夫か、いじめられてない?」
「…ちょっと、みんな言う事はきつくなってきたけど、我慢できないほどじゃない」
「そっか…ごめんな。」
俺は心の底から反省した。俺は霞に文句が言えて嬉しかったが、それで草下はますます冷遇されているのだ。
「それより、矢吹君の方が…」
「俺?俺は男子の人気者だよ。霞嫌ってる奴多いしな」
草下は目を丸くした。
「そなの?」
「うんまあ、霞あの性格だから、嫌いじゃない奴のが少ないだろ」
「…まあ、それはそうだけど…」
「そういうお前こそ、優しいな。こんなことになったら普通俺なんて嫌いって言うとこじゃん」
「………だって、傘に入れてくれたじゃない」
「お前そういう優しさが一番嫌いだっていってたじゃないか」
俺の顔はさも意外そうにうつっただろう。
「結果として、風邪引かないですんだもの」
なんだ、いつも空想を見てる様な顔をして、以外と現実主義派なんだな。
「じゃ、皆の前で喧嘩でもしてみるか?だったらあっさり誤解を解けそうなもんだっけどな」
「………理由も無いのに喧嘩なんて出来ないよ」
「ふりだけでいいんだよ。俺が一方的に怒るから」
「………ふりだけでもそれはいや。矢吹君は誤解されてるの、いやなの?」
ううん、どうなんだろうな。
「草下は?」
「私は…矢吹君のこと、嫌いじゃないから別に良い。どうせまた皆他に興味見つけたらすぐそっちにいくだろうし」
言うだけ言うと、草下は例の赤い顔をして教室の中にすべりこんだ。いっけね、つい話し込んでしまったけど、次音楽の時間じゃん。音楽の先公、恐いんだよ な。
移動教室の合間や、休み時間にちょくちょく草下と話をしてると、以外と草下は話が通じるんだと言う事が解った。意外と、聡い視点をしている。本の解釈で も、男の俺でも解らない様な男性心理を汲み取ってる様な一言も言ったりして、俺を何度も驚かされた。
女と話してて、いやな気分を感じる事はあっても驚かされるなんて、始めてだった。あの時、雨が降っていて本当に良かった。しかし、そうなると気になるのが 例のリストバンドだ。キラーワーズに終わらせてもらう、と言う一言も気になる。
放課後、何となく居残ってたら、草下も残っていたので、…俺に何か用事でもあるのかと思ってたら、何も言わないので、俺から話をきりだした。
「なあ、草下、お前、そのリスバン…」
声に出して聞こうとすると、もはやすでに草下は瞳に怒りの色をにじませていた。
「やっぱり、矢吹君も…」
「え、おいおい、何も下を見ようなんていってないぞ」
「………それだけで、近づいてきたんじゃないの!?」
「い、いや、そんなことは…」
「やっぱり、皆私に死ねって思ってるのね。言われなくても、キラーワーズに終わらせてもらうわよ!」
草下はいきなり、階段の方に向かって駆け出した。
「おい待てよ草下!ちくしょう、なんで足早いんだ…いらん技能だぞ、それ!」
と、ふと俺は気がついた。草下の駆け出した先に、黒衣の女がいる。
誰だ…?
その女が、草下にむかって何か呟き―――。そして、草下の体がぐらりと揺らいだ。
「草下!?おい、お前誰だよ草下に何した!」
「彼女の望むままに。」
青みがかった黒い瞳が、しっかりと俺をみすえる。それはそれだけで呪われてしまいそうなほど、冥く、底の無い色をたたえていた。
「まさか…殺したの、か?」
さあ、と笑いながら。女はどこかに立ち消えてしまった。幽霊か、そのたぐいか…。俺はさっぱり訳が分からなくて、しばらく立ち尽くした。
「草下、おい、草下…」
草下はぐったりしたまま、動かない。だらりと弛緩した腕。言葉を紡がない唇、開かない瞳。さすがに心臓に手をあてるまではいかないが、もしかしたら本当に 死んでいるのかもしれない。
「しっかりしろよ、お前、こんなんじゃ…!こんなんじゃ、人生なんだったんだよ!おい、草下!」
しばらく、草下の名前を呼び続けたが返事がない。おい、やめてくれよ。俺の前で、死なないでくれ。しかも、俺の所為じゃないか。…ほんと、やめてくれよ、 こんな冗談…!
「そ、そうだ、脈…!」
脈をとれば、生きているかどうか、解る。
左手のリストバンドをはがそうかはがすまいか、しばし迷ったが、ここは非常時だ。仕方ない、と、その時。その腕を華奢な手がやめた。
「…やめて。矢吹君」
「く、くさか…!生きてたのか、なら、いいんだ。悪かったよ、お前がそんなに傷つくなんて思っても見なかった。ほんとはリスバンなんか最初からどうでもよ かったんだ…あの日は、ほんとに偶然で」
「ううん、いいの…見せてあげる。ほんとは傷なんて無いから」
草下はゆっくりと起き上がり、言う通りにリストバンドを外した。言う通り、傷なんて無かった。
「なんだ…ファッションだったのかよ。驚かせやがって」
「ううん、違うの。ほんとは、自殺未遂してるんだって皆に思わせたかった。恥ずかしい話だけど、そうだったら皆反省するかもと思った。でも、結果は皆余計 リストバンドの中身を期待するだけ。私が傷つく事を期待するだけ。だから、矢吹君も実はそうなんじゃないかと思ってしまって、勝手に傷ついたの」
「………」
「私に傘をさしかけてくれたあの日も、リスバンの話相馬君としてたでしょ、だから、ずっと心の底で疑ってた。ごめんね…」
「いいんだよ、生きてて。」
俺は草下の前髪をくしゃっとなでた。
「お前確かにかわいげ無いけど、するどいし話してて楽しい。誰に嫌われてても俺は好きだよ、お前の事」
「………!」
「あ、ま、まだ恋愛じゃねえぞ!恋愛じゃねえけどな…うん、好きだ。」
草下はかああっと顔を赤くして、俺の方を見た。う、や、やめてくれよその潤んだ瞳…それ、殺人的なんだから。
「だから、生きててくれ。」
「………うん。」
結局キラーワーズとはなんだったのか、あの女は何ものだったのか、草下がどうやってあの女を呼んだのか、くわしい事は何一つ解っていない。
しかし、俺と草下は、生きている。
たわいもない話をかわし、時々照れ合いながらも。
お互いに歩み寄りを交わしている―――。生きている喜びを、噛み締めながら。
四話壊してやる。
俺はあいつを傷つけた。人通りの多い駅前で、あいつなんていってもどこの誰だか解らないやつだった。ただの衝動。誰でも良かった。血を流す生き物ならばな んでも。でも何故か、注目される場所で犯行におよんだのは、ただの俺の愚かさだ。その場にいた女が叫んで、すぐに刑事に取り囲まれた。
「お前―――こっちに来い。」
地下鉄の改札をくぐり、こちらを何事かと言う目で見て近づいてきた黒衣の女。その華奢な腕をつかんで、胸元に引き寄せる。
「刑事ども!俺に近づいたら、こいつを殺す―――」
青みがかった瞳でこちらを見つめてきた瞳は、どこかでみたことのある光をやどしていた。女は小さく呟く。
「まあ、それは私の専売特許よ―――あなたも知ってるでしょう、荒川忠志さん」
―――誰、だ?
高校を卒業後、俺はあちこちバイトを転々としていた。長続きしないのだ。特にこれと言って鍛えてもなかった体は短時間で稼げる様な重労働には向いていな かった。金がどうしてもいるというわけではない。けれど、どこに向かっているかも解らない地道な道を歩んでいるよりは、きついバイトでも金が入るという実 感を得られる方が良かった。働くのは、嫌いじゃない。実感がある。でも俺は人付き合いと言う物がからきし駄目なのか、どこにいてもすぐに絡まれた。
そして言われたことに我慢できずに喧嘩―――いつも、俺の方が負け。でバイトをやめるということを繰り返していた。アホでバカで愚かだった。そんな男だっ た。俺は。その時は、ちょうどいくつめかのバイトが喧嘩でぶちこわれた日だった。あちこちぶらぶらほっつき歩いてから、家に帰った。まだ午後三時だったの に、親父は家にいた。いつものことだった。親父はほとんどはたらかない。母さんにまかせっきりだ。だから俺はいつも家には帰りたくなかった。
それなのに。
親父はそんな事も知らず、俺に話しかけてきた。くだらない、ご近所の話を延々と。俺に関係もない様なことばかり。耳が、腐る。
だからか―――俺は気がつけば親父を殴っていた。
親父はへらへらと笑っていた。
「強くなったな―――忠志ぃ―――」
あの日を境に、俺は完全にぶち切れた。
暴力的な衝動が抑えきれなくなったのだ。人を傷つける事は罪だ。殺す事、奪うことはやめましょう。だから?
傷つけられた顔を見せろ。オブラートに隠すな。痛みを現せ。誰も彼もが感情を吹き出してめちゃくちゃになればいい。どうせ、帰る場所なんて無い。居場所な んてなくていい。壊れてしまえ。
家にも帰らず、そこらの親父をなぐりつけ、金を奪って過ごした。
快適だった。
あの親父の顔を見ないですむのは。
ああ、でも。
人間って壊れればどうなるのかな。俺は衝動にまかせてナイフを買った。
そして―――。
今に至る。
「それで、私をどうするの?」
「暴れなきゃ、なにもしねえよ―――ただ、俺が人を殺すのを黙ってみてな。」
長い黒髪の女はおびえたそぶりを見せない。ただの強がりでもないらしい。顔の通り、感情欠落女なのかもしれない。引きずればついてくるので、俺たちは物陰 へと身を潜めていた。
「殺すのに、観客がいるの?変な話ね」
血ぬれのナイフを突き立てられているのに、余裕ぶった顔をやめない。
いらつくよりも、逆に。
こういう女にこそ、恐怖の色を浮かべさせたいと。
「ヒーローには観客がつきものだろ」
「その言葉、借り物みたい。まあ、いいわ。あなたがそうして人を殺してまで得たい物があるなら、見届けてあげる。興味があるから。」
図星だった。青少年犯罪のニュースを見るたびに流れていた言葉、ヒーローになりたかった。俺の言葉はそれのぱくりだった。ヒーロー?違うだろ。俺はただの 獣だ。得たいものなんて―――ない。
「ねえよ、そんなもの。ただ、傷つけたいから傷つけるだけ、ただの興味本位だ」
私はそんなあなたに興味があるわ。ただの興味本位で人生を棒に振る覚悟があって?面白いじゃない。
そんな風に囁いた声は透明で表情が見えなかった。
「刑事さん達、あっちにいったみたいよ。逃げるなら、今だと思う」
「指図すんじゃねえよ―――お前、名前は」
「ただの観客なら、名前なんていらないわ」
「呼ばなきゃ解らねえだろ」
女はしばし考え、そうね―――と呟いた。
「知ってるはずだけど。文月小夜香。キラーワーズよ」
ひょうひょうと名乗る姿に、一瞬目が丸くなる。
「って…キラーワーズって都市伝説の?嘘じゃん」
だから言いたくなかったのに、という表情を女はした。初めて見た人間らしい表情だと思うと、なんだか自分が間抜けに思えてきた。
「観客に名前はいらないっていったでしょう。捕まりたいの?」
「ふん?なら、お前を殺してみるのも面白いかもなって言ったら?言っただろ、誰でも良かったって」
じろり、と俺はあらためて文月小夜香を見直した。多少人形的すぎるところはあるが、まあまあ良い女だ。死神めいた黒装束も、かえって艶っぽくて良いかもし れない。
「文月のキラーワーズを殺したら、ほんとにヒーローだ」
「………ただ、動物的に人を殺したいの?」
「お前がもしほんもののキラーワーズなら、どうだ?」
「そうね。殺す事に意味なんて無いわ。哀しみも痛みも結局朽ちて行くだけだもの。殺された方も、どんな崇高な理由であれ殺されれば同じだものね。生まれて きた事を悔やんで死んだとしても、心から喜んで死んでも結局変わらない。」
「面白いじゃん、続けろよ」
「殺すのは結局誰かが望んでいるからよ、死を。」
「ふーん…」
「あなたは、逃げて生き延びたいのかと思ってたら違うの?死にたい?」
「さあ。結局、どうでもいいのかもな。どうせ死んでないだろ、最初にさした奴。だったら俺は死ぬ事なんて無いだろ」
「殺したいんじゃなかったの?」
「ああ、殺したいよ。なあ、お前自身は望んでねえの?」
「何を?」
この黒い女の言う事はどこまで本当なのか解らない。本当は肉も血もちゃんとある人間かもしれないし、無表情を装っているだけなのかもしれない。
「死を」
文月は意表をつかれた瞳でこちらを見返してきた。
「誰の?」
「誰でも良いよ、俺とかさ、死んでしまえとか思わないの?」
くす、と文月は笑う。それはあざ笑うような笑顔ではなく、むしろ―――。
「…そうね、意味など無くても感情はあるものね。すべてを否定する事にこそ、むしろ意味はないわ―――」
「どういう意味だよ?」
「殺して何かが変わると思うんなら、やめておいた方が良いわ。きっとあなたは何も変わらない。興味本位でも、あなた以外のすべてが変わる。あなたの望み通 りにあなたは追われてしまう、社会から」
「…もうドロップアウトしてるも当然だけどな」
俺は苦笑した。
「他人を傷つけたいって言うのは一種の依存よ。本当に誰にも興味がなかったら何も見ないし何も傷つけない。空気を吸って吐くだけだわ。」
「…俺が、何に依存してるって言うんだよ…!親父にか、お袋にか、それとも―――」
いたぞ、こっちだ!
そんな声が、俺たち二人を遮った。俺たちを包む青い服の群れ。
文月は小さくため息をついた。
「おまわりさん。―――最初にナイフを突き立てられたと言った男はほんとに怪我をしていましたか?私は人質でもなんでもありません。これはお遊戯です わ。」
「君…何をいって…」
「演劇の練習です。彼は対人恐怖症なので克服するために人前でしただけです―――」
「違う!お前、何言ってんだよ…!俺は…」
文月は横目で俺を見た。いいから任せなさい。そういってるように思えた。何を考えてるんだ、この女?まさか、本当にここはごまかして、本当に人を殺せと?
そういって―――いるんだろう、か。
「みてください。こんなちゃちなナイフで人が殺せる訳、ないでしょう?」
「しかし、君―――」
警官達は暗示にかけられたように、うつろな顔つきになっている。いや、実際かけたのだろう。いつの間にか俺は悟っていた―――。こいつは本物だ。警官達が 訳の分からないと言った顔でこの場をさっていくと。
「この場ではあなたは人を殺さなかった」
呟くように、歌うように文月小夜香は言った。
「だからといって危険がすべて無くなった訳じゃない。人間は獣だから衝動はいくらでもあるわ。いつか本当に逃亡生活を送るはめになるかもしれないわね。悪 も善もこの世には掃いて捨てるほどあるのよ」
「お前は―――」
「どっちに転ぼうと、本当は誰にも関係がないのかもしれない。だってそうでしょう。何も無い物には誰も何も望まないわ」
「………!」
「堕ちたいか、留まるべきか考えてみると良いわ。考えようによっては、一番のチャンスかもしれないわよ。…そうね。でもどうしようもなく何もなくなった ら、もう一度私を呼ぶと良いわ。」
「それって、お前が俺を殺すのかよ―――」
文月小夜香は微笑んだ。
「自分に望みの無くなった時こそが本来の死に時よ」
俺は混乱する。果たしてこれが俺と同じ世界に生きる女だろうか。俺のどうしようもない世界に俺が依存しているなんていう女が。
「もともと、全員不老不死の遺伝子を持ってるらしいわ。生き物は。それがどうして寿命なんてあるのかしら?」
「それは…他者がいるからだ。」
「…そうね、悲しいけれど自己で完結してる人間はいないってことだわ。じゃあ、もう私には用事はないわね?」
「…お前のおかげで失敗したからな。いけよ。これからどうするか、お前がいなくなってから考える。お前がこれ以上いるとお前を殺してしまいそうだ」
「じゃあ、まだ呼んでる人間がいるから行くわね…今度こそ本当ならいいんだけど」
そんなことを呟きながら、黒衣は地下街をすりぬけて人ごみにまぎれて行った。まるで俺の心は暴風が吹き荒れた後のようにすんでいた。
あいつがふるったのは口先というナイフだけだというのに―――。
殺さなくてすんだという安心感も無く、行き場は相変わらずないまま、選択肢だけを与えられて俺はたたずんだ―――。
いつの間にか雨が降っている。
ビルの屋上、留まるべきか堕ちるべきかだれかがまだ迷っている。
手を差し伸べる人間はその瞳に何をみるだろう―――。
最新の画像もっと見る
最近の「再録、リメイク」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事