今日は久しぶりに小更新。次に大更新を予定しているんだけど、たまには文字ベースで作っても良いんじゃないかと思ってね。
無月:無風で満月下を想定して作ったキャロ
反月:曇りで暴風圏を想定して作ったキャロ
そして、今宵、第3の特殊キャロの制作に取り掛かった。ある日、神様が僕の頭の上に降りてきたんですよ。
神様「カポコンよ。どうしたもっと釣れるだろ?もっと釣れ、もっと釣れ」
んで。神様が僕の頭の中にキャロの設計図を描いてくれたのです。
第3のFキャロその名は・・・・
「狐月
英名:Moon Fox!」。シチュエーションは、ボトム取りと特許が取れるかもしれない 2段スイッチの採用。
2段スイッチについては前々から構想があった。
「2段スイッチ」を発案するまでの苦悩
発想の起点になったのは、アタリウキと水中ウキの2段仕掛けからだ。なぜ水中ウキが必要なのか?それは、表層と深層での水流差が生まれた場合だ。表層の潮の流れが速すぎて、深層の流れが緩やかな場合、これが実に厄介で、確実に糸ふけが出てしまう。
確かに、反月を使うことも考慮に入れていたんだけど。深くて遠い場所の繊細なアタリは、意外に今のタックルではフィネスフィッシングも含めて不可能とされてきた。
その理由は、竿にアタリを伝える伝達素材のラインが外力からの圧力に弱い事に起因する。更に、外力といっても潮のレンジで潮の流れの違う潮ヨレに関しては現行モデルで解決できた例が無い。
釣り師は糸を細くしたり、エサのサイズを変えて吸い込み力をアップさせてきたのかもしれないが季節によってはエサのサイズアップは全くの役に立たないことも多い。
キャロや、水中ウキは、スプリットは、この糸のタルミに効果的にアプローチをかけることが重要であり、また、適所とされるライン上でプッシュをかけることで糸の張力は保つことができ、アタリを竿先に伝える事ができる。
キャロにおけるデメリットは、糸に傷を付ける可能性があることだ。これはキャスト方法にも起因する。糸に対して強いストレスをかけてキャストするとフロロなんかだと途端にダメになる。また、キャロに使用されているチューブ素材も大切な要素である。
これは現行で売られている【硬質カラミパイプ】がコストパフォーマンスに優れた素材である。それ以外の素材は、伝導業界の連中から横流しで貰っている。Mキャロのチューブは安価なパイプを採用しており、すぎにライン上にストレスがかかり長いゲーム向きの構造を有していないと断言できる。Mキャロを使用すればするほどラインが痛むのである。
1年前、私が作成した「レッドリーフ F22」は既にこの手のライン問題を解決済みであり、キャロによってラインがダメになるというのも経験したことがない。にも関わらず、Mキャロは1時代ブームを「未完成」な構造を元に金儲けの道具に使ったのである。
TICTは釣りに関しても未完成な初心者集団を多く採用し、もはや情報戦で私のような反乱分子を見つけては潰す作業に取り掛かっているといっても過言ではない。元々アジングは元来の釣りではないので、しばしばエサ釣り師とのトラブルが耐えなかった釣り。
未だに釣っている姿を見て「メバル、釣れてますか?」と声をかけられる事も少なくない(今は、爆釣してますけどねw)TICTの未完成なシステムを尻目にし、黙々と私がとりかかったのは2段スイッチという構想だった。
2段スイッチ構想とは?
キャロを2重(水中ウキ×2)みたいにしてしまうと、それこそラインに対して強いストレスが働いてしまう。かといって水流ストレスに関し、適度なアーチ構造を保つことがアジングにおいての大前提である。
水中アーチを保つための水中運動をいかにするべきか?
それが2段スイッチ仕掛けである。
仕掛けを言ってしまおう、恐らく言ったところでTICTの初心者軍団ごときにその技術を開発できるだけの脳を持つ者はおるまい。先ず、空中でこのキャロは推定50m付近の飛距離を持つ、キャロは着水と同時に表層まではジグヘッドと行動を共にする。しかし深層に入るとスイッチが入り、キャロだけ釣り人のところまで移動してくるという算段だ。
これが2段スイッチの発想のキッカケになった。なおかつ魚に関して不必要に「重たいもの」を加えているという感覚を与えないためだ。深層にジグヘッドを送り込み、そこから方向転換で急いで釣り人のとこに自動移動を開始する。その距離、実に30m。
つまり、50m先にキャロとジグヘッドは着水し、ボトム付近から釣り人のいるところへフロントスライドを開始する。それで釣り人の約20m手前で着底するというまさに「悪魔のキャロ」と呼ぶべき内容なのだ。
水深9~10m付近を狙うように設計されており、ジグヘッドとキャロを7~8m(塩分濃度によって調整)付近まで一緒になって沈み、その後、ラスト1mで20m手前の走行遊泳を自動開始する。分かるまい・・・(-)ニヤニヤ。
この2段スイッチは、かなり綿密に時間を割いた。Macを開き、CADシステムと流体力学の参考書を読みあさりながら、独自にソフトを作ったりもした(←もともとはプログラマ・SE)、水中運動もそうだけど、かなり綿密な計算を用いた。そして27種類の物質を試した。
では、最後になぜ「狐月」という名前をしたのかだけについて・・・。
なぜ「狐月」と命名したか?
理由の1つは、魚をダマせるから、そして、キャロの動きを断面図化すればそれはまるで弧(満月)を描くがごとく動くから、だから・・・「狐月」!
以上だ。小更新とか言いつつ、長々と失礼します。
最新の画像[もっと見る]
-
 更新しなさすぎ
10年前
更新しなさすぎ
10年前
-
![[vol.1-1]【初心者向け】3要素で運用せよ](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/55/43/ba1ded3e191d49aad1324caaa9caa4f5.png) [vol.1-1]【初心者向け】3要素で運用せよ
10年前
[vol.1-1]【初心者向け】3要素で運用せよ
10年前
-
![[vol.1-1]【初心者向け】3要素で運用せよ](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/4f/e6/cc248e15d0cc66086dc333a11372781e.png) [vol.1-1]【初心者向け】3要素で運用せよ
10年前
[vol.1-1]【初心者向け】3要素で運用せよ
10年前
-
![[vol.1-1]【初心者向け】3要素で運用せよ](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/3b/3f/256d7992d774db4a1dbb49e7e2bf1676.png) [vol.1-1]【初心者向け】3要素で運用せよ
10年前
[vol.1-1]【初心者向け】3要素で運用せよ
10年前
-
![[vol.1-1]【初心者向け】3要素で運用せよ](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/75/5c/79f6bd541be9f49aa3c9cdd07b7e1fce.png) [vol.1-1]【初心者向け】3要素で運用せよ
10年前
[vol.1-1]【初心者向け】3要素で運用せよ
10年前
-
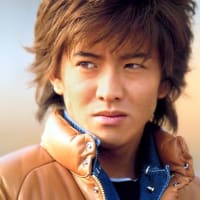 もし「ジョジョの奇妙な冒険 part3」がドラマ化されたら・・・
12年前
もし「ジョジョの奇妙な冒険 part3」がドラマ化されたら・・・
12年前
-
 もし「ジョジョの奇妙な冒険 part3」がドラマ化されたら・・・
12年前
もし「ジョジョの奇妙な冒険 part3」がドラマ化されたら・・・
12年前
-
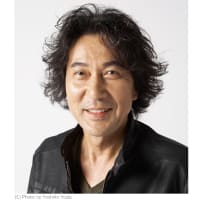 もし「ジョジョの奇妙な冒険 part3」がドラマ化されたら・・・
12年前
もし「ジョジョの奇妙な冒険 part3」がドラマ化されたら・・・
12年前
-
 もし「ジョジョの奇妙な冒険 part3」がドラマ化されたら・・・
12年前
もし「ジョジョの奇妙な冒険 part3」がドラマ化されたら・・・
12年前
-
 もし「ジョジョの奇妙な冒険 part3」がドラマ化されたら・・・
12年前
もし「ジョジョの奇妙な冒険 part3」がドラマ化されたら・・・
12年前










