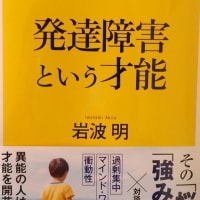副題は『「ウォー・ギルト」をめぐる攻防』だ。
GHQが、「真相はこうだ」といったラジオ番組を通して、日本人を再教育しようとしたことは知っていたが、心理作戦として「ウォー・ギルト・プログラム」なるものが存在したのは最近になって知った。
心理戦について研究しようとしている教え子が、これをテーマにして叩き台を持ってきたからだ。
資料作成の目的やテーマの概要説明から、彼が『正論』などに掲載される、一部の偏向した歴史観に依拠しているであろうことに気づいた。(かつての私がそうであったから、すぐにわかるのだ)
もっと学術的な論及があるだろうと探して、意外な少なさに驚いた。江藤淳の言ったことが波及して右翼論壇で事実のように語られており、その手の感情的で非学術的な書籍はたんまり出ているのに、研究者によるアカデミックなものは賀茂氏くらいしか見当たらなかった。
必読書であろうと手にした。
日本政治外交史・占領史を専門とする名古屋大学大学院の特任准教授である。
歴史を網羅的に、文献に依りながら紐解いてみせてくれる。歴史をほじくり返して何らかの解釈・意見をするなら、こうした検証を行ってほしいものだが、わざとなのか面倒くさいのか頭が悪いのか、中国や韓国が大嫌いな輩は、それをしないで、他人に聞いた風なことを事実であるような語り口で書く。もはやそれは文芸であう。そう、江藤淳は歴史家でなく文芸評論家だったのだ。
90年代末、『新しい歴史教科書をつくる会』が結成されたころ、かつて江藤淳が唱えた“GHQによる洗脳言説”というのが持ち上げられ、それこそが“自虐史観”の原因であるという物語が語られるようになったようだ。ある意味『つくる会』のレーゾンデートルのようなものに祭り上げられたと皮肉な思いで眺めてしまう。
実際には、江藤淳は『ウォー・ギルト・プログラム』のごく一部を拾い読んで、あとは自分の印象や直感だけで、日本人の歴史観は洗脳されたと説いたことを、著者は指摘している。実際に公開されている公文書を丹念に調べる学者ならば、そうでない者のつまみ食いは一目瞭然なのであろう。
この新書を読み終えて思うのは、GHQが思った以上に急拵えの、流動的な組織だったということだ。
戦後すぐに『ウォー・ギルト』を担任したGHQの職員は、戦争中に心理戦を行っていた者であったり、きわめて左寄りのニューディーラーや、中には共産党員だったことを窺わせる者もいる。
彼らの思惑や理想が、GHQや本国の要求との兼ね合いの中で薄められたり、改変されたりし、首尾一貫した方針で占領政策が進められたのではないことがよく理解できた。
また、強度の『ウォー・ギルト』は取り下げられ、日本人が主体的に気づいていくようなソフトな再教育に換わっていく様子も勉強になった。相手の傷に塩を塗り込むのは良くない、という判断である。それはアメリカのフィリピン統治で得た経験則であったし、一方で無差別爆撃や広島・長崎への原爆投下への恨み、批難を抑制するための、賢い占領政策であったろう。
敗戦国を裁き、民主国家として、逆らわない国に作り直す。これにあたって、アメリカもまた、自らの『ウォー・ギルト』を気にし続けたのだということがわかった。反米の世論を恐れたのであって、彼らが反省したというわけではないのだろうが。
しかし、よく言われているように、日本人は空気を読むのに聡い民族で、GHQの検閲を受けるまでもなく、次第に自主検閲のようにして忖度することを覚えていったようである。
長いものに巻かれておれば、商売繁昌でエエじゃないか、というのが、被占領期日本の世相であった。
洗脳は一方的にされたのでなく、日米が共犯のように行ったと観る方がいいだろう。勿論、官民ともに。
最新の画像もっと見る
最近の「評論・評伝」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事