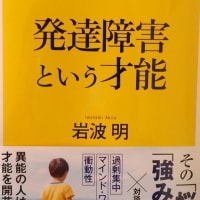様々な戦争文学、戦争に関するノンフィクションを読んできたが、従軍看護婦が書いたものは手にしていなかった。古書チェーンで本書を見つけて、そのことに気づいた。
沖縄戦を描く数々の作品から、従軍看護婦には悲壮・悲惨なイメージしかなかった。
劣悪な環境で看護にあたり、事に臨んでは軍と運命を共にする。場合によっては日本兵や敵兵の慰みものにされる・・・そんな先入観さえ抱いていた。
そのため、本書は目から鱗だった。男尊女卑の当時の社会にありながらも、彼女らが尊ばれ、大切にされていたこと。大陸の陸軍病院で勤務しながらも、休日には観光を楽しんでいたこと。
とはいえ、終戦間際の混乱と、敗戦国の看護婦となってからの貧窮する日々は苦労が偲ばれ、まさに彼女らの戦記は終戦とともに佳境に入ったのだと感じた。
国共内戦に、日本の医療従事者は巻き込まれていく。知識としては知っていたが、その徴用をめぐる駆け引きはなかなかのサスペンスだった。
おそらく、戦後だいぶ経ってから記憶を頼りに綴ったものだろう。細部の描写は部分的にしか無いし、全般に良い思い出だけが濾過された清水のように抽出された印象も受ける。
あとがきで、甥の桂氏は「叔母には書けないこともあったらしい」と指摘している。本書には描かれないが、孤児の兄弟を保護して連れ帰ったらしい。
意図的に、他者への迷惑を考え、ぼかしているところも多かったようだ。そうして思い出すうち、書けることは楽しい思い出に偏りがちだったのだろう。
正気を保つための、戦中派の知恵なのかもしれない。それを、読了後に気づかされた。
最新の画像もっと見る
最近の「ノンフィクション」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事