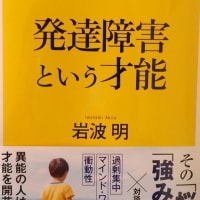いま、われわれは如何にヒロシマを“想像”できるだろうか。
核兵器が戦争への抑止力であるという免罪符を世界が持ち続ける限り、ヒロシマは“歴史”ではなく、進行する“現実”だ。
本書は1960年代前半、大江健三郎が旅し続けたヒロシマをノートしたものである。
《この政治的時代には、ひとつの国の新たな核武装が、かえって核兵器の全廃への道につうじる、というお伽話が現実的である可能性もあるという人たちがいるかもしれない。(中略)しかし、僕は見すごすことはできない、すなわちそのお伽話の城へむかって一歩踏みだされた現実的な足は、広島のいまなお昏い室内でケロイドを恥じながら青春をすでにうしないつつある娘たちの自己快復の希望を、確実に踏みにじったのである。そして、それでもなおかつ、実際的に核兵器全廃の見とおしがおとずれていないという現状が、広島の人間たちにとって、まったくどれほど苛酷なことであるか、僕はそれをおしはかる勇気をもたない。》
これは、われわれの倫理、威厳に関わる問題である。
人は、臭いものに蓋をしたがる。“自然”な心理だ。しかしその態度が許されない場合もある。蓋をしたいなにものかが、いかなる意味においても“自然”ではなく、不合理・不条理に満ちている場合だ。
われわれはあらゆる意味で“生き残り”である。原爆という不条理、それも人的に行われた不条理に、蓋をすることは罪である。私にはそう思える。
しかし人々は、心地よいもの、罪のない感動譚をのみ求め、自らが被ることを意図せぬ、他者の苦しみには目を背けようとする。この無関心。想像力の欠如。率直に言って、これらが、人が人を殺戮する原動力になりうる。
《おなじ年の夏、広島で企画されたもう一冊の本は、印刷され製本されながら、しかも、ついに刊行されることがなかった。占領軍がそれを、あまりに被爆の現実をなまなましくえがきすぎた本だとし、反米的だとして、発行禁止処分に附したからである。1950年、それは朝鮮戦争のはじまった年であり、ひとりのアメリカ人の新聞記者が広島をおとずれて、盲目の被爆者にこう訊ねた年であった。「いま朝鮮に、原爆を二、三発落せば、戦争は終ると思うが、それについて被爆したきみはどう思うかね?」》
…いまでもアメリカ人の多くは、被爆の実態を知らないという。
日本ではどうか。私の下の世代は、教科書的な触りの知識を持っていれば良いほうである。そして私も、広島に住んでみるまでは、“歴史”としてしか、原爆を知らなかった。
個人的な話になるが、私は最も多感な八年間を広島で過ごした。そこには教科書でしか知らなかった“歴史”が“現実”として進行していた。少なくない友人たちが被爆2世、3世であり、またその中には在日朝鮮人の3世もいた。
彼らはそれを気負ってはいない。仲良くなってしばらくして、さりげなく私にそれを伝えた。
気負いはないとしても、明らかにそこには不安があり、彼らを差別し差異化する世間があった。
広島の友人らを、“彼ら”と呼ぶのはたやすい。それを取り巻く世間を“彼ら”と呼ぶのには、甘い誘惑すら感じるだろう。
だが。
どちらも“われわれ”であると呼ぼう。大江健三郎はしきりに人間の威厳を考える。もしそれに私の態度を表明するなら、私は常に、“われわれ”であることを考える。
限界状況は続いている。