ふと思うことがあり、
転職について書いてみたと思います。
私自身は、自分のキャリア形成で悩み、キャリアアドバイザーの勉強をして
せっかくなので資格も取りました。
資格を取ると、使ってみたくなるもので、実際に紹介会社で転職のお手伝いをしました。
いろんな方の、迷いや決断に触れさせていただき、
自身の人生を考えるうえでも、とても貴重な体験となりました。
さて、その「転職」ですが、
結婚になぞらえて、「相性」「縁」「条件」などと言われたり、
いろんな事例があって、奥が深いと感じます。
ちなみに、私自身はキャリア論を学ぶ中で、クルンボルツ先生のいう「8割が偶然」※という考え方に賛同しています。
今回は、一般的な【転職する流れ】についてご案内いたします。
※詳しくは、「planned happenstance thory」です。
わたし自身は「人生の8割は結果偶然」と理解したのですが、言葉が足りていないです。
ご興味ある方は、ぜひ検索いただき、詳細をご覧ください。
なお、転職する個人を主体に書いていますことをご容赦ください。
---------------------------------------------
【転職する流れ】
常に、本当に転職したいのか/転職したほうがいいのか、考えながら
下記作業をする
(今、何か仕事をしているなら、それをひとまず頑張ってみる)
・自己分析して、自身の強み・弱みを言語化。
↓
・職務経歴書にまとめる
↓
・求人票をたくさんみて、いいと思うものを深堀していく。
同時に、紹介会社や詳しい知り合いなどとの会話を通じ、相場などを掴む。
↓
・応募したい会社や職種についてしっかり調べて、自身の強調ポイント等変えて
応募書類を(応募する会社ごとに)準備し、応募する。
↓
(面接に呼ばれたら)
↓
・面接対策する。
聞かれるかもしれない問いを10以上用意して、簡潔に伝えられるようなるまで練習
書いたり、誰かに聞いてもらったりして、「自分の言葉」として語れるようになるまで練習あるのみ
※アナウンサーになった友人は、シャワー浴びながらあの時の質問には「こう」答えればよかった、と1日を振り返り、実際に「こう」と思う内容を口に出して話しているとのことでした。
これで、次の場面で似たようなことを聞かれたとき、すらすら言葉が出てくるのだとか。
そこから、わたしも、シャワーを浴びてるとき、つい一人反省会をはじめ、ぶつぶつ言ってしまいます。
↓
・内定まで粘る
※職種などにもよるのかもしれませんが、
私自身は「複数同時応募」を勧めていましたし、自身もそうしました。
応募するまでと実際面接の場での印象は変わること、
(第3希望と言っていた会社が第1希望に変わる例を多く見ました)
口頭でいい雰囲気でも、内定書面が出るまでは、結果がわからないこと、
などの理由からです。
ただ、ご自身の納得や先方の採用のやり方などもあり、1社ずつ結果を確認することも大切と思います。
↓
・転職する/しないを決める
↓
・補足:
勤務後すぐ~3か月くらいの間に、たいてい「言ってたことと違う」となります。
どこまで許容範囲とするかは難しいのですが、ある意味、面接時には自分も気分が高まっていてお互い2割(5割?)増しになっている、という冷めた気持ちも必要かもしれません。
---------------------------------------------
私自身の経験では、
「自己分析→言語化し、応募書類にまとめる」
というのが最初難しいと感じます。
仕事をする場合、上司の指示や、ミーティングの合議で進めています。
よって「わたしがこの仕事をしました」「◎◎なら任せてください」
というアピールをするのはすごく難しいと感じます。
技術職だと、手練れ度
営業職だと、成績
経理などの専門事務だと、経験
といった内容で判断されやすいですが、
それがないからダメということはありません。
チームの中で、どういう役割を担ってきたのか、
どういう貢献ができるのか、
今後、どういうことに興味があるのか
これらをしっかり言語化すること。
でも、一度できると、今度は「応募したい理由」を作るので悩みます。
(その場合は転職しないのがいいのかもしれませんが)
たくさんなる中から「なぜこの仕事」なのか。
なぜ今の仕事では達成できないのか。
また、最近は転職する方も増えており、
上記流れほど堅苦しくなく、ご縁で決まることもあるかと思います。
なお、転職活動をしてみて、結局転職をしないと決めてもいいと思っています。
それで、今の仕事に集中できるようなれば、それはそれでいいことなので。
社会保険とかでいえば、同じ会社にいたほうがいいとか、
終身雇用が保証されない時代だから、まだ気概のあるうちに転職を経験しておくとよいとか
いろんなことが言われますが、
すべてケースバイケースとなります。
ようは、どっちでもいえるので、
まずは、ご自身の状況・気持ちを土台にと思います。











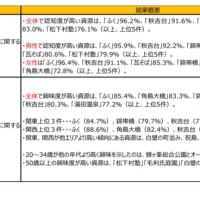
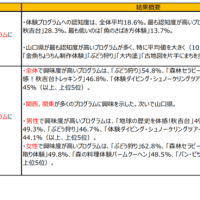
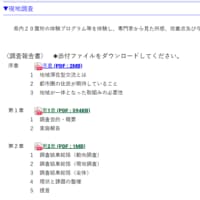
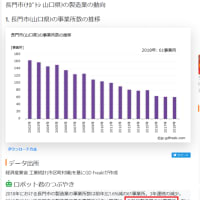
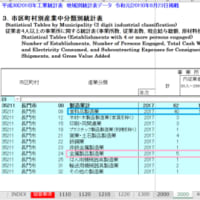


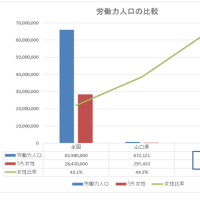
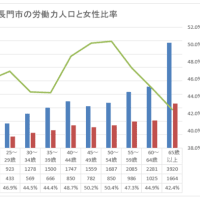
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます