日本の政治経済的課題 (その5- - -1970年代の総括 (3))
著者は続けます。
"1973年10月6日エジプトとシリアがイスラエルを不意打ちして、Yom Kippur War が勃発した。アラブ石油輸出機構(OAPEC)は素早く対応した。最初に、アラブの主義を支持しなかった者には石油の供給を停止し、次に石油の価格を5倍にした- -(第1次オイルショック)。日本に及ぼす影響は悲劇的であった。日本はそのオイルの99%を中東から輸入し、そのエネルギー供給の90%を石油に依存していた。石油が値上がりするや恐慌と大混乱が起こった。日本人の秩序正しい振る舞いはこの危機の中で崩壊した。自己よりグループを優先する倫理は突然 '全ては自分自身の為にある'という観念に取って代わられた。品薄であると噂になったものは、恐慌買いにより、本当に品薄になった。トイレットペーパーと洗剤は小売店で品切れになってしまった。人々はお金を引き出すべく銀行や貯金機関へと走った。製造者達は、好機到来とばかりに、故意に市場への供給を差し控え恐慌買いを誘発させ、かくして価格と利益を膨らませたのである。石油会社は価格協定連合を形成し、他の業界の会社は違法なカルテルを組んだのである。集約すれば、彼らは市場に出す殆ど全ての商品に対して、この売り手市場という新奇な情勢を利用するべく奔走した。非常に競争的な買い手市場で、最善を尽くして、お互いの首を絞めあってきた- -それは過去20年間の特色であった- -彼等は、過去とは違って、消費者から利益をむしりとることに共通の利益を、突然発見した。
'独占禁止法やカルテル防止法などくそ食らえだ。これこそ一生に一度の好機である。’
幾月かは、この考え方は正しいかのように見えた。政府は彼等を懲戒したり罰したりすることは何もしなかった。しかしそれは後から来るのだった。当座は、政府はどうしたら良いか分からなかったのである。石油価格の上昇は価格に対しては、インフレ的であるが、需要に対してはデフレ的である。それはインフレーションを直接に増加させるが、他方では、日本人のポケットからお金を取り、アラブの石油を産出している種族長に、それを渡すことによって、日本人の実質所得を減らしたので、消費者の支出は激減した。この第1次オイルショックは日本経済の前進しようとする足を踏みつけ、日本経済が既に進みかけていた良からぬ方向に更に推し進めたのである。1974年4月までの1年間は消費者価格のインフレーションは26%に達した。1974年の賃上げ闘争--いわゆる春闘--はしたがってひどいものになった。労働組合が、労働者は会社の利益の分配にあずかるべきだと賃上げを要求したことだけではなく、労働者と雇用主との間の協調体制が、大企業が品物不足の情勢を悪用して消費者を搾取したやり方を労働者が知っている為に、崩れてしまったのである。会社は労働者のインフレ的な賃上げ要求に逆らう根拠を持たなかったのである。会社が売り手市場の中で消費者からむしりとったのと同じように、結果を省みず、労働者は単に彼らの折衝力を悪用したのである。脅威の成長の時代には、膨張した利益を労働者と分け合うことが全般的に実質生活水準を上げたが、この一時に偶然に訪れた投機的な利益を分け合うことは全く違っていた。これらの利益は、増加した製造能力、販売、及び生産性という永続的な基礎を持つものではなく、一度限りの利益であった。それらは蒸発してしまうものであったが、賃金は定着するものであり、永続して労働コストを上げるものである。これらの余分のコストは、価格に転嫁されるか、あるいは雇用の減少によって吸収されるかされるであろうことは不可避であった。驚いたことに、彼等が暴利をむさぼったことに政府は見て見ぬふりをするのではないということを会社は発見するのである。彼らは、なかんずく政府の会計と財政の放漫さによって引き起こされたインフレーションの身代わり山羊として名指しにされたのである。1974年2月公正取引委員会の役人が、いくつかの石油精製会社の事務所に捜査令状で立ち入り、違法な価格カルテルを操作した罪で数人の社長が起訴された。同様な立ち入りが貿易会社と洗剤の会社でも行なわれた。暫くして国会がインフレーションを議論したとき騒ぎが起こった。野党は暴利をむさぼった会社は処罰され、納税者は消費者搾取で得られた過度の利益を償われるべきであると主張した。その結果、野党は政府をして、降って沸いた僥倖である異常な利益に税金を課す '特別の暫定会社利益税法' を通させた。産業界は、労働組合に対して出したのに続いて、納税官にも、その過剰利益を支払うことを強要されたのである。石油価格の高騰は田中首相の野心的な2桁成長率の成長を継続するという野心を打ち砕いたのである。インフレを抑制することが第1の優先事項となった。1973年12月、日本銀行はその公定歩合を2%上げて記録的な9%にした。さらに不動産会社、建設会社、及び貿易会社などの問題の業界に関して特別な貸し出し限度額の制限を課すべく '窓口指導' が行われた。トイレットペーパーや液化石油ガスからビニールクロライドに至る主要な製品に関して価格統制が導入された。1974年度の予算は緊縮予算となり、1972年と1973年に入れられた壮大な公共投資計画は停止されたり延期されたりした。システムは突然ストップした。石油価格の上昇に引き続いて起こった円レートの低下とそれが惹起した国際収支の赤字により事態は更に悪化し、会社はエネルギー、原材料、及び賃金の高コストに直面していた。国内市場も国際市場も崩落したのでこれらのコストをもはや価格に転嫁出来ないことに彼らは気づいた。経済はリセッションに入ったので、土地価格、原材料価格、証券市場の株価も大暴落した。熱心に進めてきた財テクの投機の結果は、厄介な実現損失となって現れた。生産は落ち込み統計的な失業指数は、あまり上がらなかったけれども、労働時間の減少や、強制された長期休暇の形で、隠れた失業指数は急激に増加した。1975年、日本の実質GNPは、第2次大戦後初めて前年比マイナスを記録した。日本の成長の船は、石油ショックという魚雷を受けて、大打撃を受け、田中内閣は船とともに沈んだ。田中首相は、62%の支持(1990年に海部首相に抜かれるまでは今までの最高の支持率であった)を受けて登場したが、2年後の1974年12月たった12%の支持率(1989年竹下首相と宇野首相はこれより下回ったが)で、首相の座を去った。1976年には実質GNPは急激に回復した。そしてその後は安定した一定の率(約5%)で成長を続けるのである。1960年代は成長は平均、年率11%であったが、1970年代の後半はやっと平均、年率5%であった。輸出がなかったらこの数値はもっと悪かったであろう。オイルショックは貿易の条件を日本に不利にした。1973年から1976年の間で日本の輸出価格は50%しか上がっていないのに、輸入価格は130%上がった。不変の輸入額を輸出で賄うためには、輸出を25%増やさねばならなかった。1974年も1975年も日本は輸出をその様に増やす手立てがなかった。リセッションに苦しんでいたのは日本だけではなく、その外国市場もまた崩れていた。さらに、経済がリセッションに移行しているので輸入量も減ったが、輸入価格上昇を埋め合わすことは出来なかった。他の工業国と同じ様に、日本も国際収支の赤字に突入したのである。1972年から1974年の間に、日本の経常収支は、GNP比2%の黒字から1%の赤字に落ち込んだ。1975年には、輸出が回復したからではなく、輸入が落ち込んだから、経常収支は均衡に戻った。しかしながら1975年の終わり頃から日本の輸出は再び力強く増加し始めた。石油ショックのリセッションの深さに驚いたアメリカとイギリスはりフレーション政策(*注記参照)を余りにも短期に激しくやり過ぎたが、日本とドイツはりフレーション政策をやったが少なすぎたし遅すぎた。したがって日本はアメリカのこのりフレーション政策の恩恵にあずかることが出来た。日本の会社は、いつもの様に、国内市場が停滞すると攻撃的な輸出に打って出る。今回は円の弱さに助けられた。その結果、1976年には日本の国際収支は黒字に転じ、日本は1978年までこの黒字を継続した。一方 アメリカは、1975年の黒字から、1978年には少しの赤字に陥った。日本もドイツも、アメリカの膨張政策にただ乗りしたと、諸外国に見られたのである。アメリカは世界の諸国を引っ張っていたので、'機関車経済' と呼ばれた。日本は1976年からづっと、全ての国際会議と特に先進7カ国首脳会議において、ただ乗り国として非難された。1977年の暮れ、日本は1978年度は7%の成長率とすることに合意させられ、1978年のボンのサミットはこの目標が達せられるかどうかの議論で多くの時間が費やされた。1975年からスタートして日本の財政政策は膨張的になった。田中首相は1970年代の初めの多額の赤字予算の為に厳しく非難されたが、彼を引き継いだより保守的な首相継承者は更に多額の赤字予算を組んだのである。1975年から1978年までに遂行された経済刺激策は国の国債額を大きく膨らます結果となった。予算赤字の性格もまた変化した。石油ショック後公共投資は厳しくチェックされる一方で、社会保障の出費は急激に増加し始めた。1980年代に国の赤字予算を抑制する時が来たときに、公共投資は低く抑えても、削減の一番難しいのはこの最も多額の社会保障費であった。”
*注記
リフレーション政策(reflation policy):インフレーションにならない程度に、通貨を膨張させて景気を良くする政策。
著者は続けます。
"1973年10月6日エジプトとシリアがイスラエルを不意打ちして、Yom Kippur War が勃発した。アラブ石油輸出機構(OAPEC)は素早く対応した。最初に、アラブの主義を支持しなかった者には石油の供給を停止し、次に石油の価格を5倍にした- -(第1次オイルショック)。日本に及ぼす影響は悲劇的であった。日本はそのオイルの99%を中東から輸入し、そのエネルギー供給の90%を石油に依存していた。石油が値上がりするや恐慌と大混乱が起こった。日本人の秩序正しい振る舞いはこの危機の中で崩壊した。自己よりグループを優先する倫理は突然 '全ては自分自身の為にある'という観念に取って代わられた。品薄であると噂になったものは、恐慌買いにより、本当に品薄になった。トイレットペーパーと洗剤は小売店で品切れになってしまった。人々はお金を引き出すべく銀行や貯金機関へと走った。製造者達は、好機到来とばかりに、故意に市場への供給を差し控え恐慌買いを誘発させ、かくして価格と利益を膨らませたのである。石油会社は価格協定連合を形成し、他の業界の会社は違法なカルテルを組んだのである。集約すれば、彼らは市場に出す殆ど全ての商品に対して、この売り手市場という新奇な情勢を利用するべく奔走した。非常に競争的な買い手市場で、最善を尽くして、お互いの首を絞めあってきた- -それは過去20年間の特色であった- -彼等は、過去とは違って、消費者から利益をむしりとることに共通の利益を、突然発見した。
'独占禁止法やカルテル防止法などくそ食らえだ。これこそ一生に一度の好機である。’
幾月かは、この考え方は正しいかのように見えた。政府は彼等を懲戒したり罰したりすることは何もしなかった。しかしそれは後から来るのだった。当座は、政府はどうしたら良いか分からなかったのである。石油価格の上昇は価格に対しては、インフレ的であるが、需要に対してはデフレ的である。それはインフレーションを直接に増加させるが、他方では、日本人のポケットからお金を取り、アラブの石油を産出している種族長に、それを渡すことによって、日本人の実質所得を減らしたので、消費者の支出は激減した。この第1次オイルショックは日本経済の前進しようとする足を踏みつけ、日本経済が既に進みかけていた良からぬ方向に更に推し進めたのである。1974年4月までの1年間は消費者価格のインフレーションは26%に達した。1974年の賃上げ闘争--いわゆる春闘--はしたがってひどいものになった。労働組合が、労働者は会社の利益の分配にあずかるべきだと賃上げを要求したことだけではなく、労働者と雇用主との間の協調体制が、大企業が品物不足の情勢を悪用して消費者を搾取したやり方を労働者が知っている為に、崩れてしまったのである。会社は労働者のインフレ的な賃上げ要求に逆らう根拠を持たなかったのである。会社が売り手市場の中で消費者からむしりとったのと同じように、結果を省みず、労働者は単に彼らの折衝力を悪用したのである。脅威の成長の時代には、膨張した利益を労働者と分け合うことが全般的に実質生活水準を上げたが、この一時に偶然に訪れた投機的な利益を分け合うことは全く違っていた。これらの利益は、増加した製造能力、販売、及び生産性という永続的な基礎を持つものではなく、一度限りの利益であった。それらは蒸発してしまうものであったが、賃金は定着するものであり、永続して労働コストを上げるものである。これらの余分のコストは、価格に転嫁されるか、あるいは雇用の減少によって吸収されるかされるであろうことは不可避であった。驚いたことに、彼等が暴利をむさぼったことに政府は見て見ぬふりをするのではないということを会社は発見するのである。彼らは、なかんずく政府の会計と財政の放漫さによって引き起こされたインフレーションの身代わり山羊として名指しにされたのである。1974年2月公正取引委員会の役人が、いくつかの石油精製会社の事務所に捜査令状で立ち入り、違法な価格カルテルを操作した罪で数人の社長が起訴された。同様な立ち入りが貿易会社と洗剤の会社でも行なわれた。暫くして国会がインフレーションを議論したとき騒ぎが起こった。野党は暴利をむさぼった会社は処罰され、納税者は消費者搾取で得られた過度の利益を償われるべきであると主張した。その結果、野党は政府をして、降って沸いた僥倖である異常な利益に税金を課す '特別の暫定会社利益税法' を通させた。産業界は、労働組合に対して出したのに続いて、納税官にも、その過剰利益を支払うことを強要されたのである。石油価格の高騰は田中首相の野心的な2桁成長率の成長を継続するという野心を打ち砕いたのである。インフレを抑制することが第1の優先事項となった。1973年12月、日本銀行はその公定歩合を2%上げて記録的な9%にした。さらに不動産会社、建設会社、及び貿易会社などの問題の業界に関して特別な貸し出し限度額の制限を課すべく '窓口指導' が行われた。トイレットペーパーや液化石油ガスからビニールクロライドに至る主要な製品に関して価格統制が導入された。1974年度の予算は緊縮予算となり、1972年と1973年に入れられた壮大な公共投資計画は停止されたり延期されたりした。システムは突然ストップした。石油価格の上昇に引き続いて起こった円レートの低下とそれが惹起した国際収支の赤字により事態は更に悪化し、会社はエネルギー、原材料、及び賃金の高コストに直面していた。国内市場も国際市場も崩落したのでこれらのコストをもはや価格に転嫁出来ないことに彼らは気づいた。経済はリセッションに入ったので、土地価格、原材料価格、証券市場の株価も大暴落した。熱心に進めてきた財テクの投機の結果は、厄介な実現損失となって現れた。生産は落ち込み統計的な失業指数は、あまり上がらなかったけれども、労働時間の減少や、強制された長期休暇の形で、隠れた失業指数は急激に増加した。1975年、日本の実質GNPは、第2次大戦後初めて前年比マイナスを記録した。日本の成長の船は、石油ショックという魚雷を受けて、大打撃を受け、田中内閣は船とともに沈んだ。田中首相は、62%の支持(1990年に海部首相に抜かれるまでは今までの最高の支持率であった)を受けて登場したが、2年後の1974年12月たった12%の支持率(1989年竹下首相と宇野首相はこれより下回ったが)で、首相の座を去った。1976年には実質GNPは急激に回復した。そしてその後は安定した一定の率(約5%)で成長を続けるのである。1960年代は成長は平均、年率11%であったが、1970年代の後半はやっと平均、年率5%であった。輸出がなかったらこの数値はもっと悪かったであろう。オイルショックは貿易の条件を日本に不利にした。1973年から1976年の間で日本の輸出価格は50%しか上がっていないのに、輸入価格は130%上がった。不変の輸入額を輸出で賄うためには、輸出を25%増やさねばならなかった。1974年も1975年も日本は輸出をその様に増やす手立てがなかった。リセッションに苦しんでいたのは日本だけではなく、その外国市場もまた崩れていた。さらに、経済がリセッションに移行しているので輸入量も減ったが、輸入価格上昇を埋め合わすことは出来なかった。他の工業国と同じ様に、日本も国際収支の赤字に突入したのである。1972年から1974年の間に、日本の経常収支は、GNP比2%の黒字から1%の赤字に落ち込んだ。1975年には、輸出が回復したからではなく、輸入が落ち込んだから、経常収支は均衡に戻った。しかしながら1975年の終わり頃から日本の輸出は再び力強く増加し始めた。石油ショックのリセッションの深さに驚いたアメリカとイギリスはりフレーション政策(*注記参照)を余りにも短期に激しくやり過ぎたが、日本とドイツはりフレーション政策をやったが少なすぎたし遅すぎた。したがって日本はアメリカのこのりフレーション政策の恩恵にあずかることが出来た。日本の会社は、いつもの様に、国内市場が停滞すると攻撃的な輸出に打って出る。今回は円の弱さに助けられた。その結果、1976年には日本の国際収支は黒字に転じ、日本は1978年までこの黒字を継続した。一方 アメリカは、1975年の黒字から、1978年には少しの赤字に陥った。日本もドイツも、アメリカの膨張政策にただ乗りしたと、諸外国に見られたのである。アメリカは世界の諸国を引っ張っていたので、'機関車経済' と呼ばれた。日本は1976年からづっと、全ての国際会議と特に先進7カ国首脳会議において、ただ乗り国として非難された。1977年の暮れ、日本は1978年度は7%の成長率とすることに合意させられ、1978年のボンのサミットはこの目標が達せられるかどうかの議論で多くの時間が費やされた。1975年からスタートして日本の財政政策は膨張的になった。田中首相は1970年代の初めの多額の赤字予算の為に厳しく非難されたが、彼を引き継いだより保守的な首相継承者は更に多額の赤字予算を組んだのである。1975年から1978年までに遂行された経済刺激策は国の国債額を大きく膨らます結果となった。予算赤字の性格もまた変化した。石油ショック後公共投資は厳しくチェックされる一方で、社会保障の出費は急激に増加し始めた。1980年代に国の赤字予算を抑制する時が来たときに、公共投資は低く抑えても、削減の一番難しいのはこの最も多額の社会保障費であった。”
*注記
リフレーション政策(reflation policy):インフレーションにならない程度に、通貨を膨張させて景気を良くする政策。




















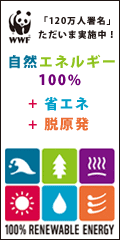






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます