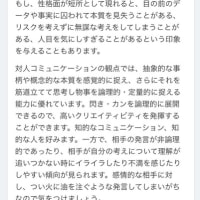こんにちは。
「朋、わたし、分かった気がするんだ。人って凄く色に癒されるのよね。その時々で色が変わることも分かったし、厄除けとか、災難除けって、本人にストレスを与える環境がなくなることっていう意味もよく分かったよ。」
「うーん。それでもさ、ちょっと違うんだよ。本人にストレスを与えない環境ってのは、本人がそれをストレスと思うかどうかなんだよね。」
「あっそっか。どんな人の愚痴でも、そりゃ好きな人の愚痴は割りと聞けてさ、どうでもいい人の愚痴はストレスになるもんね。」
「そうなんだよ。愚痴を聞かされない状態になるって事もそうなんだけれど、愚痴を聞かされても何とも思わないような状態に自分の精神を持っていくのって凄く必要な事なんだよ。まぁ、それでも人間だからね。幾らなんでも限界はあると思うけれどね。」
「うんうん。分かる分かる。でも、ひとって限界を超えたいが為に精神世界とか言うんじゃないの?」
「あぁ、ひとつ言っておくとあんたのスペックをここで紹介しそびれたね。ヨガオタクなんだよね。」
「そ。私もさ、若い頃から色々あって、自分で自分に納得のいく答えが欲しくてヨガを始めたのよ。けれど、朋ってさ、誘ってもヨガに来ないジャン。」
「いや、私だってヨガやっているけれど、流石にあんたの目の前で、大開脚とかしたくないからね。」
「いやだ(笑)。別にコマネチしろって言っているわけじゃないジャン。」
「いや、ほんと、ピラティスとかでうっかり気を許して、おならでもしようもんなら、あんたから、一生色々言われるからね。」
「緩むのも大概にしとけってことよ。朋は、加減を知らないで緩む癖があるし」
「出物腫れ物ところ構わずだよ(涙)。ところでさ、石って、元々、古くは神官や巫女さんたちが使っていたんだよね。」
「うんうん。」
「あれってのは、やっぱり、その石のパワーやカラーに、昔から人が価値を見出してきたってことなんだと思うんだよ。同じ紫でもアメジストとタンザイナイトは随分違う色だし、瑠璃のオパールに関しても色々な遊色効果があって、色々違うんだよね。ダイヤモンドだって、同じ透明な石だけれど、水晶とは違う。色って石によって違うけれど、昔の神官は、凄く大きな石を身につけていた。無論、それが高価なもので、自分の立場を誇張する為にも用いられるし、パワーがあったから、身につけたってこともあるんだよね。」
「ラピスラズリって結構有名よね。」
「そう。あの色、紺碧の青だしね。紫にしても、やはり人々を魅了し、自分のカリスマ性を高めるには、色々な色があって、その紫である必要が昔の神官や巫女さんにはあったんだと思うね。魅惑的に魅せるとしたら、クレオパトラのエメラルドは凄く有名じゃないの。それに、エジプトでは、随分沢山の王女たちや、お后様が沢山の色の宝石を身につけていたじゃない?王様だって、身につけていたよね。」
「うんうん。クレオパトラなんて、真珠飲んだって言うよね。」
「あれは、ローマの将軍アントニウスとね、豪華であればある程いいって言う饗宴を競ったんだよ。その時にさ、国を一つ二つ買えるほどの値打ちのあった真珠のピアスを耳から外して、ビネガーに浸して溶かし、そして飲んじゃったって言う話だね。」
「もう一個いっとく?って事もやったんでしょう。」
「そりゃ、クレオパトラだもの。流石にアントニウスが止めたって言うけれど、そりゃ止めるよね。まぁ、その前にさ、私は、真珠を溶かすほどの威力があったビネガーってものに、流石に驚きを隠せないよ。」
「なんでよ?」
「真珠溶かしてしまうほどの威力の酸でしょ?そりゃ、多少のビネガーは日本で言えば三杯酢ってことで、酢の物なんかに使われているじゃないの。あれじゃ、溶けないんだよね。」
「え?ってことは、凄い強い酸っぱいやつだったってこと?」
「うん。恐らく。だからさ、黒酢で、のどがむせ返っているような私じゃ、あれは饗宴の競いの中のメニューに入らないね。まず、その威力の酢を飲むっていうこと自体、すげー、ビビリだもん。」
「よく考えると、真珠が溶けている酢が飲めるっていう豪華さより、あんたは、真珠が溶けるくらい酸っぱい酢を飲んだ女傑に大拍手ってとこなの?」
「そりゃ、凄いよね。私だったら、腰に手を当てて、ぐびっと行かないと酸っぱくて飲めたもんじゃない。それを、悠々と飲んでみせて、アントニウスに「いかが?」って言ってのけたクレオパトラは凄いよ。流石にアントニウスが止めたのは、もうひとつ、国が買えるほどの真珠を溶かされることより、いっちょ、この女の胃袋を心配したろか?って思ったんじゃないかって、幼い頃は思ったね。ちなみに、自分でもやってみたよ。」
「へ?」
「酢に真珠突っ込んでね。」
「あんたは、普通の実験魔じゃないと思ったけれど、なんてことを。」
「やっぱ、きつくて飲めなかったけど。」
「馬鹿か。」
「だからさ、昔から、宝石や色のある石、カットをする事でとてつもないきらめきを呼ぶ石は、パワーがあり、自分を魅力的に魅せてくれて、そして自分のカリスマ性を高める、財産があるんだと誇示できる、そして、着ける事によって、自分の信念を強くさせるという力は認められてたんだと思うね。」
「そうなんだ。昔の人だって結構なマイナスはあるでしょ?」
「上に立てば、ある程度ひとから妬まれる事もあるし、いじめられることも、陰口を叩かれることもある。それを超える為に自分の心を強くするのに、昔から石は使われてきたんだよ。元々、男性がつける事が多くて、女性が着けるようになったのはその後だよ。まぁ、ライオンのたてがみ感覚かな。」
「あんたが言うと、大昔の神官もライオンレベルか。」
「んまぁ、よくよく考えると、昔から宗教は政治と紙一重だったからね。だから、あながち、全ての陰口を超えて統治していくのに、必要な石はあったんだと思うね。」
「ふーん。昔の人はそういう風に考えていたのね。」
「うん。だから、自分で時々思うよ。自分の石好きは、きっと前世で、石きちがいだった神官ではないかと(苦笑)。」
「それは、ありえるね。あんたのその石好きは、尋常じゃないもんね。でも、今回の雑学は面白かった。今度もまたよろしく。」
「うん。了解。」
朋