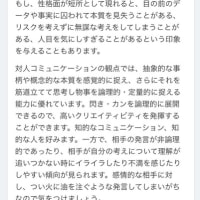|
米国製エリートは本当にすごいのか? |
| クリエーター情報なし | |
| 東洋経済新報社 |
こんにちは。
先日の富士山では、そんなに暇がなかったんで、沢山持っていった本は読めなかったんですが、その内のイージーリーディングをひとつ。
米国製エリートつまり、米国の大学、大学院を卒業した人は、そんなにすごいのかってところについて、現在、30代の著者が、実際にスタンフォード大大学院に入学して、その現実を知ったって感じのレポートを書いてあります。割と軽い本です。この本の中で、色々書いてある意見は、その人独自のモノだとして、米国製エリートになる道は、入り口は広いけれど、出口が狭いってことが書いてあります。
日本の大学に必要なものって言うと、知識豊富な人材を、講師陣に迎えられない低予算的なところがあります。私立だと時々、目玉教師みたいな人がいて、白熱する授業を展開している人もいるんですけれど、まぁ、基本的に、教授や講師にとってみて、研究が第一であって、講義は金稼ぎで仕方なくやっているところがよく垣間見えます。けれど、米国は、大学が実際に、金を運営して、潤沢な資金の中で講師を呼んでくるので、実際に政治家になった人の話なんかも聞けたりするんですね。
町全体が大学の敷地みたいなところがありまして、昔、私が友人をたずねに行った場所もパロアルトでした。
米国では、完全な学歴社会です。その為に、学歴がもてないような低所得の家族に対して、奨学金も豊富に存在しています。まず、学歴。そこからはじめないと、故スティーブジョブス氏は大学中退でしたが、彼は天才的な読みと企画がありました。けれど、あんな例は、もはやないと思ってもいいほど、米国は学歴社会です。
実際に、この季節になると思い出すのですが、NY州郊外では、家族代々ハーバードって家族が多くてですね。IVYリーグとも言う名門校に受かる受からないが決まった頃、必ず、学生の自殺報道が新聞を飾るんですわ。日本はそれでも、何度でも挑戦できますね。ところが、アメリカの場合は、挑戦するのは、一回で、浪人するという概念は基本的にないんです。だから、泣いても笑っても、たった一回のみ。
まぁ、そこで入れる大学に入って、そこから転校することもできますが。
冬の雪降る時期に、家庭が裕福で、大きな家の坊ちゃんが、首をくくったの、嬢ちゃんが、短銃自殺したの、激しいもんですわ。日本の場合、入れなかったから死ぬって事まで考える前に、浪人決定ですけれど、何不自由ない不足ない家庭の子女が、自殺ですわ。
学歴社会の象徴としては、グーグル社があります。
ほんと、真面目に、高学歴しか入ってないです。(日本はどうかわかりませんがね)高学歴の人たちが、お遊び感覚で運営して、そして現在に至るわけで、あれはあれで、それでも、先日のサイゼリヤ商法や、ユニクロ商法などとまた違ったひとつの戦法を持っているんですよ。学歴低くて、あそこで出世は出来ませんしね。まぁ、私も無理な口ですわ(笑)。
学歴がそんなに大事な米国にとって、実質学歴という名目の元に、ほんとうに実力があるのかどうかってことをここの著者が書いているんですが、まぁ、実際、そんなにずば抜けて頭がいい人なんて、そんなにいないですよ。ただ、桁はずれた金持ちと言うのがいて、投資をうまくさせると、案外化けたりしますね。結局金かよと言う問題に達するのかってことですが、今の東大も、入っている坊ちゃん達は、いかに、親に金をかけてもらったかの集大成。
だけれど、入ってから自力で頑張ろうと思うときに気がつくようなんですよ。自分に遭う遭わないを考えないで入った事に。だから、その後、二年次で、学科に振り分けられていく時、自分の好みの学科には入れなかった人結構いたり、入って伸び悩んだりする人結構多かったりします。それでも、日本の東京大学って、世界から見たら25位なんですよ。
ただ、米国製のエリートは、リアリストで、結局世の中金で回るもんだと言うことがわかっている。だから、金儲けに対して、一抹も恥じらいがなく、日本のように金を儲ける事をドンドン行おうとすると叩かれる風潮にはいないんですね。まぁ、この本の冒頭にあるのですが、日本はエリートが出てくるのを時の運として見守っていることがあります。ですけれど、戦後なんて、結構いい加減だったと思いますよ。
楚々として、一抹の恥もないような感じで、日本人が居りますけれどね。
そんなに、綺麗事言っているから、トップが「薄すぎる河童のお皿」のような人で固める癖を日本が持つんですよ。トップに、実力も権力もコネもない人がなって、どう世界と相手していくつもりなんですかね。それこそ、原発で右往左往した首相、原発で寝込んじまった東電社長、こういう人にトップを任せていくことのほうが、問題だとは思いますが、これもひとつの世相なんでしょうね。民主に入れて、今になって、入れた自分を恥じる人もいますが、自民だって同じだったと思いますけれどね。
どの道、トップを作ってきたのは、国民の世論。これに間違いはないんですから。
面白い本でしたよ。年末のひと時にお勧めします。
朋