
昔、エリア88というマンガの中で(確かグレッグのセリフだったと記憶してますが)「戦争は経済のぶつかり合いだ。貧乏人は負ける」というようなセリフがありました。
ということで戦時はもちろん、平時の防衛においてはより重要な経済についてのシロウト談義です。
先頃、日銀当座預金への一部マイナス金利適用が発表されました。
これに関して黒田日銀総裁は「量的緩和が限界に達したわけではない。」と言ってましたが、
2月19日の「虎ノ門ニュース8時入り」の中で須田のオジキは「ウソです」と、事細かに解説してますた。
その内容について知りたい方はYouTube等で番組の動画を観ていただくとして、結論的な事を言えば
銀行は収益の悪化を防ぐためにATM手数料やら送金手数料などを値上げする公算が強いし、その他もし貸し倒れ引き当て金を圧縮しなければならないような銀行があれば、その銀行はリスクがある貸し付けがやりにくくなる、つまり融資にブレーキがかかる恐れがある、というような話でした。
デフレ脱却が叶わぬうちに円がジワジワ上がってきた。
しかしもはや量的緩和は限界に来ている。
追い詰められた黒田総裁は様々な問題点を承知の上で円安誘導を目的にマイナス金利を導入した、という事のようです。
なんでマイナス金利だと円安誘導になるのかというと
マイナス金利政策は物価上昇の期待を生むんだそうです。
そして物価高の国の通貨は安くなるんだそうで。
まあ、要するに金融業界の思惑・期待で円安に
なったらイイナー的な?
そんな感じでしょうか。
そんなウマく行くかなー。
「トトメス5世」によれば超低金利国の通貨は一瞬安くなっても長期的には必ず高くなるそうです。
つまり低金利国=信用が高い国でお金を借りて高金利国(ここにお金を貸すとたくさん利子が付く)=信用が低い国に貸し付ける業者がいる。
高金利国は外資が入って好景気になり通貨が高くなる=相対的に低金利国の通貨安くなる。
しかし高金利国=信用が低い国=土人国なのでやがて破綻→土人通貨暴落。
かくして低金利国=信用が高い先進国の通貨が再び高騰。
この繰り返しだそうな。
ただひとつの正しい事をやらない、あるいはやりたくないためにゴチャゴチャ小難しい策を弄した挙げ句、結局ずっと不況のまま次の円高フェーズを迎えてしまうんでは…?
景気浮揚のためには個人消費拡大。
それには消費税廃止と大規模財政出動しかないと思うんですが。










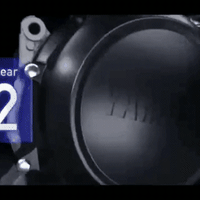
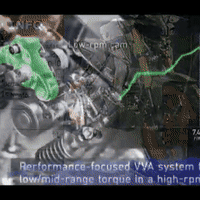
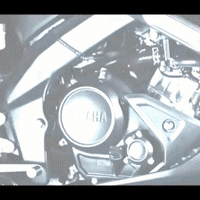




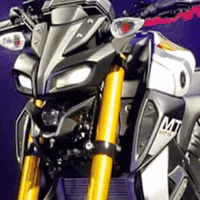

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます