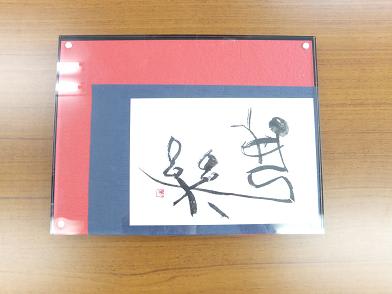安部さんの作品
昨日の続き、こちら↑は軸ではなく、モビール。
「茶煎穀雨春」
詩写梅花月 詩は梅花の月に写し 詩を写す(書く)なら梅花の月(が良よろし)
茶煎谷雨春 茶は穀雨の春に煎る 茶を煎る(煎れる)なら穀雨の春(が良ろし)
より。
前回、一字づつ書いてそれを軸にとの構想でしたが、
揺れるモビールとは、新鮮で思わず、わぉ~!と感激
小さい洗濯バサミのようなクリップで留めてます。
どこかに鈴とかつけるといいかも~と、話していましたが
鈴じゃ相当風が吹かないと鳴らないかも~ですね。
ということで、ウィンドベルウは?と思ったけど、これも難しそう。
 ←クリックで拡大
←クリックで拡大
音はなくても、春風にゆらゆらと揺れる作品、楽しいです
そしてUさんは、靴が入っていた箱に枝をアレンジした作品。
作品は半紙1/2に「映杏映桃山路中」。

作品は四隅をゴムでとめているので、入れ替え可能だそうです。
今は3人しかいない教室なのに、皆さまモノづくりがお好きな方ばかりで
それぞれに工夫とアイデアを凝らした、思いもよらぬ発想に触れ、
私も刺激を頂いています。
まずは「創る」楽しさを実感、共感していけたらと。
そして、ちょっとづつ完成度も上げていけたらと思っています。
 いつでもお仲間募集中です
いつでもお仲間募集中です 
東京の小田急線・横浜線町田駅より徒歩15分程の会場で、
第1・3木曜日の午後1時半~4時頃までやっています。
お問合せ・見学も大歓迎です。お気軽にどうぞ~
Mail: one-shoart★mail.goo.ne.jp ★を@に変えてください。
こちらもどうぞ ⇒ 心の免疫力~書とことばから
⇒ 心の免疫力~書とことばから
昨日の続き、こちら↑は軸ではなく、モビール。
「茶煎穀雨春」
詩写梅花月 詩は梅花の月に写し 詩を写す(書く)なら梅花の月(が良よろし)
茶煎谷雨春 茶は穀雨の春に煎る 茶を煎る(煎れる)なら穀雨の春(が良ろし)
より。
前回、一字づつ書いてそれを軸にとの構想でしたが、
揺れるモビールとは、新鮮で思わず、わぉ~!と感激

小さい洗濯バサミのようなクリップで留めてます。
どこかに鈴とかつけるといいかも~と、話していましたが
鈴じゃ相当風が吹かないと鳴らないかも~ですね。
ということで、ウィンドベルウは?と思ったけど、これも難しそう。
 ←クリックで拡大
←クリックで拡大音はなくても、春風にゆらゆらと揺れる作品、楽しいです

そしてUさんは、靴が入っていた箱に枝をアレンジした作品。
作品は半紙1/2に「映杏映桃山路中」。

作品は四隅をゴムでとめているので、入れ替え可能だそうです。
今は3人しかいない教室なのに、皆さまモノづくりがお好きな方ばかりで
それぞれに工夫とアイデアを凝らした、思いもよらぬ発想に触れ、
私も刺激を頂いています。
まずは「創る」楽しさを実感、共感していけたらと。
そして、ちょっとづつ完成度も上げていけたらと思っています。
 いつでもお仲間募集中です
いつでもお仲間募集中です 
東京の小田急線・横浜線町田駅より徒歩15分程の会場で、
第1・3木曜日の午後1時半~4時頃までやっています。
お問合せ・見学も大歓迎です。お気軽にどうぞ~

Mail: one-shoart★mail.goo.ne.jp ★を@に変えてください。
こちらもどうぞ
 ⇒ 心の免疫力~書とことばから
⇒ 心の免疫力~書とことばから













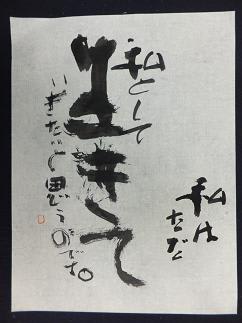














 すみませんです
すみませんです


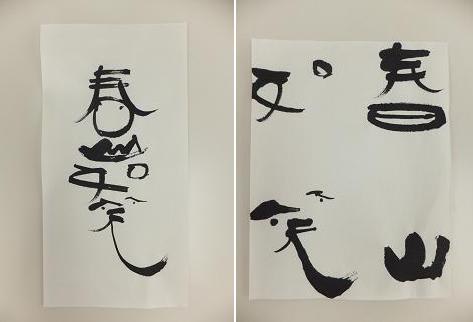










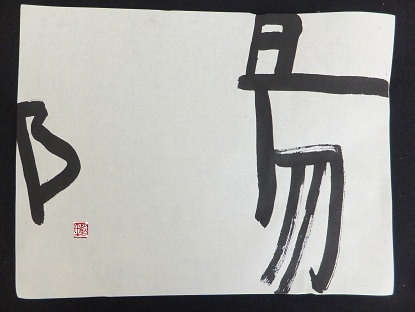



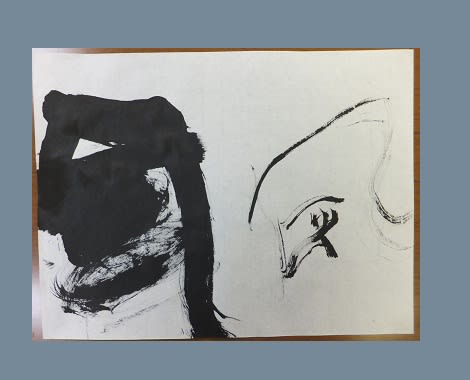
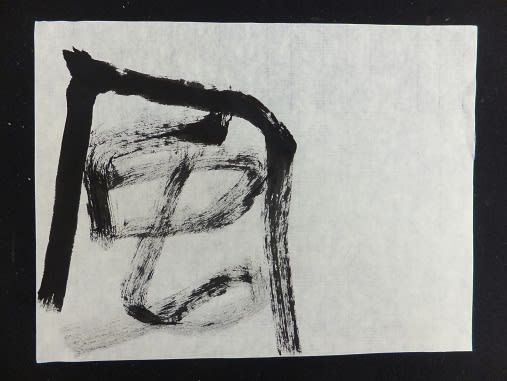
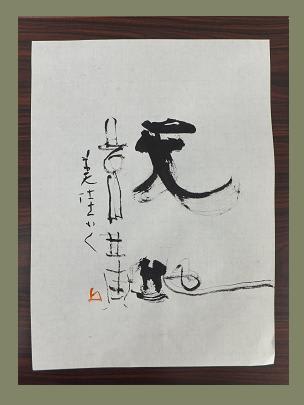

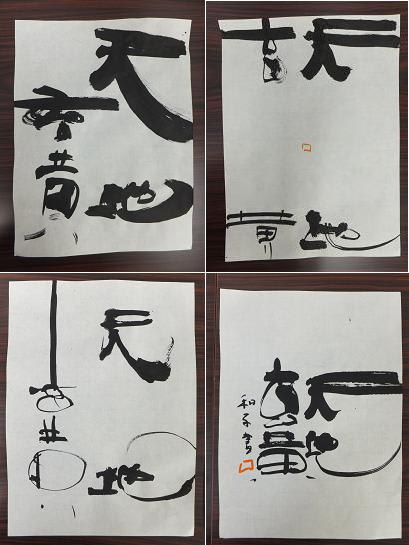
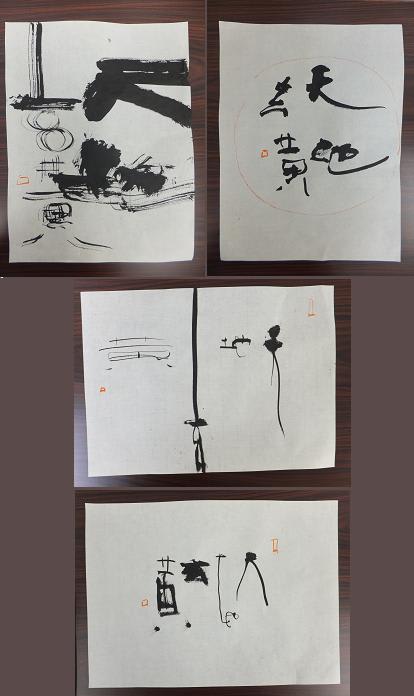
 講師ブログはこちら→
講師ブログはこちら→