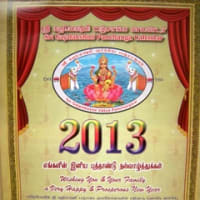同時並行でいくつかの仕事をしながら、と言うよりしてもらいながらお客さんの相手もし、どうにか夫々が順調に片付く。そしてお客さんも予定より1つ前の便に乗れそうと言うことで喜んで帰っていただけた。来週の水曜日に再開するとしても、今回同様うまく行くだろうと予想する。
"来客あり"で始まった今回の仕事はかなり上手く行った。仕事が予定通り進んだ意外に仕様変更がオフィシャルに承認されたことが大きい。承認依頼した項目のほとんどが認められたことで量産がかなり楽になったはずだ。検査できるかできないかスレスレかそれ以下が書かれていた仕様のままではツール作成も生産も検査も全部が苦労してしまう。苦労だけならまだマシだが、実際にはどちらでも良いような事で損を出すことになる。だからこうした初期の仕様の審査はかなり重要なのだ。
重要にも関わらず、それを仕事にする人は少ない。仕様に向かって物作りに励む人はいるが、ほとんど徒労に終わるのが関の山。後で品質保証チームに交渉のための無駄な労力を使わせるだけとなる。お客さん側も、工場が技術と折衝しなければならなかったり社内承認が必要だったりとつまらない労力を使わせてしまう。
そうした意味も含めて明日から3連休は気楽に休めそうだ。
会社はどう言うわけか組織図を描くものだ。
ある程度の規模、数人レベルよりちょっと大きくなっただけでも組織図と言うのは描かれる。ほとんどの場合は樹形図のようなものになっている。一番上に社長がいてその下に管理職....と枝分かれしていってだんだんと幅が広くなるあれだ。ちなみにGoogle画像検索で"組織図"と入れるとそれが山ほど出てくる。
なぜこんな事が気になっているかと言うと、今の仕事場でもそうした組織図と言うのがかなり頻繁に描き変えられるからだ。ただ描き変えられるだけなら気になる事もないが、それが一体何のためにそうしているのか理解し難い感じがしてもいると言う事だ。はっきり言って、それを描き変えるだけの労力に対して見返りが少ないのではないかと思っている。描き変える事が絶対に無意味と言うのではなく、効果的にそれができる会社や場合もあるだろうが、そうでない場合もあると言う意味で。
ところで何故、組織図は樹形図なのだろう?
組織が命令系統に従って出来ていると言う発想から来るのではないかとは普通に想像できる。描く立場からすればそれも尤もだ。けれども実際にそこで起こっている事をよく見てみれば、この樹形図でできた組織図がそこに含まれる小さな個別の組織と組織、人と人または仕事と仕事を分断しているようでもある。あっちの仕事は俺の仕事じゃないから知らないよ、とか、または、俺は誰々の命令でしか動かないよと。
と言うわけで、こうした当たり前に思っているものも見直してみたらどうなんだろうか。
例えば製造業だった場合、どの組織も人も製造の支援をしているわけだから中心に製造部門があってその周りを連携して支えているその他部門が取り囲む、円グラフ状の組織図にしてみるのも良いかもしれない。そうすれば全員がひとつの方向に動いているのが意識できるかもしれない。
最新の画像もっと見る
最近の「3年目に突入マレーシア」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
- 日本でニャー2025(51)
- 日本でニャー2024(344)
- 猫の治療(34)
- 猫の引越(17)
- 癌になる(25)
- 日本でニャー2023(333)
- 日本でニャー2022(98)
- マレーシアでニャー2022(244)
- マレーシアでニャー2021(355)
- マレーシアでニャー2020(277)
- マレーシアでニャー2019(280)
- マレーシアでニャー2018(238)
- マレーシアでニャー2017(241)
- マレーシアでニャー(321)
- 長いようで短い5年目マレーシア(5)
- どうにか4年目マレーシア(157)
- 3年目に突入マレーシア(358)
- 2年目のマレーシア(428)
- まさか、マレーシア!(409)
- 英語やるぞ!(140)
- いい歳して大学へ(13)
- 台湾-非観光的(78)
- 備忘録バリとインドネシア(24)
- Vespa? Yes, but LML !(218)
- カンガルーじゃないKangoo(108)
- Photo Photo(117)
- 日本脱出(140)
- 美食満腹(104)
- 映画って !(292)
- いろいろ雑記帖(394)
- これってスゴイ!(92)
- Puppy で Go!(20)
- ABCのAはArduinoのA(68)
バックナンバー
人気記事