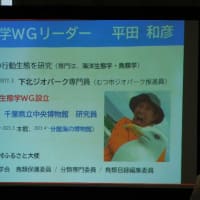第10回日本ジオパーク全国大会 (2019おおいた大会) 参加報告
(各写真はクリックすると拡大されます.本文に戻るときはブラウザの戻るボタンを使用してください)
標記大会に参加させていただきましたので,概略について報告します.本大会期間は10月31日~11月5日ですが私は開会式前日の11月1日(金)午前のジェット船にて大島を出港し11月2日からの公式行事および阿蘇GPのポストジオツアーに参加した後6日(水)に大島に帰着しました.
11月2日 開会式の行われた大分市のiichiko総合文化センターは近代的な設備を備えた巨大な複合施設です.35年ほど前に当地に出張したおりに地元で耳にしたお話ですが,大分県を代表する焼酎である「いいちこ」は,当時ほぼ全量が県外出荷されるため県内では入手が難しいということで,その人気の高さに驚くとともに,県外出荷を輸出ととらえる考え方をとても新鮮に感じたものです.現在,市民会館の冠スポンサーとなって財政に貢献しているのも,むべなるかなと感じました.
iichiko総合文化センター

ロビー展示

セレモニー会場

開会セレモニー,講演と一連の行事の中で米田JGN理事長 (糸魚川市長)の挨拶にあった「ジオパークはふるさとに愛着を持つことが目的」 は地学的な興味に向かいがちな運動の本質を思い返させる言葉でした.中田日本GP委員長 (防災科学技術研究所火山研究センター長)からは地球温暖化により世界的に巨大台風,水害が増加しているが,危険が切迫しているのに行動 (逃げる) ができない事例がある.南米コロンビアのネバド・デル・ルイス火山噴火では氷河が溶け流れ出した泥流で25000人が亡くなった.このような事例はジオの知識があれば防げた災害であり,コロンビアではGP設置の動きがあるとの報告がありました.
尾池 元日本GP委員長(元京大総長)の第10回大会記念講演は地球規模の地学的考察から俳句が生まれた理由まで多岐に渡るお話でしたが,印象的だったのは「活断層運動が平野を生み出した,したがって大地震は大都市の直下で起こる」というフレーズで,地学とは地球と人間の営みの両方を考える学問であると感じました.また注目すべき発言として南海トラフ地震について過去の発生間隔等のデータから,おそらく2030年~2040年,季節は12月前後が発生時期であろうと各種図表を示して解説してくださいました.現在の政府の見解では向こう30年以内に80%の確率で発生するとされているので,かなり踏み込んだ発信です.この情報の載った本も執筆されているようですが,これは尾池先生が多くの役職からある程度身を引いたお立場だからこそできる具体的発言ではなかろうかと拝察しました.
「ブラタモリ」の相部チーフプロデューサーによる基調講演と氏を混じえたパネルディスカッションでは,GPガイド活動に係る多くのノウハウが語られました.強く印象に残った示唆は,「その風景(地形)から生まれるストーリーを語ること」,と「伝えすぎてはいけない(伝えすぎると伝わらない)」ということで,どちらも次のガイド機会にすぐ応用してみたくなる考え方でした.
交流会では各地のGP関係者と情報交換を兼ねた歓談を重ねましたが,今回名刺交換した方は21名でした.事務局と現役ガイドがほとんどで,どのGPの方も話好きであることと,地元GPについて語れる多くの引き出しを持っているのがこの会の参加者の特徴です.交流会はこちらも勉強せねばと思わせるモチベーションアップの機会に溢れています.
パネルディスカッション
「伝える」ということ
~ジオパークの「Wa(わ)」を広げるために~

交流会

3日午前は香港世界GP統括責任者のヨン・カミン氏の講演を聴講し,午後はジオサイトの保全に関する分科会に出席しました.ヨン氏のお話は逐次通訳を介しての講演でやや聞き取りにくかったものの,要約すると香港の失われて行くかつての生活の記憶を土地の方々(古老?) から聞き出し記録するオーラルヒストリー活動によって地域の住民が誇りを持つとともにGP活動に協働していく事例を紹介していました.
保全分科会では
・銚子市の沖合に設置が計画されている洋上風力発電施設の景観問題
・南紀熊野の保全整備にかかる事例紹介
・室戸高校の「ジオパーク学」を通しての生徒たちの活動と学び
・糸魚川GPの保全の取り組み
の4事例の発表と意見交換が行われました.発言を求められたので特別保護地区である裏砂漠への自動車の侵入,およびサンキライなどの採集実態と入会権(いりあいけん)について感じていることを話しました.
保全分科会


4日午前はポスターセッションで全国のGPが持ち寄り掲示した様々な事例紹介のポスター見学と各地方別に設置されたパビリオン(テント小屋)の体験区ブース巡りをしました.ポスター発表では毎回各地のGPから派遣された学生さんの姿が見られます.このことはGP活動の将来にとって心強く思うとともに,大島でも今年二名の女子高校生認定ガイドが誕生したことを思い起こしました.大島からもジオ発表をたずさえた生徒・学生さんが大会に参加できることを強く望みます.
ポスターセッション

八戸水産高校から参加した川端さんの研究発表
手作りの紙芝居形式で土器と漆に関するお話をしてくれました.

関東地方パビリオン内部の様子

午後からは閉会式出席後,お隣県のGPである阿蘇カルデラ周辺をめぐるポストジオツアーに参加しました.私は年間20回ほど山頂口ジオパーク展で定点ガイドをしています.その際三原山を語るときにカルデラの形成過程に触れる訳ですが日本第二のカルデラ面積を持ち,ほぼすべての日本人がその山名を知っている阿蘇山のカルデラに触れないわけにはいきません.そこで実際にカルデラを見,触れることのできるチャンスであるこのツアーを選びました.
中央構造線という巨大な割れ目の上で誕生し25万年前から4回に及ぶ大噴火を起こし,とりわけAso4と呼ばれる9万年前の破局的噴火では大島が4つすっぽり入る大カルデラが作られました.このときの火山灰は偏西風に乗って北海道まで運ばれ15cmも積もったそうです.カルデラ面積こそ屈斜路カルデラにわずかに及びませんが,そこに居住する人口は約5万人.街区・農地には縦横に道路がはしり鉄路まで敷かれている世界的にも稀有な有り様をもって日本一のカルデラと称しているそうです.カルデラ内からは全周に壁のような外輪山がどこからでも見られ,漫画「進撃の巨人」の街のようで島育ちの身は一瞬閉塞感におそわれます.この風景に既視感を感じ,思い起こすと甲府盆地を初めて訪れた時にこれとよく似た感じを受けたのでした.
大観峰からのカルデラの眺めと噴煙を上げる中岳.

今回のガイドの皆さん.右端は若女将の北里さん.

大火砕流に覆われた外輪山の外側は広大な台地が広がりススキを主体とする大草原となっています.本来なら植生が進むにつれ森林化するはずですが,毎年定期的に野焼きを行い景観を維持しているそうです.押戸石ジオサイトをガイドしていただいたのは生業が旅館の若女将だという北里さん.彼女によると阿蘇GPの登録ガイド数は約80人,実働は30人ほどでほぼ手一杯の活動状況だそうです.複数ある中央火口丘の一つである中岳は活発に活動中で現在レベル2だそうです.盛んに噴煙を上げている姿は子供の頃見ていた三原山を思い出します.しかしその規模は文字通り月と素盆で長径25kmに及ぶ大カルデラは長くても4kmほどの三原山とは距離感が全く異なり,その広大さに圧倒されます.
この景観に対する三原山のアドバンテージは何があるのかと考えてみました.コンパクトで典型的なカルデラ火山である三原山は短時間で山頂までアクセスでき,火孔の観察やカルデラ壁に沿って周回できるなど直に触れることができるため,生きている地球の鼓動を気軽に感じる事ができる.しかも首都に近く多くの人々が容易に訪れることができるため地学の研究者たちの揺り籠となっている.短いスパンで噴火を繰り返し人生で二回以上の噴火を体験する可能性も期待できるため火山研究にとって欠かせない噴火の実態を観察する機会が多い.等々かなり負け惜しみ的になりますが絞り出してみました.
今回の大会参加はGP活動をするにあたって多くの感動と示唆を与えてくれました.近々に迫る伊豆大島で開催されるJGN関東大会にあたっては,参加者にその成果を盛り込んだおもてなしができれば良いなと思っています.
伊豆大島ジオパーク研究会 田附克弘