女の園
吉野 光彦
女の園、といっても、阿部知二原作の、古い映画のことではありません。
……大学のようなところに勤めはじめて、もう20数年になる。
30代の前半、さる女子大にスカウトされて、いきなり専任講師になった。
春、4月。最初の授業が、4年生のゼミナールであった。日本近代文学の卒業論文を書く学生たちである。私のことは、「気鋭の、川端文学の研究者」と学生たちに紹介してあるらしかった。
午後からの授業である。牢獄のような暗い廊下を歩いて、その室番号のしるされた演習室の前に立った。廊下側に窓がないから、教室の気配はわからない。ただドアに小さなのぞき窓があるので、ちょっと背伸びして中をうかがうと、とりどりの服装をした妙齢の女性たちが20人ばかり、おしゃべりをしている最中であった。
そこで小さくひとつ呼吸して、さっとドアをあけた。
キャーッ!
私の姿を見た彼女たちは、いっせいに、声をかぎりに叫んだ。
悲鳴とも、矯声ともつかぬ声に、小さな演習室はつつまれた。
それはあたかも、孤島に群れたオットセイたちが、いっせいに、海にむかって咆哮しているような光景だった。
それはそうだろう。「気鋭の」、つまり若い、「川端の」とくれば、読んでいなくとも「雪国」の島村のような、長身で、ちょっとニヒルな男を想像していたにちがいない。
ところが現れたのが、まるまるとした、まだ学生のような、小さな男だったのだから、叫ぶのも無理はない。
その叫びは、落胆、絶望、悲嘆、諦念、それにほんのわずかの興味の入った、心からの叫びであったにちがいない。
だが私は、見かけによらず、度胸がいいのである。
ころあいを見て、しずかに声をだした。
「君たちは、井上陽水を知っているか」
「知ってるうー」
と、いっせいに答えた。世に出てから数年後、陽水のひとつの絶頂期であった。
「では、『夢の中へ』を知ってるね?」
「知ってるうー」
おのおの机にしがみついて、肉体的には十分に成熟した女性たちが、しかし声音だけは高校生とちっとも変わらずに、足踏みしながら叫ぶのである。
「じゃあ、聞くが……」
と、音調を変えて私はたずねた。
「この曲の、詩のテーマは、わかるかい?」
彼女たちは、しんと静まった。
いちばん前の左端にすわっている、瞳のきらきらする女の子を指差した。
彼女は、つらそうに、ゆっくり首を左右にふって、「わかりません」と、悔しそうにいった。
後ろの方に、瞳の大きい、大柄ですらりとした、明らかにグループのボスと思われる女性がいた。女優にしたいような、きわだった容姿である。
私は、先輩から教えられていた法則を無視して、彼女を指名し、
「あなたは、どうですか? 『探しもの』 つて、何のことですか」 とたずねた。
彼女はちょっと首をかしげ、それからまっすぐ私を見据えながらいった。
「先生は、どう解釈されるんですか?」
互いの視線の先が火花を散らした。うーむ、できる! ここで負けたら、この学校で、私の将来はない。
私はおもむろにいった。
「では、ぼくの考えをいいましょう。
陽水の作品世界は多くの場合、日常性と非日常性をテーマとしています。『夢の中へ』は、その基本的な構造がよく現れた作品といえるでしょう」
軽快なリズムと、ふしぎなメロディーを併せもつこの作品は、初期陽水の代表作だ。ずっとのち、斎藤由貴が歌ってふたたびヒットしたように、名曲のもつ特性をすべて含んでいる。しかし、その詩は、女学生風情(ふぜい)に理解できるようなものではない。
探しものは何ですか
見つけにくいものですか
カバンの中も机の中も
探したけれど見つからないのに
まだまだ探す気ですか
それよりぼくと踊りませんか
夢の中へ 夢の中へ
行ってみたいと思いませんか ウフッフー、ウーウ
私はこの詩を、ていねいに読み説いてみせた。
現代日本の中産階級の人々を覆っている意識――よい学校に入って、よい成績で出て、よい会社に就職して、よい異性と結婚して……
つまり、いつも、よりよい生活をめざしてあくせくしている人々の心に、この曲は呼びかけているのだ。「あなたは、何を探しているのか。それよりも、さあ、夢の世界へ入ってゆこう。現実から逃れて、夢のような私の官能の世界へ入ってゆこうじゃないか」と誘っている。日常性からの脱却、官能的世界への誘惑、それがこの曲のテーマです。
陽水は、日本社会の構造をよく知っている。この曲の2番にある「探すのをやめたとき/見つかることもよくある話で」は、まことに鋭い観察である。じつは私たちのほんとうの幸福は、意外なところに、すぐ足もとにころがっているのに(あの、「青い鳥」のチルチルとミチルの物語のように)人々はそれに気づかない。
まあ、そんな意味のことを、時折わざとむずかしい研究用語をもちいて解釈してみせたのである。
……教室の空気が変わったことに私は気づいていた。この先生、見かけによらず、やるじゃない、といった感じである。そこで私はいった。
「川端康成を勉強してくると、こういう詩が、しぜんにわかるようになる。逆にいうと、こういう詩を理解できないようでは、川端文学はわからない。それにしても、陽水のコンサートはいいね」
「先生、コンサートに行ったことがあるんですか?」
「もちろん。近くに来たときは、かならず行くよ」
そして私は、はじめて陽水のコンサートに行ったとき、どのように苦心して前から3番めの理想的な席のチケットを手に入れたかを話してみせた。それから陽水のコンサートの模様を、実況放送のように熱く語った。
その日から、私は学生たちのアイドルになった。学内のどこかを歩いていると、「吉野せんせーい!」と、見知らぬ学生から声をかけられるようになった。
「先生、ゼミ・コンパ、しましょう。先生の歓迎コンパよ」
数人の学生が私の研究室のドアをノックして、そう切り出したのは、翌週の月曜日であった。
数名の学生のうしろに、女優のような、例の学生が立って、こちらを凝視していた。彼女は実際、広島市内のアマチュア劇団で活躍する、かなりの有名人であることが、まもなく判明した。
週末の夕暮れ、指定されたデパート前に行けば、彼女たちが手をひくように連れていってくれたのは、広島の繁華街、流川(ながれかわ)である。
酒場といえば、私は居酒屋かバーか、スナックのような、つまり、むさくるしい貧乏な男たちが出入りするようなところしか知らない。
団体で、店の一部を借り切って、そこでパーティーをする、などということから、これまで無縁の世界に住んできた。
学生たちはよく飲み、かつ喰らう。マイクの前で平気で歌う。梓(あずさ)みちよの「乃木坂あたりで……」という曲や、清水健太郎の「失恋レストラン」が流行している時代であった。
私はなかば茫然と、彼女たちの振る舞いを見て、勧められるままに飲み、食べるだけである。彼らはまた、いろいろな店をよく知っているのであった。
かくて私は、若者たちの集う飲み屋さん、ディスコ、ロック・コンサートなど、新しい大衆文化の先端を、彼女たちから学んでいった。どっちが先生だかわからない。
現代の大学を象徴するのが、ゼミナールであろう。
私の場合は、専攻が近代文学だから所属学生が多いので、演習室で行うのが常であったが、少人数のゼミでは、教師の研究室で行うことがある。
週に1コマのその時間になると、学生たちが茶菓を持ち込み、勝手に湯をわかし、珈琲やら紅茶やら、てんでに入れてくる。教師は人形のようにじっとしていて、必要な時だけ、口をひらけばいいのである。
女子学生たちは、すでに中年女性のごとく、世話をやくのが好きであり、かつ上手である。彼女たちに取り巻かれたら、むかしの王侯貴族のように、じっと動かず、なされるがままに身をまかせているのが、尊敬される生き方である。
かくて教師は腑抜けになり、身の回りのことはすべて他人まかせが当たり前、という異形の人格が形成されてゆく。
……その学校に、私より何年かあとに、40前後の、英文学の教師が転じてきた。工業大学(つまり男子学生ばかりの学校)に勤めていたということで、19世紀英国の、あまりパッとしない小詩人を専攻している彼は、この世の中に、面白いことなぞあるものか、というような陰鬱きわまりない表情をして、私の隣の研究室に入った。
4階の研究室の窓から飛び降りるのではないかと心配したくなるほど、世界中の苦悩をひとりで背負っているような、暗澹(あんたん)たる顔つきをしていて、その顔を見るだけでこちらも憂鬱になるような男であった。
当然ながら、彼の専攻からしても、ゼミの学生は数えるほどである。
しかしやがて、彼の研究室で行われる小さなゼミナールの、学生たちの笑い声が壁越しに聞こえてくるようになった。
1年後、彼の表情は生き生きとしてきた。顔を合わせると「おはようございまーす!」と、明るい表情で声をかけてくるようになった。
さらにもう1年が過ぎて、3月の卒業式の日の夕べ、謝恩会の会場となったホテルに、彼が赤い蝶ネクタイをつけて現れたときには、同僚も学生たちも、一同ことばを失った。
「俺たちは、芸能人じゃあないんだから」という言葉も浮かんだが、驚きを通り越して、人間の不思議に私は胸をつかれた。なるほど、人生は、生きてみなければわからない、と私は思った。
……あとにも先にも、あれほど大勢の女性たちにもてはやされたことはない。
それは私の、黄金の30代の数年間の出来事であった。
『文芸・日女道』380号(2000、1)












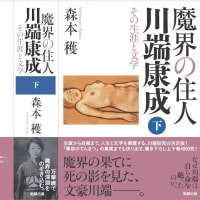
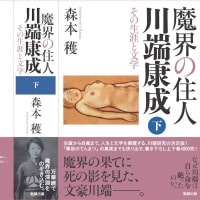

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます