ライアンの娘
むかし読んだ司馬遼太郎さんの「愛蘭土(アイルランド)紀行」に、その苛酷な自然を描いた文章があった。
たとえばアラン島は、一枚の巨大な岩盤から出来ている島である。島人は、つよい海風が吹き運んでくる土や塵を両掌ですくいとり、岩盤上の畑に置きつづけて、少しでも畑の上をふやそうとする。
また、男たちは岩盤をくだいて石くれをつくる。石垣をきずいて、せっかくの畑の上が吹き飛ばされないようにするのである。
さて、これまた海風がはこんできた海藻を若妻が背負い、岩盤を上ってゆく場面がある。わずかな土壌を助ける肥料とするためである。
アイルランドとは、およそこのような国であると、私には強烈に印象されている。
私が映画「ライアンの娘」を見だのは、多分それより以前であったが、画面を一瞥しただけで、この国のおかれた厳しい自然条件は納得された。
題名の「ライアンの娘」というのは、ライアン家の娘、という意味で、ライアンは父親の名前である。もっとも、ライアン家といっても、立派な資産のある家ではない。アイルランドの寒村で、しがない居酒屋をいとなむ家である。
ライアンの娘ロージーは、しかし珍しいことに、この島で教育を受けた。教育といっても、村に赴任してきた教師から、聖書やその他についてわずかな知識を吸収したに過ぎなかったのだが、娘の心に火がついた。
彼女はこの教師を、一人の尊敬する男として愛し、結婚したいと願ったのである。
教師は切々と、自分はそんなに立派な学殖があるわけでもなく、精神も平凡な男で、要するにたいした男ではない、あなたは私の中に、何か別のものを夢想しているのだと説くが、彼女は耳をかさない。
――確かに私はバイロンやベートーヴェンを教えはしたが、私は彼らとは違う。私はただの田舎教師だ。
彼はまた、こうも言う。「生徒が教師に好意をもつのは、よくあることだ。心の惑いだよ。安物の鏡を、太陽と思いこむようなものだ。」
しかし彼女の心が変わることはなかった。
村人たちが参加して、質素な結婚式が行われる。
私はそれと知らずに映画館に入ったのだったが、この映画の監督は「アラビアのロレンス」「ドクトル・ジバゴ」を撮った名匠デヴィッド・リーンであった。名匠らしく、彼はこの骨太の作品でも、独特の工夫をこらした。
それは背景の音楽がすべてベートーヴェンの交響曲だということである。このことによってこの作品は、いっそう悲劇的で荘重な内容を獲得することができたのである。
教育を受けるということが、娘の中にひそんでいた夢想家の夢を花開かせるというのは、フローベルの「ボヴ″ァリー夫人」と同じ構造である。ライアンの娘は、人生の最初に出会った教師に、彼女のありあまる情熱を傾けたのである。
しかしやがて、当然ながら、彼女は平凡な生活に失望し、生活に倦(う)んでくる。夫は、村人だちより少しだけ知識のある、平凡な男に過ぎなかった。アイルランドの寒村そのものが、卑小で退屈な日々で成り立っている。教師の家も、それと変わりはなかった。
アイルランドという国が苛酷な状況に置かれているのは、自然だけではなかった。英国軍がこの島に侵攻して以来、この国は幾世紀にもわたって、その圧政に苦しんできたのである。
時は第一次世界大戦のさなか、英国がドイツ軍の猛攻に耐えているときであった。
その間隙をぬって首都ダブリンで叛乱が起こり、鎮圧されたのち、イギリスはいっそうこの国を警戒した。
村はずれの丘には要塞があり、そこに、村人たちを監視する英国軍が駐屯していた。
その要塞で指揮をとっているのは、学校を出たばかりの若い士官だった。彼は西部戦線の生き残りであろうか、酷薄な精神と、ひきずる足をもっていた。
この若い将校が、夕暮れの中、ほの赤い夕空を背景に、岩の上に立ちはだかる場面は圧巻だ。貴族的な容貌と、背筋をぴんと伸ばした英国将校。だが彼は、大きく足を引きずっているのである。
足を負傷している彼は、それだけにいっそう精神は厳しい。その彼がアイルランド人たちの憎悪の洗礼を受けるのがライアンの居酒屋だ。
警戒心もなくこの小さな居酒屋に入った彼は、狭い店内の村人たちから、憎悪のこもった言葉を浴びせられる。スノッブ!(俗物め!)が村人たちの合い言葉だ。
この将校と、ライアンの娘ロージーが出会ったのは、どういう経緯だったのか、今では思い出せない。
が、とにかくロージーは彼の内に何かを見出した。そして秘密の恋が始まった。
村人たちにとって英国人は、これ以上ない仇敵だ。ましてその長官である将校には、村人の憎悪が一身に集められている。
しかしロージーは彼の冷徹な意志の底に、心をふるわせる何かを見出したのだ。
二人の秘密の恋がはじまる。彼の駆る白馬に乗せられて、ふたりは遠い森の中へゆき、そこで激しい愛が燃え上がる。
アイルランドにも、こんな美しい緑があったのかと思わせるような、木立にかこまれた桃源郷のような塲。ふたりの愛は狂おしい。
どのくらいの期間がたったろう。この恋は村人たちの知るところとなり、父ライアンは村人たちから厳しい罵倒の言葉を浴びせられる。彼には返す言葉もない。ただ彼は、なぜ娘が、選(よ)りにも選(よ)って、敵国の長官と愛し合うようになったか、理解に苦しむばかりである。
娘は見せしめのために長い髪を切られ、囚人のようなざんぎり頭にされてしまう。
……そして、娘が村を出てゆく日がやってくる。
荷車に、わずかばかりの家財を積んで、彼女は石ころ道を、車を引いてとぼとぼと出てゆく。家々の窓から、冷たい蔑(さげす)みにみちた眼が、彼女の逐(お)われてゆく後ろ姿を、どこまでも見送っている。
そこに、観客を驚嘆させる事実が加わる。何と、彼女の荷車を後ろから押して、ともに村を出てゆくのは、あの教師なのである。
彼には罪はないはずだ。ただ妻を寝取られた男としてみっともなさに耐えれば、それでいいのである。しかし凡庸な教師は、愚かな妻と罪を分かち合うことを決意し、村人たちの視線の中、とぼとぼと石の多い道を、どこまでもたどって行く。
観客は、彼の内部にあった、或る崇高な精神に心うたれるのである。
それにしてもこの物語は、アイルランドの一地方の、それでも人間は生きてゆけるのか、と思えるほどに厳しい環境の中で進められてゆく。
ひとりの娘の内面の劇が、ベートーヴェンの交響曲と共に、大きなうねりをもってスクリーンにくり広げられてゆくのである。
そして最後に、村の老神父の言葉であったか、呪文のようなささやきが胸に残るのである。
夢を見るのは仕方がない。だが育ててはいかん。夢で身を滅ぼすぞ――。
『文芸・日女道』447号(2005年8月)
吉野 光彦
むかし読んだ司馬遼太郎さんの「愛蘭土(アイルランド)紀行」に、その苛酷な自然を描いた文章があった。
たとえばアラン島は、一枚の巨大な岩盤から出来ている島である。島人は、つよい海風が吹き運んでくる土や塵を両掌ですくいとり、岩盤上の畑に置きつづけて、少しでも畑の上をふやそうとする。
また、男たちは岩盤をくだいて石くれをつくる。石垣をきずいて、せっかくの畑の上が吹き飛ばされないようにするのである。
さて、これまた海風がはこんできた海藻を若妻が背負い、岩盤を上ってゆく場面がある。わずかな土壌を助ける肥料とするためである。
アイルランドとは、およそこのような国であると、私には強烈に印象されている。
私が映画「ライアンの娘」を見だのは、多分それより以前であったが、画面を一瞥しただけで、この国のおかれた厳しい自然条件は納得された。
題名の「ライアンの娘」というのは、ライアン家の娘、という意味で、ライアンは父親の名前である。もっとも、ライアン家といっても、立派な資産のある家ではない。アイルランドの寒村で、しがない居酒屋をいとなむ家である。
ライアンの娘ロージーは、しかし珍しいことに、この島で教育を受けた。教育といっても、村に赴任してきた教師から、聖書やその他についてわずかな知識を吸収したに過ぎなかったのだが、娘の心に火がついた。
彼女はこの教師を、一人の尊敬する男として愛し、結婚したいと願ったのである。
教師は切々と、自分はそんなに立派な学殖があるわけでもなく、精神も平凡な男で、要するにたいした男ではない、あなたは私の中に、何か別のものを夢想しているのだと説くが、彼女は耳をかさない。
――確かに私はバイロンやベートーヴェンを教えはしたが、私は彼らとは違う。私はただの田舎教師だ。
彼はまた、こうも言う。「生徒が教師に好意をもつのは、よくあることだ。心の惑いだよ。安物の鏡を、太陽と思いこむようなものだ。」
しかし彼女の心が変わることはなかった。
村人たちが参加して、質素な結婚式が行われる。
私はそれと知らずに映画館に入ったのだったが、この映画の監督は「アラビアのロレンス」「ドクトル・ジバゴ」を撮った名匠デヴィッド・リーンであった。名匠らしく、彼はこの骨太の作品でも、独特の工夫をこらした。
それは背景の音楽がすべてベートーヴェンの交響曲だということである。このことによってこの作品は、いっそう悲劇的で荘重な内容を獲得することができたのである。
教育を受けるということが、娘の中にひそんでいた夢想家の夢を花開かせるというのは、フローベルの「ボヴ″ァリー夫人」と同じ構造である。ライアンの娘は、人生の最初に出会った教師に、彼女のありあまる情熱を傾けたのである。
しかしやがて、当然ながら、彼女は平凡な生活に失望し、生活に倦(う)んでくる。夫は、村人だちより少しだけ知識のある、平凡な男に過ぎなかった。アイルランドの寒村そのものが、卑小で退屈な日々で成り立っている。教師の家も、それと変わりはなかった。
アイルランドという国が苛酷な状況に置かれているのは、自然だけではなかった。英国軍がこの島に侵攻して以来、この国は幾世紀にもわたって、その圧政に苦しんできたのである。
時は第一次世界大戦のさなか、英国がドイツ軍の猛攻に耐えているときであった。
その間隙をぬって首都ダブリンで叛乱が起こり、鎮圧されたのち、イギリスはいっそうこの国を警戒した。
村はずれの丘には要塞があり、そこに、村人たちを監視する英国軍が駐屯していた。
その要塞で指揮をとっているのは、学校を出たばかりの若い士官だった。彼は西部戦線の生き残りであろうか、酷薄な精神と、ひきずる足をもっていた。
この若い将校が、夕暮れの中、ほの赤い夕空を背景に、岩の上に立ちはだかる場面は圧巻だ。貴族的な容貌と、背筋をぴんと伸ばした英国将校。だが彼は、大きく足を引きずっているのである。
足を負傷している彼は、それだけにいっそう精神は厳しい。その彼がアイルランド人たちの憎悪の洗礼を受けるのがライアンの居酒屋だ。
警戒心もなくこの小さな居酒屋に入った彼は、狭い店内の村人たちから、憎悪のこもった言葉を浴びせられる。スノッブ!(俗物め!)が村人たちの合い言葉だ。
この将校と、ライアンの娘ロージーが出会ったのは、どういう経緯だったのか、今では思い出せない。
が、とにかくロージーは彼の内に何かを見出した。そして秘密の恋が始まった。
村人たちにとって英国人は、これ以上ない仇敵だ。ましてその長官である将校には、村人の憎悪が一身に集められている。
しかしロージーは彼の冷徹な意志の底に、心をふるわせる何かを見出したのだ。
二人の秘密の恋がはじまる。彼の駆る白馬に乗せられて、ふたりは遠い森の中へゆき、そこで激しい愛が燃え上がる。
アイルランドにも、こんな美しい緑があったのかと思わせるような、木立にかこまれた桃源郷のような塲。ふたりの愛は狂おしい。
どのくらいの期間がたったろう。この恋は村人たちの知るところとなり、父ライアンは村人たちから厳しい罵倒の言葉を浴びせられる。彼には返す言葉もない。ただ彼は、なぜ娘が、選(よ)りにも選(よ)って、敵国の長官と愛し合うようになったか、理解に苦しむばかりである。
娘は見せしめのために長い髪を切られ、囚人のようなざんぎり頭にされてしまう。
……そして、娘が村を出てゆく日がやってくる。
荷車に、わずかばかりの家財を積んで、彼女は石ころ道を、車を引いてとぼとぼと出てゆく。家々の窓から、冷たい蔑(さげす)みにみちた眼が、彼女の逐(お)われてゆく後ろ姿を、どこまでも見送っている。
そこに、観客を驚嘆させる事実が加わる。何と、彼女の荷車を後ろから押して、ともに村を出てゆくのは、あの教師なのである。
彼には罪はないはずだ。ただ妻を寝取られた男としてみっともなさに耐えれば、それでいいのである。しかし凡庸な教師は、愚かな妻と罪を分かち合うことを決意し、村人たちの視線の中、とぼとぼと石の多い道を、どこまでもたどって行く。
観客は、彼の内部にあった、或る崇高な精神に心うたれるのである。
それにしてもこの物語は、アイルランドの一地方の、それでも人間は生きてゆけるのか、と思えるほどに厳しい環境の中で進められてゆく。
ひとりの娘の内面の劇が、ベートーヴェンの交響曲と共に、大きなうねりをもってスクリーンにくり広げられてゆくのである。
そして最後に、村の老神父の言葉であったか、呪文のようなささやきが胸に残るのである。
夢を見るのは仕方がない。だが育ててはいかん。夢で身を滅ぼすぞ――。
『文芸・日女道』447号(2005年8月)












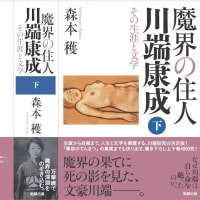
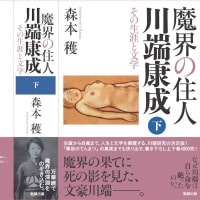

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます