川端康成の手紙 初恋 運命のひと 伊藤初代(3)
喪われた物語「篝火(かがりび)」
長良川のほとり
「篝火(かがりび)」(『新小説』1924・3・1)は、その発端を描いた作品である。
「私」は、朝倉(三明永無みあけ えいむ がモデル)とふたりで岐阜に来る。岐阜名産の雨傘と提灯を作る家の多い田舎町にある澄願寺に、みち子を訪ねる。
半月のうちに二度も、東京から岐阜のみち子を訪ねてくるのは、養父母の手前、穏やかではないので、名古屋方面に行く修学旅行のついでに寄るといつわって、手紙を書いての訪問だった。
みち子は、和尚が壁塗りをする手伝いをしていた。やがて「私」の前に着疲れた単衣(ひとえ)で坐っているみち子を見ながら、「私」はこの二十日ばかり空想してきたみち子と、現実のみち子の隔たりを感じて、自分の願望がどんなにみち子を苦しめているかを思って暗澹たる思いになる。自分の一途な恋情が、恋に未経験なみち子を懊悩させていることへの反省である。
しかし朝倉の機転で、みち子を寺から出させることに成功したふたりは、長良川の川向こうの宿に来る。そこで「私」が湯に入っているあいだに朝倉がみち子を口説いて「私」との結婚を承諾させる、という筋書きだった。
朝倉は、「私」の知らないうちに、みち子を口説いていた。「俊さんが君を望んでゐる。お前の身にとって、こんないいことはないと僕も思ふし、それに第一、非常に似合ひだ」と言ってくれたのである。
「朝倉さんから聞いてくれたか。」
さつと、みち子の顔の皮膚から命の色が消えた。と見る瞬間に、ほのぼのと血の帰るのが見えて、紅く染つた。
「ええ。」
煙草を銜(くは)へようとすると、琥珀(こはく)のパイプがかちかち歯に鳴る。
「それで君はどう思つてくれる。」
「わたくしはなんにも申し上げません。」
「え?」
「わたくしには、申し上げることなんぞございません。貰つていただければ、わたくしは幸福ですわ。」
幸福といふ言葉は、唐突な驚きで私の良心を飛び上らせた。
「幸福かどうかは……。」と私が言ひかかるのを、さつきから細く光る針金のやうにはきはき響いてゐるみち子の声が、鋭く切つた。
「いいえ、幸福ですわ。」
抑へられたやうに、私は黙つた。
みち子は、今の養父母が自分のうちからお嫁に出すと言っているから、「一旦私の籍を澄願寺へ移して、それから貰つて下されば、わたくしは嬉しいんですわ」と言う。これに対して「私」は、「私のやうな者と婚約してしまつてと、なぜだか、無鉄砲なみち子が可哀想でならない」と思うのである。
そして三人は宿の廊下から、長良川を下ってきた鵜飼いの船を印象深く見る。
「私は篝火をあかあかと抱いてゐる。焔の映つたみち子の顔をちらちら見てゐる。こんなに美しい顔はみち子の一生に二度とあるまい」と思う。――
「篝火」は、およそこのような作品であるが、「私」がみち子を痛ましく思ってならないでいる心がつよく全編を流れている。昨夜の汽車の中で見た女学生たちよりも、みち子が子供であることを思って胸を痛めたりする。
瀬古写真館と故郷・岩谷堂の父
1921(大正10)年10月8日、意外なほど簡単に、みち子は結婚を承諾した。それも、康成が直接口説いたのではなく、友人朝倉が初代を説いて、なかば強引に結婚を納得させたのである。このとき康成は数えで23歳、初代は16歳であった。「篝火」に書いてあるとおりである。
いったん初代を寺に帰した翌日の10月9日、3人は、婚約の記念に、岐阜の裁判所の前にある大きな写真館で、幾枚かの写真をとった。
このときのことを、康成は「南方の火」(第4次37巻本『川端康成全集』第2巻)の第4章に、以下のように書いている。
岐阜市の裁判所前の写真屋だつた。
「髪は?」と時雄が小声に言つた。弓子はひよいと彼を見上げて頬を染めると、子供の素直な軽さでぱたぱたと化粧室へ走つて行つた。 (中略)それを見ただけでも時雄は夢のやうに幸福だつた。微笑が温かくこみ上げてきた。(中略)
しかし男の前では恥かしくて化粧の真似も出来ないほんの小娘だつた。だから、初め時雄と一緒に行つた水澤といふ学生を加へて三人 で写す時には、彼女は海水帽を脱いだばかりのやうにほつれた髪だつた。それからもう一枚二人で写したのが、弓子の父に見せた写真だ つた。
弓子が化粧室を出てくると、写真師が生真面目に、
「どうぞそこへお二人でお並びになつて。」と白いベンチを指さしたが、時雄は弓子と並んで坐ることが出来なかつた。うしろに立つ た。彼の親指に弓子の帯が軽く触れた。その指の仄かな體温で彼は弓子を裸でだきしめたやうな温かさを感じた。
時雄は康成、水澤は三明、弓子が初代であることは、言うまでもない。このとき、三人で並んだ写真と、康成と初代と二人だけの、二枚の写真が撮影されたはずであるが、93年後の今日、三人の写真だけが残って、二人だけの写真は、すでにない。
ここに登場する写真館が瀬古写真館であることは、地元の人々によって、簡単に明らかになった。岐阜裁判所の向かいにある、当時も群を抜いた写真館であったからだ。
瀬古写真館は創業1875(明治9)年の、三層の塔をもつ、瀟洒な洋館の写真館だった。
このとき三人が一緒に写した写真は、後年、長谷川泉が三明永無を説いて譲ってもらい、世に出た。
しかし実は、瀬古写真館にも、原板が残っていた。
岐阜では、若き日の康成が恋人を求めて岐阜を訪れた事実を検証しようと、島秋夫、青木敏郎といった人たちが調査を進め、その結果、「篝火」に澄願寺と記されている寺――初代が養女として預けられていた寺が正しくは浄土宗の西方寺(岐阜市加納新本町)であること、などが明らかにされてきた。
わたくしは、三木秀生『篝火に誓った恋 川端康成が歩いた岐阜の町』(岐阜新聞社、2005・5・5)を入手して、そこに当時の瀬古写真館の写真のあることに驚いた。それがあまりにも見事な洋風建築であったからだ。
川西政明『新・日本文壇史』第三巻(岩波書店、2010・7・15)の第16章「川端康成の恋」には、この瀬古写真館が岐阜市今沢町、と明記されているので、現在も存続しているにちがいない。早速、104番で電話番号を訊ね、康成らの写真がそちらに存在するなら、譲ってほしいと店主夫人らしき方に懇願した。
数日後、現在の社長(正社員36名を擁し、名古屋、四日市にも事業所を持つ瀬古写真株式会社に成長していた)瀬古安明氏より、4葉の写真が恵送されてきた。
当時の写真館主、瀬古安太郎が撮影した3人の写真2葉のほかに、3人の署名を写した写真があった。
大正十年十月九日
於 瀬古写真館
三明永無 東大二年(23)
伊藤初代 十六才
川端康成 東大二年(23)
「篝火」に書かれた10月8日の翌9日に、確かに3人は、瀬古写真館で写真をとったのだ。
そして、康成と初代が二人で撮った写真は、今度、岩手県岩谷堂に住む、初代の父に結婚を承諾を得るために行く、いわば二人の愛の証拠写真として機能させる目的を秘めていたのである。
もっとも、このときの約束を、「婚約」と表現するのは、大げさすぎるかもしれない。康成がのちに「文学的自叙伝」に書いているように、「結婚の口約束」という表現が、真実にいちばん近いだろう。
なお、初代をめぐる岐阜の西方寺との関わり、西方寺の住職夫妻、あるいはカフェ・エランのマダムであった山田ますのその後などについては、早い時期に『図書新聞』に発表された三枝康高「川端康成の初恋」が詳しい。この文章は、山田ますのその後の人生についても教えてくれ、流転する人生の不思議をも示唆して味わい深い名文である。
――それはさておき、東京に帰ると、康成は早速、新居の準備をはじめた。といっても先立つものは金である。
菊池寛と康成のかかわりについては後述するが、まだ二、三度会ったばかりの先輩である。翻訳の仕事でも紹介してもらえれば、ぐらいの気持だった。
私の二十三歳の秋であつた。菊池氏は今の私より若い三十四 歳であつた。私は小石川中富坂の菊池氏の家を訪れて、二階の部屋に対坐するなり、娘を一人引き取ることになつたから、翻 訳の仕事でもあれば紹介してほしいと、突然頼んだ。菊池氏はうんと力強くうなづいて、引き取るつて、君が結婚するのか。ええ、結婚は今直ぐぢやないと、私が弁解めいたことを言ひ出さうとすると、だつて君、いつしよにゐるやうになれば結婚ぢ やないか。そして、その後に直ぐ続いた菊池氏の言葉は、僕は近く一年の予定で洋行する、留守中女房は国へ帰つて暮したい と言ふから、その間君にこの家を貸す、女の人と二人で住んでればよい、家賃は一年分僕が先払ひしておく、別に毎月君に五十円づつやる、一時に渡しといてもいいが、女房から月々送るやうにしといた方がいいだらう。それに君がもらふ学資の五十円くらゐを合せたら、たいてい二人で食へるだらう、君の小説は雑誌へ紹介するやうに芥川によく頼んでおいてやる、そんなことで僕がゐなくてもなんとかやつて行けるだらう、僕が帰つたらその時はまた考へてやる。私はあまりに夢のやうな話で、むしろ呆然と聞いてゐた。
だから、帰りの富坂は、足が地につかぬ喜びで走つて下りた。
二十三の私が十六の小娘と結婚したいと言ふのも非常識だつたが、菊池氏はただ娘の年と居所を聞いただけで、なんの批判も加へず、穿鑿 (せんさく)もしなかつた。
「文学的自叙伝」(『新潮』1934・5・1)の冒頭部分に描かれた告白である。ここにもあるように、伊藤初代と、恩人としての菊池寛は、康成の文学を成立せしめた二つの重要な要素である。
さて、 経済的な目処はついたが、次に康成が必要と考えたのは、初代の父親の承諾を得ることだった。
初代は、数え10歳のとき母を喪い、まもなく父と別れ、尋常小学校の3年を終えたあたりで学校をやめて上京している。
初代の父伊藤忠吉の故郷は、先述したように岩手県江刺郡岩谷堂(現、奥州市江刺町岩谷堂 いわやどう)である。
妻に死なれたあと、忠吉は幼いマキをつれて岩谷堂に帰り、岩谷堂小学校の使丁(用務員)になっていた。会津若松でもこの仕事をしていたこともあり、堅実実直な仕事ぶりであったという。
その父の承認をとって、晴れて結婚したいと康成は考えた。
友人たちも賛成した。友人のひとり鈴木彦次郎は同県盛岡市の名家の出身である。鈴木の先導で、康成をふくめた四人――三明永無、石濱金作――が岩谷堂をたずねることになった。
このとき彼らは東京帝国大学の学生であった。制服角帽のきちんとした身形(みなり)で父親に面会した方がよいだろうと三明が提唱し、それを実行した。
彼ら四人は、水沢の駅から約六キロの距離を、自動車で岩谷堂小学校に到着し、校長に面会を求めた。それから使丁の伊藤忠吉を呼んでもらった。
おずおずと現れた父親に、彼らは、代わる代わる、初代が自身の意志で康成と婚約したと説明し、その証拠として、岐阜で撮影した写真を見せた。
父親は、写真の初代を見て涙をこぼした。
そして、本人がそう希望したなら、それでよい、と小さな声で答えた。
四人は、盛岡の鈴木彦次郎の家に一泊し、翌日、東京に凱旋した。
喪われた物語「篝火(かがりび)」
長良川のほとり
「篝火(かがりび)」(『新小説』1924・3・1)は、その発端を描いた作品である。
「私」は、朝倉(三明永無みあけ えいむ がモデル)とふたりで岐阜に来る。岐阜名産の雨傘と提灯を作る家の多い田舎町にある澄願寺に、みち子を訪ねる。
半月のうちに二度も、東京から岐阜のみち子を訪ねてくるのは、養父母の手前、穏やかではないので、名古屋方面に行く修学旅行のついでに寄るといつわって、手紙を書いての訪問だった。
みち子は、和尚が壁塗りをする手伝いをしていた。やがて「私」の前に着疲れた単衣(ひとえ)で坐っているみち子を見ながら、「私」はこの二十日ばかり空想してきたみち子と、現実のみち子の隔たりを感じて、自分の願望がどんなにみち子を苦しめているかを思って暗澹たる思いになる。自分の一途な恋情が、恋に未経験なみち子を懊悩させていることへの反省である。
しかし朝倉の機転で、みち子を寺から出させることに成功したふたりは、長良川の川向こうの宿に来る。そこで「私」が湯に入っているあいだに朝倉がみち子を口説いて「私」との結婚を承諾させる、という筋書きだった。
朝倉は、「私」の知らないうちに、みち子を口説いていた。「俊さんが君を望んでゐる。お前の身にとって、こんないいことはないと僕も思ふし、それに第一、非常に似合ひだ」と言ってくれたのである。
「朝倉さんから聞いてくれたか。」
さつと、みち子の顔の皮膚から命の色が消えた。と見る瞬間に、ほのぼのと血の帰るのが見えて、紅く染つた。
「ええ。」
煙草を銜(くは)へようとすると、琥珀(こはく)のパイプがかちかち歯に鳴る。
「それで君はどう思つてくれる。」
「わたくしはなんにも申し上げません。」
「え?」
「わたくしには、申し上げることなんぞございません。貰つていただければ、わたくしは幸福ですわ。」
幸福といふ言葉は、唐突な驚きで私の良心を飛び上らせた。
「幸福かどうかは……。」と私が言ひかかるのを、さつきから細く光る針金のやうにはきはき響いてゐるみち子の声が、鋭く切つた。
「いいえ、幸福ですわ。」
抑へられたやうに、私は黙つた。
みち子は、今の養父母が自分のうちからお嫁に出すと言っているから、「一旦私の籍を澄願寺へ移して、それから貰つて下されば、わたくしは嬉しいんですわ」と言う。これに対して「私」は、「私のやうな者と婚約してしまつてと、なぜだか、無鉄砲なみち子が可哀想でならない」と思うのである。
そして三人は宿の廊下から、長良川を下ってきた鵜飼いの船を印象深く見る。
「私は篝火をあかあかと抱いてゐる。焔の映つたみち子の顔をちらちら見てゐる。こんなに美しい顔はみち子の一生に二度とあるまい」と思う。――
「篝火」は、およそこのような作品であるが、「私」がみち子を痛ましく思ってならないでいる心がつよく全編を流れている。昨夜の汽車の中で見た女学生たちよりも、みち子が子供であることを思って胸を痛めたりする。
瀬古写真館と故郷・岩谷堂の父
1921(大正10)年10月8日、意外なほど簡単に、みち子は結婚を承諾した。それも、康成が直接口説いたのではなく、友人朝倉が初代を説いて、なかば強引に結婚を納得させたのである。このとき康成は数えで23歳、初代は16歳であった。「篝火」に書いてあるとおりである。
いったん初代を寺に帰した翌日の10月9日、3人は、婚約の記念に、岐阜の裁判所の前にある大きな写真館で、幾枚かの写真をとった。
このときのことを、康成は「南方の火」(第4次37巻本『川端康成全集』第2巻)の第4章に、以下のように書いている。
岐阜市の裁判所前の写真屋だつた。
「髪は?」と時雄が小声に言つた。弓子はひよいと彼を見上げて頬を染めると、子供の素直な軽さでぱたぱたと化粧室へ走つて行つた。 (中略)それを見ただけでも時雄は夢のやうに幸福だつた。微笑が温かくこみ上げてきた。(中略)
しかし男の前では恥かしくて化粧の真似も出来ないほんの小娘だつた。だから、初め時雄と一緒に行つた水澤といふ学生を加へて三人 で写す時には、彼女は海水帽を脱いだばかりのやうにほつれた髪だつた。それからもう一枚二人で写したのが、弓子の父に見せた写真だ つた。
弓子が化粧室を出てくると、写真師が生真面目に、
「どうぞそこへお二人でお並びになつて。」と白いベンチを指さしたが、時雄は弓子と並んで坐ることが出来なかつた。うしろに立つ た。彼の親指に弓子の帯が軽く触れた。その指の仄かな體温で彼は弓子を裸でだきしめたやうな温かさを感じた。
時雄は康成、水澤は三明、弓子が初代であることは、言うまでもない。このとき、三人で並んだ写真と、康成と初代と二人だけの、二枚の写真が撮影されたはずであるが、93年後の今日、三人の写真だけが残って、二人だけの写真は、すでにない。
ここに登場する写真館が瀬古写真館であることは、地元の人々によって、簡単に明らかになった。岐阜裁判所の向かいにある、当時も群を抜いた写真館であったからだ。
瀬古写真館は創業1875(明治9)年の、三層の塔をもつ、瀟洒な洋館の写真館だった。
このとき三人が一緒に写した写真は、後年、長谷川泉が三明永無を説いて譲ってもらい、世に出た。
しかし実は、瀬古写真館にも、原板が残っていた。
岐阜では、若き日の康成が恋人を求めて岐阜を訪れた事実を検証しようと、島秋夫、青木敏郎といった人たちが調査を進め、その結果、「篝火」に澄願寺と記されている寺――初代が養女として預けられていた寺が正しくは浄土宗の西方寺(岐阜市加納新本町)であること、などが明らかにされてきた。
わたくしは、三木秀生『篝火に誓った恋 川端康成が歩いた岐阜の町』(岐阜新聞社、2005・5・5)を入手して、そこに当時の瀬古写真館の写真のあることに驚いた。それがあまりにも見事な洋風建築であったからだ。
川西政明『新・日本文壇史』第三巻(岩波書店、2010・7・15)の第16章「川端康成の恋」には、この瀬古写真館が岐阜市今沢町、と明記されているので、現在も存続しているにちがいない。早速、104番で電話番号を訊ね、康成らの写真がそちらに存在するなら、譲ってほしいと店主夫人らしき方に懇願した。
数日後、現在の社長(正社員36名を擁し、名古屋、四日市にも事業所を持つ瀬古写真株式会社に成長していた)瀬古安明氏より、4葉の写真が恵送されてきた。
当時の写真館主、瀬古安太郎が撮影した3人の写真2葉のほかに、3人の署名を写した写真があった。
大正十年十月九日
於 瀬古写真館
三明永無 東大二年(23)
伊藤初代 十六才
川端康成 東大二年(23)
「篝火」に書かれた10月8日の翌9日に、確かに3人は、瀬古写真館で写真をとったのだ。
そして、康成と初代が二人で撮った写真は、今度、岩手県岩谷堂に住む、初代の父に結婚を承諾を得るために行く、いわば二人の愛の証拠写真として機能させる目的を秘めていたのである。
もっとも、このときの約束を、「婚約」と表現するのは、大げさすぎるかもしれない。康成がのちに「文学的自叙伝」に書いているように、「結婚の口約束」という表現が、真実にいちばん近いだろう。
なお、初代をめぐる岐阜の西方寺との関わり、西方寺の住職夫妻、あるいはカフェ・エランのマダムであった山田ますのその後などについては、早い時期に『図書新聞』に発表された三枝康高「川端康成の初恋」が詳しい。この文章は、山田ますのその後の人生についても教えてくれ、流転する人生の不思議をも示唆して味わい深い名文である。
――それはさておき、東京に帰ると、康成は早速、新居の準備をはじめた。といっても先立つものは金である。
菊池寛と康成のかかわりについては後述するが、まだ二、三度会ったばかりの先輩である。翻訳の仕事でも紹介してもらえれば、ぐらいの気持だった。
私の二十三歳の秋であつた。菊池氏は今の私より若い三十四 歳であつた。私は小石川中富坂の菊池氏の家を訪れて、二階の部屋に対坐するなり、娘を一人引き取ることになつたから、翻 訳の仕事でもあれば紹介してほしいと、突然頼んだ。菊池氏はうんと力強くうなづいて、引き取るつて、君が結婚するのか。ええ、結婚は今直ぐぢやないと、私が弁解めいたことを言ひ出さうとすると、だつて君、いつしよにゐるやうになれば結婚ぢ やないか。そして、その後に直ぐ続いた菊池氏の言葉は、僕は近く一年の予定で洋行する、留守中女房は国へ帰つて暮したい と言ふから、その間君にこの家を貸す、女の人と二人で住んでればよい、家賃は一年分僕が先払ひしておく、別に毎月君に五十円づつやる、一時に渡しといてもいいが、女房から月々送るやうにしといた方がいいだらう。それに君がもらふ学資の五十円くらゐを合せたら、たいてい二人で食へるだらう、君の小説は雑誌へ紹介するやうに芥川によく頼んでおいてやる、そんなことで僕がゐなくてもなんとかやつて行けるだらう、僕が帰つたらその時はまた考へてやる。私はあまりに夢のやうな話で、むしろ呆然と聞いてゐた。
だから、帰りの富坂は、足が地につかぬ喜びで走つて下りた。
二十三の私が十六の小娘と結婚したいと言ふのも非常識だつたが、菊池氏はただ娘の年と居所を聞いただけで、なんの批判も加へず、穿鑿 (せんさく)もしなかつた。
「文学的自叙伝」(『新潮』1934・5・1)の冒頭部分に描かれた告白である。ここにもあるように、伊藤初代と、恩人としての菊池寛は、康成の文学を成立せしめた二つの重要な要素である。
さて、 経済的な目処はついたが、次に康成が必要と考えたのは、初代の父親の承諾を得ることだった。
初代は、数え10歳のとき母を喪い、まもなく父と別れ、尋常小学校の3年を終えたあたりで学校をやめて上京している。
初代の父伊藤忠吉の故郷は、先述したように岩手県江刺郡岩谷堂(現、奥州市江刺町岩谷堂 いわやどう)である。
妻に死なれたあと、忠吉は幼いマキをつれて岩谷堂に帰り、岩谷堂小学校の使丁(用務員)になっていた。会津若松でもこの仕事をしていたこともあり、堅実実直な仕事ぶりであったという。
その父の承認をとって、晴れて結婚したいと康成は考えた。
友人たちも賛成した。友人のひとり鈴木彦次郎は同県盛岡市の名家の出身である。鈴木の先導で、康成をふくめた四人――三明永無、石濱金作――が岩谷堂をたずねることになった。
このとき彼らは東京帝国大学の学生であった。制服角帽のきちんとした身形(みなり)で父親に面会した方がよいだろうと三明が提唱し、それを実行した。
彼ら四人は、水沢の駅から約六キロの距離を、自動車で岩谷堂小学校に到着し、校長に面会を求めた。それから使丁の伊藤忠吉を呼んでもらった。
おずおずと現れた父親に、彼らは、代わる代わる、初代が自身の意志で康成と婚約したと説明し、その証拠として、岐阜で撮影した写真を見せた。
父親は、写真の初代を見て涙をこぼした。
そして、本人がそう希望したなら、それでよい、と小さな声で答えた。
四人は、盛岡の鈴木彦次郎の家に一泊し、翌日、東京に凱旋した。












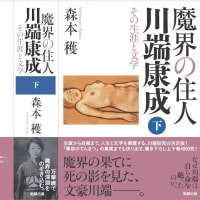
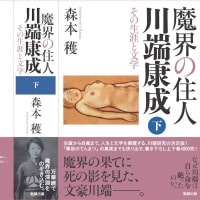

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます