戦時下の川端康成 その16 出版社鎌倉文庫
『人間』のヴィジョン
編集を一任された木村徳三は、昂奮し、感激した。妻と子供を近江から東京へ連れてくると、すぐ編集の実務にとりかかった。
木村の内部には、すでに過去6年間の経験から、望ましい文芸雑誌のヴィジョンが出来上がっていた。端的にいうなら、「文壇的な文芸雑誌ではなく、文芸的総合雑誌ともいうべき雑誌」、あるいは「文学を中心に、思想、芸術の城を総合した新しい雑誌」であった。
最初に木村の念頭にのぼったのは、トマス(ママ)・マンの「来るべきデモクラシイの勝利について」だった。ナチス・ドイツを追われてアメリカに渡ったマンが、1938年にアメリカの15都市で行った講演である。戦前、ドイツ文学者芳賀檀(まゆみ)のエッセイがこれにふれていて、木村の心に焼きついていたのである。この全訳を載せたい、と思った。
京都時代に知遇を得た京都大学の大山定一にこれの翻訳を依頼し、快諾されて、雑誌の1つの柱が出来たように思った。
――出版会社鎌倉文庫の設立事務所は、はじめ丸ビルの中央公論社の一室があてられていたが、10月には、日本橋交差点の角にある白木屋デパートの2階に移った。デパートといっても、物資不足で売るものがなく、売場は地階と2階だけであり、その地階の一隅に貸本屋鎌倉文庫の出店があり、2階には出版会社の鎌倉文庫があって、2階の4分の1ほどのスペースを占めていた。
次に木村が意図したのは、戦前戦後に物故した三木清、島木健作、里村欣三や、フランスのポール・ヴァレリー、ロマン・ロランへの追悼文である。これらを特集しようと考えた。
三木清は、言論界でよく知られた売れっ子哲学者であった。その三木が敗戦直前に逮捕され、敗戦後1ヶ月あまりの9月26日に獄中死したことは、衝撃的な事件でもあった。
文芸的な原稿も、だんだん集まってきた。谷崎潤一郎に宛てた永井荷風の書簡を久米正雄が谷崎から預かってきたし、中山義秀が中村光夫や今日出海の原稿をもらってきた。伊豆大仁に滞在中の里見の小説を入手できたのも、北条誠の手柄だった。
それにもまして嬉しかったのは、終戦直後に逝去した島木健作の遺稿「赤蛙」を、康成が持ってきたことである。これは絶品ともいうべき傑作で、康成が選びぬいた作品であった。
このほか、小説蘭には、正宗白鳥、里見、川端康成、林芙美子ら売れっ子の作品が揃った。
また『人間』は、新人を世に送り出す、という大きな目標も掲げた。
もう1つ、雑誌の顔ともいうべき表紙の絵に、独立美術協会の重鎮、須田国太郎の、逞しい男女が後ろ向きに並び立つ裸像を得たことも、大きな喜びだった。『人間』という誌名にぴったりの、力強く、清新な画風である。
GHQ・CIE(進駐軍文化情報局)の意向で今日出海、里村欣三の原稿が掲載を許可されなかったのは痛かったが、予定どおり12月22日には、創刊号、昭和21年1月号が刷り上がった。
総ページ数240頁、定価4円50銭、部数2万5千――。
創刊号は、あっというまに売り切れた。未曾有の書籍難の時代に、戦前に近い体裁と厚さをもった雑誌があらわれたのだから、当然でもあった。同じころ創刊号を出した『新生』『世界』『展望』も、すべて新雑誌は、あっというまに店頭から消えた。
『人間』は、地方の小売り業者がリュックを背にまとめ買いに来るほどの好調ぶりであった。2月号を5万部、3月号を7万部と発行部数をふやしたが、同じように、たちまち売り切れた。
敗戦後10日もたたぬ8月23日の、文壇による島木健作告別式で、康成は「山里にでも入りたい厭離(おんり)の心が逆に身は日本橋の真中に出て日々をまぎらはしてゐるこの頃……」と弔辞を読んだが、実際、株式会社鎌倉文庫は、異常なほどの繁栄を見せ、康成たちは、その業務に追われる毎日だった。
出版社の話が降って湧いたころ、康成は、新しい出版の企画を提示したが、それを実現してゆくこととなり、『人間』の刊行と相接するようにして、『現代文学選』『大衆文学選』『世界文学選』『青春の書』『国木田独歩全集』の五大企画が次々と実践されていった。
『現代文学選』では、里見『潮風』、志賀直哉『和解』を筆頭に、横光利一『紋章』、永井荷風『墨東綺譚』、谷崎潤一郎『蓼(たで)食う虫』が、『大衆文学選』では、菊池寛『三家庭』、吉屋信子『良人の貞操』前後編、吉川英治『松のや露八』が、続々と刊行され、これまた飛ぶように売れていった。
さらに、『人間』につづいて、同年5月には女性向けの雑誌『婦人文庫』が、10月には一般社会人向けの雑誌『社会』が、またヨーロッパ文学の紹介雑誌『ヨーロッパ』が発刊された。
意外な実務家
戦争末期に鎌倉文庫が店をひらいた時、予想外の反響に、発起人たちは当番の割り当てをつくり、夫人たちも動員して仕事に励んだが、その過程でわかったことがあった。
レコード会社に勤めたことがあり、初めから事務能力を期待されていた高見順が予想どおりに実力を発揮したことは、まあ当然であったが、それ以上に意外な実務能力を発揮したのが康成であった。
作風から、世間的な実務からは遠いと思われてきた康成が、いざ開店してみると、臨機応変に迫られる決断をてきぱきとくだし、必要な備品の詳細なリストを作るなど、予想外の働きをしたことに作家たちは驚いたが、株式会社になったとき、重役の一人に推されると、康成は、弁当を持って鎌倉から日本橋に日参した。ほかの作家重役が大体週2、3日鎌倉から出社、というなかで、康成だけはほぼ毎日の出勤だった。
木村徳三は、前引の書で次のように書いている。
鎌倉文庫の作家たちの中で最も『人間』の編集を助けてもらったのは川端康成氏である。創刊号における島木健作氏の遺稿「赤蛙」や中里恒子氏の「まりあんぬ物語」をはじめとして、三島由紀夫氏の「煙草」「中世」、耕治人氏の「監房」、北条誠氏の「一年」、檀一雄氏の「終りの火」、石濱恒夫氏の「ぎゃんぐ・ぽうえっと」等々、数多くの小説が川端さんから託された作品である。
また、次のようにも述べている。川端康成の本質を見抜いた名評であろう。
私は川端康成氏というひとは、もし芸術家の道を歩まず(この仮定の荒唐無稽さはさておき、)企業家だったとしても必ず一流の企業家になり得たひとだと思っている。政治家であっても超一流ではなかったか。事に当たっての度胸のよさ、非情さ、判断の速さ、確かさ、大局をつかんだ損徳(ママ)勘定のしたたかさ――あの独特の芸術家的風貌からは想像もできないそれらを、私は鎌倉文庫時代の経験を通じて何度か痛感した。とかく揉め事の多い葬儀の委員長役を引き受け”葬式の名人”とも言われたのもこの卓抜な能力のためであろう。もともと世の掟とかきまりとかいうものを、十分承知の上でなおかつ全く意に介さないひとである。
そのころの康成の精勤と多忙を示す手帳が、1999年6月1日、生誕百年記念特集として刊行された『新潮』に「昭和20年 ~21年日記」として発表されている。
これは、「日記」というより、「手帖」である。これを見ると、たとえば永井荷風の旧作を『現代文学選』に入れるために手紙を書き、熱海に訪問し、書簡を往復した事実をはじめ、康成の八面六臂の活動が克明に綴られている。おびただしい数の作家たちと折衝していることに驚かされる。
この会社役員生活が、のちに『山の音』の主人公尾形信吾の生活に反映されていることは、いうまでもないだろう。また小説家として、戦後日本の風俗を思うさま観察することができたことも、戦後の作品を豊饒にする、大きな要因となったと思われる。
康成の心底に深くあった「山里」の隠遁生活と、その正反対ともいうべき東京の中心地、日本橋への日参――。
同じとき、株式会社鎌倉文庫の平(ひら)取締役として、日本橋に通った中山義秀は、鎌倉から出京して眼にした光景を、『台上の月』39章において、次のように描写している。
鎌倉から出京して目にふれるものは、満目瓦礫と化した焼け跡の廃墟、栄養失調のため瀕死の状態で、東京駅のホームへ列車からかつぎだされる復員兵、浮浪の戦災孤児や欠食児童、襤褸(らんる)衣のパンパン、乞食、駅前の広場、橋畔、路傍いたるところにひり散らされてある糞便の山――かういつた敗戦の現実を、私達はまのあたり体験した。
康成もまた、同じ光景をほとんど毎日目撃したはずである。敗戦国の無慙な、赤裸々な現実。――そこから、「哀愁」の、あの決然とした断言が吐き出されるのである。
敗戦後の私は日本古来の悲しみのなかに帰つてゆくばかりである。私は戦後の世相なるもの、風俗なるものを信じない。現実なるものもあるひは信じない。
日ごとに否応なく眼に入ってくる「戦後の世相なるもの」「風俗なるもの」、それをあえて拒否し、眼をつむって、自分は「日本古来の悲しみ」のなかに帰ってゆくばかりであると、日本古来の伝統的な美を引き継ぐ悲壮な決意を宣言するのである。
――『人間』は、その後も文学史に残る名作を多く誌上に載せるなど、戦後の日本文化に大きく貢献したが、昭和24年10月、鎌倉文庫は倒産し、康成たちの役割は終わった。
『人間』の編集は目黒書店に移行したが、昭和26年8月号をもって終刊となった。
途中で大同製紙が資本金を引き揚げたことなども倒産の一因に数えられようが、やはり世情が落ち着いて、多くの古い出版社も社業を再開すると、好況に眼をくらまされた素人の経営には限界があった、ということだろう。
『人間』のヴィジョン
編集を一任された木村徳三は、昂奮し、感激した。妻と子供を近江から東京へ連れてくると、すぐ編集の実務にとりかかった。
木村の内部には、すでに過去6年間の経験から、望ましい文芸雑誌のヴィジョンが出来上がっていた。端的にいうなら、「文壇的な文芸雑誌ではなく、文芸的総合雑誌ともいうべき雑誌」、あるいは「文学を中心に、思想、芸術の城を総合した新しい雑誌」であった。
最初に木村の念頭にのぼったのは、トマス(ママ)・マンの「来るべきデモクラシイの勝利について」だった。ナチス・ドイツを追われてアメリカに渡ったマンが、1938年にアメリカの15都市で行った講演である。戦前、ドイツ文学者芳賀檀(まゆみ)のエッセイがこれにふれていて、木村の心に焼きついていたのである。この全訳を載せたい、と思った。
京都時代に知遇を得た京都大学の大山定一にこれの翻訳を依頼し、快諾されて、雑誌の1つの柱が出来たように思った。
――出版会社鎌倉文庫の設立事務所は、はじめ丸ビルの中央公論社の一室があてられていたが、10月には、日本橋交差点の角にある白木屋デパートの2階に移った。デパートといっても、物資不足で売るものがなく、売場は地階と2階だけであり、その地階の一隅に貸本屋鎌倉文庫の出店があり、2階には出版会社の鎌倉文庫があって、2階の4分の1ほどのスペースを占めていた。
次に木村が意図したのは、戦前戦後に物故した三木清、島木健作、里村欣三や、フランスのポール・ヴァレリー、ロマン・ロランへの追悼文である。これらを特集しようと考えた。
三木清は、言論界でよく知られた売れっ子哲学者であった。その三木が敗戦直前に逮捕され、敗戦後1ヶ月あまりの9月26日に獄中死したことは、衝撃的な事件でもあった。
文芸的な原稿も、だんだん集まってきた。谷崎潤一郎に宛てた永井荷風の書簡を久米正雄が谷崎から預かってきたし、中山義秀が中村光夫や今日出海の原稿をもらってきた。伊豆大仁に滞在中の里見の小説を入手できたのも、北条誠の手柄だった。
それにもまして嬉しかったのは、終戦直後に逝去した島木健作の遺稿「赤蛙」を、康成が持ってきたことである。これは絶品ともいうべき傑作で、康成が選びぬいた作品であった。
このほか、小説蘭には、正宗白鳥、里見、川端康成、林芙美子ら売れっ子の作品が揃った。
また『人間』は、新人を世に送り出す、という大きな目標も掲げた。
もう1つ、雑誌の顔ともいうべき表紙の絵に、独立美術協会の重鎮、須田国太郎の、逞しい男女が後ろ向きに並び立つ裸像を得たことも、大きな喜びだった。『人間』という誌名にぴったりの、力強く、清新な画風である。
GHQ・CIE(進駐軍文化情報局)の意向で今日出海、里村欣三の原稿が掲載を許可されなかったのは痛かったが、予定どおり12月22日には、創刊号、昭和21年1月号が刷り上がった。
総ページ数240頁、定価4円50銭、部数2万5千――。
創刊号は、あっというまに売り切れた。未曾有の書籍難の時代に、戦前に近い体裁と厚さをもった雑誌があらわれたのだから、当然でもあった。同じころ創刊号を出した『新生』『世界』『展望』も、すべて新雑誌は、あっというまに店頭から消えた。
『人間』は、地方の小売り業者がリュックを背にまとめ買いに来るほどの好調ぶりであった。2月号を5万部、3月号を7万部と発行部数をふやしたが、同じように、たちまち売り切れた。
敗戦後10日もたたぬ8月23日の、文壇による島木健作告別式で、康成は「山里にでも入りたい厭離(おんり)の心が逆に身は日本橋の真中に出て日々をまぎらはしてゐるこの頃……」と弔辞を読んだが、実際、株式会社鎌倉文庫は、異常なほどの繁栄を見せ、康成たちは、その業務に追われる毎日だった。
出版社の話が降って湧いたころ、康成は、新しい出版の企画を提示したが、それを実現してゆくこととなり、『人間』の刊行と相接するようにして、『現代文学選』『大衆文学選』『世界文学選』『青春の書』『国木田独歩全集』の五大企画が次々と実践されていった。
『現代文学選』では、里見『潮風』、志賀直哉『和解』を筆頭に、横光利一『紋章』、永井荷風『墨東綺譚』、谷崎潤一郎『蓼(たで)食う虫』が、『大衆文学選』では、菊池寛『三家庭』、吉屋信子『良人の貞操』前後編、吉川英治『松のや露八』が、続々と刊行され、これまた飛ぶように売れていった。
さらに、『人間』につづいて、同年5月には女性向けの雑誌『婦人文庫』が、10月には一般社会人向けの雑誌『社会』が、またヨーロッパ文学の紹介雑誌『ヨーロッパ』が発刊された。
意外な実務家
戦争末期に鎌倉文庫が店をひらいた時、予想外の反響に、発起人たちは当番の割り当てをつくり、夫人たちも動員して仕事に励んだが、その過程でわかったことがあった。
レコード会社に勤めたことがあり、初めから事務能力を期待されていた高見順が予想どおりに実力を発揮したことは、まあ当然であったが、それ以上に意外な実務能力を発揮したのが康成であった。
作風から、世間的な実務からは遠いと思われてきた康成が、いざ開店してみると、臨機応変に迫られる決断をてきぱきとくだし、必要な備品の詳細なリストを作るなど、予想外の働きをしたことに作家たちは驚いたが、株式会社になったとき、重役の一人に推されると、康成は、弁当を持って鎌倉から日本橋に日参した。ほかの作家重役が大体週2、3日鎌倉から出社、というなかで、康成だけはほぼ毎日の出勤だった。
木村徳三は、前引の書で次のように書いている。
鎌倉文庫の作家たちの中で最も『人間』の編集を助けてもらったのは川端康成氏である。創刊号における島木健作氏の遺稿「赤蛙」や中里恒子氏の「まりあんぬ物語」をはじめとして、三島由紀夫氏の「煙草」「中世」、耕治人氏の「監房」、北条誠氏の「一年」、檀一雄氏の「終りの火」、石濱恒夫氏の「ぎゃんぐ・ぽうえっと」等々、数多くの小説が川端さんから託された作品である。
また、次のようにも述べている。川端康成の本質を見抜いた名評であろう。
私は川端康成氏というひとは、もし芸術家の道を歩まず(この仮定の荒唐無稽さはさておき、)企業家だったとしても必ず一流の企業家になり得たひとだと思っている。政治家であっても超一流ではなかったか。事に当たっての度胸のよさ、非情さ、判断の速さ、確かさ、大局をつかんだ損徳(ママ)勘定のしたたかさ――あの独特の芸術家的風貌からは想像もできないそれらを、私は鎌倉文庫時代の経験を通じて何度か痛感した。とかく揉め事の多い葬儀の委員長役を引き受け”葬式の名人”とも言われたのもこの卓抜な能力のためであろう。もともと世の掟とかきまりとかいうものを、十分承知の上でなおかつ全く意に介さないひとである。
そのころの康成の精勤と多忙を示す手帳が、1999年6月1日、生誕百年記念特集として刊行された『新潮』に「昭和20年 ~21年日記」として発表されている。
これは、「日記」というより、「手帖」である。これを見ると、たとえば永井荷風の旧作を『現代文学選』に入れるために手紙を書き、熱海に訪問し、書簡を往復した事実をはじめ、康成の八面六臂の活動が克明に綴られている。おびただしい数の作家たちと折衝していることに驚かされる。
この会社役員生活が、のちに『山の音』の主人公尾形信吾の生活に反映されていることは、いうまでもないだろう。また小説家として、戦後日本の風俗を思うさま観察することができたことも、戦後の作品を豊饒にする、大きな要因となったと思われる。
康成の心底に深くあった「山里」の隠遁生活と、その正反対ともいうべき東京の中心地、日本橋への日参――。
同じとき、株式会社鎌倉文庫の平(ひら)取締役として、日本橋に通った中山義秀は、鎌倉から出京して眼にした光景を、『台上の月』39章において、次のように描写している。
鎌倉から出京して目にふれるものは、満目瓦礫と化した焼け跡の廃墟、栄養失調のため瀕死の状態で、東京駅のホームへ列車からかつぎだされる復員兵、浮浪の戦災孤児や欠食児童、襤褸(らんる)衣のパンパン、乞食、駅前の広場、橋畔、路傍いたるところにひり散らされてある糞便の山――かういつた敗戦の現実を、私達はまのあたり体験した。
康成もまた、同じ光景をほとんど毎日目撃したはずである。敗戦国の無慙な、赤裸々な現実。――そこから、「哀愁」の、あの決然とした断言が吐き出されるのである。
敗戦後の私は日本古来の悲しみのなかに帰つてゆくばかりである。私は戦後の世相なるもの、風俗なるものを信じない。現実なるものもあるひは信じない。
日ごとに否応なく眼に入ってくる「戦後の世相なるもの」「風俗なるもの」、それをあえて拒否し、眼をつむって、自分は「日本古来の悲しみ」のなかに帰ってゆくばかりであると、日本古来の伝統的な美を引き継ぐ悲壮な決意を宣言するのである。
――『人間』は、その後も文学史に残る名作を多く誌上に載せるなど、戦後の日本文化に大きく貢献したが、昭和24年10月、鎌倉文庫は倒産し、康成たちの役割は終わった。
『人間』の編集は目黒書店に移行したが、昭和26年8月号をもって終刊となった。
途中で大同製紙が資本金を引き揚げたことなども倒産の一因に数えられようが、やはり世情が落ち着いて、多くの古い出版社も社業を再開すると、好況に眼をくらまされた素人の経営には限界があった、ということだろう。












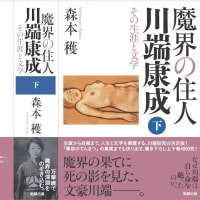
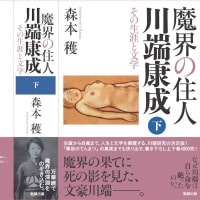

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます