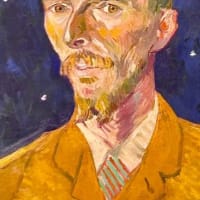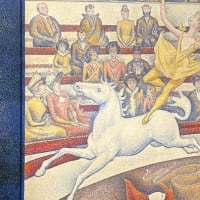注:以下情報は2015年当時のブログです。
地球上の酸素生産の50%をになっている
プランクトン
そんなプランクトンの人生が明らかになりました。

2009年から2013年、帆船タラ号で国際研究チームが調査しました。
京都大学の緒方博之教授も参加

こんな0.02ミクロンから数ミリの生物まで取ることができるアミで

3段階の水深で、35000個のプランクトンを採取
水深5メートル(光が届く)、70メートル(光合成が活発)、600メートル(光が届かない)
DNA解析で、真核生物(原生生物、動物性プランクトン)は
15万種類存在することがわかりました

キラキラとベネチアングラスみたいなプランクトン

1991年に発表されたクラゲの「不老不死(ふろうふし)」で
センセーションを起こした地中海クラゲの仲間のプランクトン
正確には、若返りをするんだって
日本でも10回若返りした記録があるらしいよ
「若返り」を研究する京大准教授 クラゲを若返らせることに成功

環境との相互作用として、
インド洋と大西洋の水が入り込む喜望峰沖(アフリカの南端)でできる低温の海流の渦が
インド洋側プランクトンと大西洋側プランクトンを
それぞれが境界を越えて混ざらないようにしていることもわかりました。
収集されたデータは公開され、
気候変動が海洋エコシステムに及ぼしている影響を調査するための大事な資料になります。
海の中はまだまだ知られていないことがいっぱいの宝箱
今回の調査は、地球環境と海の生物との関係を知る上でも重要な研究基盤になるそうです。