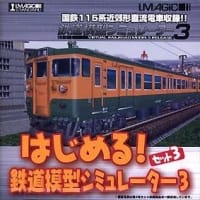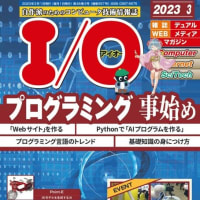長文の上、身の上話でもあるので失礼します(^_^;)
私が初めて鉄道模型シミュレーター(略称VRM)に触れたのは「はじめる!鉄道模型シミュレーター3セット3 近郊型電車115系」でした。しかしながら3DCGをやっていた私にとっては画像がまだ粗く、正直言ってしょぼいグラフィックスにガッカリし2~3回起動しただけで終了しました。

それから数年し、VRM4の夜景のスクリーンショットを見てコレなら十分満足のいくグラフィックスであると感じて2007年4月にVRM4を始めました。鉄道模型は結構所有していましたが走らせられるほど広い家に住んでいる訳ではなかったですし、機械設計を生業とする私にとってはセンサーとスクリプトで制御するシステムは正に打って付けで、気軽に出来るシミュレーターとしてのめり込みました。

このセンサーとスクリプトで制御するシステムは既存のVRM3ユーザーには難しかったのでしょうか、多くの人がこれによって離れたかもしれないのですが、逆にVRM4になって新たな人も多く入ってきていたという印象もありました。確かにスクリプトによって難易度が上がり、考える力を要求されるようになった訳ですが、出来ることが限られていたVRM3の制御から進化するためには必要な過程だったのでしょう。もしこの時点でVRMONLINE(VRM5)から登場した自動センサーがあれば離脱者も減ったのかもしれませんが・・・。
VRM4の時代は正にブログ文化の全盛期で幾つものVRM関連ブログが書かれていました。それぞれ個性のあるブログで、鉄道知識を得意とする人、情景作りを得意とする人、スクリプトを得意とする人、テクスチャー作成を得意とする人など色々と特徴のある人達が日々切磋琢磨してVRMを盛り上げていました。ただこの時代もストラクチャーが各パッケージに分散していて中々他人が作ったレイアウトを完全再現できないという問題は毎日のように議論されていましたね。
そんな中、パッケージ問題を解決しようとしたのでしょうか、VRMはパッケージ販売からオンライン販売へ変貌することが発表され、2008年12月15日VRMONLINEが正式スタートします。当初は月額費用が必要とされましたがユーザーの猛反発があったせいでしょうか、この月額費用は中止され2009年2月2日には入会金のみが必要という形に変わりました。記録では私は2008年11月4日にVRMONLINE入会、2009年1月20日に1000円を支払っています。しかし、この1000円というのは確かVRM4の全パーツをVRMONLINEで使えるようにするという短期キャンペーンに乗っかったものだったと記憶しています。ここがVRM4ユーザーがVRMONLINEユーザーになる最大のチャンスだった訳でこれを逃した人はVRMONLINEユーザーにならなかったのではないでしょうか。またオンラインになれば制作&運営会社都合によるサービス終了のリスクがあることからこれに反発して辞めていった人が多数いました。この時は辞めていく人ばかりで新しく入ってきたという感じの人はいないように感じましたね。そんな状況に不安を感じたのか、アイマジック社は2009年2月20日にパッケージ版であるVRM5を発売します。ここにパッケージ版とオンライン版の2つが存在するという面倒臭い状況が発生しました。
私はVRM5第0号と第1号は購入しましたが、ここで私は海外ソフトのTrainzの方へと舵を切ります。というのも、この時点ではVRM4もVRM5も大差がなく高価なパッケージを再び購入していくことが馬鹿馬鹿しくなったこと、VRMONLINEがサービス終了した時に自分だけでなくVRM仲間も移籍できる先を作っておきたいと思ったこと、海外ソフトの良い点を紹介していくことでアイマジック社への刺激を与えVRMがより良くなるようにしたかったことの3点が挙げられます。この後、2009年4月1日に自動センサー登場でVRM4との差が出来、2014年にVRMCLOUDが登場して自作車両が使えるようになったのですが、それは私がVRMから一旦離れた状態の時でした。
VRM話とは離れてしまいますが、私は2010年からHDR写真を撮るようになります。これは創作活動が出来なくなりつつあり、その場にある情景を写真に撮るけれども創作物(CG)っぽくみせるという手法を取っていたのです。この頃から「鬱」の症状が出ていた訳ですね。2011年にはTRAINZ12が出てますがもう限界だったのでしょう、ブログ更新も途切れました。そして治療中に躁鬱病(双極性障害)であることが判明し2012年は「躁」の治療が中心となりました。2012年10月4日障害者手帳取得、その日は奇しくもその後数年嵌り続けるバイオハザード6の発売日でした。2015年10月17日VRM東京オフ会には参加しましたが、その後はブログ更新もせずPS4でゲームをすることが趣味になる日々が続きました。そして、他人が作ったゲームを消費することに飽き、かなり回復したこともあり再びクリエイティブな活動をしたいなぁと思っていたタイミングでUSO800鉄道さんからDISCORDにお誘いいただき、2021年1月13日に「鉄道模型シミュレーターコミュニティ」に参加。そして2021年1月末からブログにも復帰しました。
復帰後はパーツを買いまくってストラクチャーに関しては殆どのパーツを揃えました。2022年12月23日に終了したアシアルサーバのVRMONLINEで23万6千円も使っています(^_^;) 鉄道模型シミュレーターNX(V0~V15)全部で151030円ですからバラ売りのVRMONLINEはやはり割高でしたかね。最初の内はVRMONLINEを使っていましたが徐々にVRMONLINE-NXも使用するようになり、今ではほぼNXの方を使っています。
それでは最後にVRM3、VRM4、VRMONLINE(VRM5)、VRMNX(VRMONLINE-NX)の特徴をまとめましょう。
VRM3
・車両が豊富にある
・グラフィックスは低解像度
・簡単な制御しか出来ない
・販売終了
VRM4
・グラフィックスは十分綺麗(VRM5、VRMNXも同様)
・複雑な制御も出来る(VRM5、VRMNXも同様)
・スクリプト制御は難しい(VRM5も同様)
・販売終了
VRMONLINE(VRM5)
・自動センサーで制御が楽になった(VRMNXも同様)
・自作車両が使える(VRMNXも同様)
・テクスチャーが高解像度に一部対応
VRMNX(VRMONLINE-NX)
・スクリプト制御がPythonになり楽になった
・扉の開閉が出来る車両も登場
・起動が速い
・クローンツールなど作業環境が改善
・テクスチャーが高解像度に標準対応
・地形が把握しづらい(全バージョンそうですが)
恐らく開発者的にはNXが最後のバージョンになるのではないかなと思いますが、それに見合うだけの改善が見られVRMの集大成に相応しいソフトになりつつあるという感じです。