東京五輪・パラリンピックを巡る汚職事件の舞台となった大会組織委員会には、権威に異を唱えられぬ悲しき人々がいた。政治家や経営者、元官僚、元アスリート、文化人……。多彩な背景を持つ理事が30人以上そろっていたが、多くが自己主張を控え、存在感を消していた。組織委の理事に限らず、日本には社長を監督しない取締役、上司の言いなりの部下がどこにでもいる。五輪を汚した、権威に弱い「普通の人々」を追う。
◇ ◇ ◇
今となっては、組織委が掲げた崇高な基本コンセプトがむなしい。
未来への継承
・東京1964大会は(中略)高度経済成長期に入るきっかけとなった大会。
・東京2020大会は、成熟国家となった日本が、今度は世界にポジティブな変革を促し、それらをレガシーとして未来へ継承していく。
1年間の延期を経て、2021年夏に開かれた2度目の東京五輪は、世界にポジティブな変革を促すどころか、成熟国家を自任する日本で、不正が横行していることを印象づける大会となった。現在、東京地裁で五輪のスポンサー選定などを巡る汚職事件の裁判が進んでいる。加えてテスト大会で入札談合があったとして、東京地検特捜部と公正取引委員会が捜査中だ。
<picture class="picture_p169s49k"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2912144027012023000000-1.jpg?ixlib=js-2.3.2&w=425&h=266&auto=format%2Ccompress&ch=Width%2CDPR&q=45&fit=crop&bg=FFFFFF&s=e0957cd95c1f05c9de4a054673fba9dd" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2912144027012023000000-1.jpg?ixlib=js-2.3.2&w=425&h=266&auto=format%2Ccompress&ch=Width%2CDPR&q=45&fit=crop&bg=FFFFFF&s=e0957cd95c1f05c9de4a054673fba9dd" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2912144027012023000000-1.jpg?ixlib=js-2.3.2&w=425&h=266&auto=format%2Ccompress&ch=Width%2CDPR&q=45&fit=crop&bg=FFFFFF&s=e0957cd95c1f05c9de4a054673fba9dd" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2912144027012023000000-1.jpg?ixlib=js-2.3.2&w=425&h=266&auto=format%2Ccompress&ch=Width%2CDPR&q=45&fit=crop&bg=FFFFFF&s=e0957cd95c1f05c9de4a054673fba9dd" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2912144027012023000000-1.jpg?ixlib=js-2.3.2&w=425&h=266&auto=format%2Ccompress&ch=Width%2CDPR&q=45&fit=crop&bg=FFFFFF&s=e0957cd95c1f05c9de4a054673fba9dd" media="(min-width: 0px)" />

</picture>
保釈され東京拘置所を出る組織委元理事の高橋治之被告。スポンサーの選定などで便宜を図る見返りに、各社から賄賂を受領した受託収賄罪で起訴された。本人は否定している模様
崇高な理念を掲げた国家的イベントを地に落としたのは権威に弱い、どこにでもいる「普通の人々」だ。不正に手を染めた疑いのある現場と、現場の不正を防げなかった組織委の理事会の双方に、権威に異を唱えられぬ悲しき人々の姿があった。
まずは理事らが形骸化させた理事会の内実をご覧に入れよう。毎回しゃんしゃんで終わってしまう多くの民間企業の取締役会と似ていることが分かっていただけるはずだ。人ごとでは済ませられない。
出発点は森喜朗氏の女性蔑視発言
覚えているだろうか。21年2月に開かれた日本オリンピック委員会(JOC)の会議で当時、組織委の会長だった森喜朗氏が、あいさつ中に女性を蔑視し、辞任に追い込まれた。発言の要旨は次の通り。
「(私が過去に会長を務めていた)日本ラグビー協会にはたくさんの女性理事がいるため、理事会に時間がかかる。(これに対して)私どもの組織委の女性理事はみんなわきまえておられて、お話がシュッとして、的を射ている。我々にとって非常に役に立っている」。森氏の真意は本人のみぞ知るだが、「余計なことを長々と発言しない」ことが、「わきまえている」ことだと解釈できる。
組織委のような団体の理事会は民間企業の取締役会に相当し、不正を防ぐ仕組みの構築と運用が法的に求められていた。結果的に理事らは実効性のある仕組みの導入に失敗したと言わざるを得ない。「わきまえる」という言葉にその原因が隠れている、との仮説に基づいて記者は取材に乗り出した。
今回、複数の元理事が取材に応じてくれた。その一人である佐野道枝氏(仮名)は取材中、「理事会で積極的に意見を出さず、与えられた役割を果たさなかった。本当に情けなく、申し訳ない」と、率直に陳謝した。
「理事会で発言を控えたあなたは、『わきまえた女性理事』の一人だったと言えるのではないだろうか?」。記者のそんな質問に、佐野氏は「確かにそうだ」と吐露した。
佐野氏だけではない。性別にかかわらず、理事らの受け身の姿勢が、理事会の議事録からうかがえる。理事会は14年1月〜22年6月の8年半に50回開かれた。そのうち15年12月以降に開催された計42回分の議事録(要約版)が公開されている。
<picture class="picture_p169s49k"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2917108029012023000000-1.jpg?ixlib=js-2.3.2&w=425&h=283&auto=format%2Ccompress&ch=Width%2CDPR&q=45&fit=crop&bg=FFFFFF&s=b35793a30a2b7c3dfd1724035f2d17cc" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2917108029012023000000-1.jpg?ixlib=js-2.3.2&w=425&h=283&auto=format%2Ccompress&ch=Width%2CDPR&q=45&fit=crop&bg=FFFFFF&s=b35793a30a2b7c3dfd1724035f2d17cc" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2917108029012023000000-1.jpg?ixlib=js-2.3.2&w=425&h=283&auto=format%2Ccompress&ch=Width%2CDPR&q=45&fit=crop&bg=FFFFFF&s=b35793a30a2b7c3dfd1724035f2d17cc" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2917108029012023000000-1.jpg?ixlib=js-2.3.2&w=425&h=283&auto=format%2Ccompress&ch=Width%2CDPR&q=45&fit=crop&bg=FFFFFF&s=b35793a30a2b7c3dfd1724035f2d17cc" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO2917108029012023000000-1.jpg?ixlib=js-2.3.2&w=425&h=283&auto=format%2Ccompress&ch=Width%2CDPR&q=45&fit=crop&bg=FFFFFF&s=b35793a30a2b7c3dfd1724035f2d17cc" media="(min-width: 0px)" />
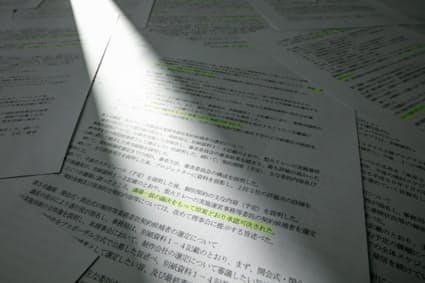
</picture>
組織委の理事会の議事録は「原案どおり承認可決された」のオンパレードだ(写真:スタジオキャスパー
この間、森会長が理事会の議長として諮った議案は115件、後任の橋本聖子会長は22件に上った。決議に先立って、まず進行役や事務局の担当者が議案の内容を説明した。テーマは「組織運営改革に伴う体制整備について」「事業計画および収支予算などについて」「副会長の選定について」など多岐にわたった。ところが説明を受けても、理事らが活発に審議した様子はほとんど見受けられない。
理事会の出席者によると、開会時に「本日は2時間後の午後3時から記者団へのブリーフィングがあります」などと伝えられた。ブリーフィングが始まる時刻までに閉会することを意識させられ、審議に時間をかける雰囲気はなかったという。
たまに意見が出たとしても、「引き続き厳しく経費の精査に努めていただきたい」「パラリンピアンなどが意見を言える場を設定してほしい」といった無難なものばかりで、誰も議案の是非を問うことはなかったようだ。政治家や経営者、元官僚、元アスリート、文化人など多彩な背景を持つ、30人超の理事らがそろっていたにもかかわらず、自分の経験や知識を議案に反映しようとする者はいなかったと言っていい。
「国・都・JOCが決めていた」
議案の修正や、差し戻しを求めたことは一度もなく、森会長や橋本会長が諮った議案は一つ残らず、「満場一致の議決をもって原案どおり承認可決された」(議事録から)。議案が最初から完璧であるならともかく、原案の可決率が100%だと、そもそも理事会は意思決定機関として機能していたのかとの疑問が湧く。
佐野氏は「重要な事柄は国と東京都、JOCの協議ですでに決定していた」と明かす。理事会の実態は、ただの追認機関だったと言える。
その日の理事会で用意されたすべての議案について決議を終えると、残りの時間で「スポンサーの決定について」「選手村について」「マスコット公募選考について」といった職務執行状況について事務局の担当者が報告した。これは会長らが適切に職務を執行しているかを、理事会で監視するための報告である。
報告が全部済むと、理事らによる意見交換の時間となる。職務執行状況に不満があれば、ここで表明できたはずだ。
だが、この頃になると、もう記者ブリーフィングまで5分ぐらいしか残っていないことも少なくなかった。ある元理事は、「意味のある意見交換はほとんどなされなかったと私は認識している」と振り返る。
本来、理事らには「一般法人法」に基づき、ほかの理事や職員が不正を働かないよう内部統制システムを構築し、運用する義務があった。具体的には、理事会で実効性のある内部統制システムを審議・決議し、会長ら職務執行者が適切に運用しているかを監視することが求められていた。しかし、理事の多くが自己主張を控え、存在感を消していた。
多くの企業にとって対岸の火事ではない。組織委の理事会のように、追認機関に成り下がっている取締役会が少なくないのが実情だ。
スルガ銀の取締役会にそっくり
女性専用シェアハウス「かぼちゃの馬車」の運営会社の経営破綻をきっかけに、18年に多額の不正融資が発覚したスルガ銀行も、その一社だった。
「取締役会において議案が否決されたり、修正されたり、差し戻しとなったことはない。すべての議案が原案のまま承認可決されている」「取締役会が実質的に議論をし、物事を決めていく場ではなかったと評価せざるを得ない」。スルガ銀行の不祥事を調査した第三者委員会は、現場で不正が横行していることを察知できなかった取締役会を、報告書でこう断罪した。
取締役会は一方的に職務執行状況の報告を受けたり、議案を提示されたりするのではなく、取締役会側から能動的に報告を求める事項を指定したり、審議すべき議案を話し合って決めたりすべきであると第三者委員会は提言した。また毎回短時間で終わらせていた取締役会を延長し、審議に必要な時間を十分確保することも提案している。組織委の理事会もこうした措置を取っていれば、不正のリスクを減らせたに違いない。
名ばかりの意思決定機関は、決議の作法も変えねばならないだろう。そうした会議体では、議長が「ご異議ありませんか?」と問うて決議をとることが多い。すかさず理事や取締役の一部が「異議なし!」と叫んで承認可決する。意思決定方法としては一般的であり、組織委の理事会も例外ではなかった。
歌舞伎のような会議
問題は100回、500回、1000回と、何回決議を繰り返しても「異議なし!」という声しか上がらず、必ず原案通り承認可決している場合だ。このような会議体は、歌舞伎と一緒ではないだろうか。歌舞伎では役者が見えを切った時などに、観客が「成田屋!」「12代目!」などと叫ぶならわしとなっている。歌舞伎独特の様式美を崩さないためにも、掛け声は屋号や代数などに限られることが事実上決まっている。
同様に、原案に対して「異議なし!」と叫ぶことが決まっているような意思決定プロセスは、芝居に等しい。そうした体質の会議体に名を連ねる社会的地位の高そうな人々は、舞台の見栄えを良くするための役者だとの指摘は厳しすぎるだろうか。
逆に役者としての立場をわきまえずに、「異議あり!」などと、筋書きにないことを口にすると、それは会議を仕切る議長への挑戦になる。組織委のような団体の理事会であれば会長、民間企業の取締役会であれば社長か会長というように、組織の最高権力者が議長を務めることがほとんどだ。あなたが最高権力者の率いる会議体のメンバーだったら、どう振る舞うだろう。
「私なら、相手がどんなに偉くても立ち向かえる」と思っているのであれば、それは幻想かもしれない。長い進化の過程で、権威に従って組織的に動くことができる集団が生き残ったとされる。その子孫である私たちの心に潜む「服従本能」にあらがうには、相当の覚悟が求められる。
元公安警察のなれ合い防止法
職場で不正が起きる一因に、一緒に仕事をするメンバーが長期にわたって変わらないことによるなれ合いがある。多額の不正融資が明らかになったスルガ銀行では、社員の在籍期間が長い部署で、不正が横行していた。品質不正が広く常態化していた三菱電機の、工場の一つでは、長年一緒に製品の出荷試験を手掛けていた従業員らが、一部の試験項目を省いていた。
「なれ合いの防止には、メンバーの定期的な入れ替えが有効だ」と語るのは、警視庁公安部出身で、在外公館の警備も手掛けたセキュリティー・コンサルタントの松丸俊彦氏である。「施設警備の現場では、警備員の顔ぶれが長く固定化されると、夜間の見回りなどを省いたりし始める恐れがある」と、人事ローテーションの重要性を訴える。「ただ一度に全員を異動させると、マニュアル化しにくいノウハウが失われるので、在籍期間が長い警備員から順次異動させるのが好ましい」と助言する。
「マニュアル化しにくいノウハウ」とは、例えば警備員2人でクレーマーに対処するのが望ましい場面であったとしても、2人がクレーマーにつきっきりになると、ほかの場所の警備が手薄になるケースがある。この場合、1人でクレーマーに対処し、待機中の警備員1人をクレーマー対応の応援として呼ぶといった、ケース・バイ・ケースの変則的な警備方法を指す。
マニュアル化できないノウハウを見極め、その知見が失われない範囲で人事ローテーションを組むという警備の眼目は、そのまま一般的な職場の不正防止策にも適用できる。(日経ビジネス 吉野次郎)

















汚れた五輪 組織委上層部に著名人30人超、中身伴わず【日経ビジネス】
東京五輪・パラリンピックを巡る汚職事件の舞台となった大会組織委員会には、権威に異を唱えられぬ悲しき人々がいた。政治家や経営者、元官僚、元アスリート、文化人……。多彩な背景を持つ理事が30人以上そろっていたが、多くが自己主張を控え、存在感を消していた。組織委の理事に限らず、日本には社長を監督しない取締役、上司の言いなりの部下がどこにでもいる。五輪を汚した、権威に弱い「普通の人々」を追う。
◇ ◇ ◇
今となっては、組織委が掲げた崇高な基本コンセプトがむなしい。
・東京1964大会は(中略)高度経済成長期に入るきっかけとなった大会。
・東京2020大会は、成熟国家となった日本が、今度は世界にポジティブな変革を促し、それらをレガシーとして未来へ継承していく。
1年間の延期を経て、2021年夏に開かれた2度目の東京五輪は、世界にポジティブな変革を促すどころか、成熟国家を自任する日本で、不正が横行していることを印象づける大会となった。現在、東京地裁で五輪のスポンサー選定などを巡る汚職事件の裁判が進んでいる。加えてテスト大会で入札談合があったとして、東京地検特捜部と公正取引委員会が捜査中だ。
崇高な理念を掲げた国家的イベントを地に落としたのは権威に弱い、どこにでもいる「普通の人々」だ。不正に手を染めた疑いのある現場と、現場の不正を防げなかった組織委の理事会の双方に、権威に異を唱えられぬ悲しき人々の姿があった。
まずは理事らが形骸化させた理事会の内実をご覧に入れよう。毎回しゃんしゃんで終わってしまう多くの民間企業の取締役会と似ていることが分かっていただけるはずだ。人ごとでは済ませられない。
出発点は森喜朗氏の女性蔑視発言
覚えているだろうか。21年2月に開かれた日本オリンピック委員会(JOC)の会議で当時、組織委の会長だった森喜朗氏が、あいさつ中に女性を蔑視し、辞任に追い込まれた。発言の要旨は次の通り。
「(私が過去に会長を務めていた)日本ラグビー協会にはたくさんの女性理事がいるため、理事会に時間がかかる。(これに対して)私どもの組織委の女性理事はみんなわきまえておられて、お話がシュッとして、的を射ている。我々にとって非常に役に立っている」。森氏の真意は本人のみぞ知るだが、「余計なことを長々と発言しない」ことが、「わきまえている」ことだと解釈できる。
組織委のような団体の理事会は民間企業の取締役会に相当し、不正を防ぐ仕組みの構築と運用が法的に求められていた。結果的に理事らは実効性のある仕組みの導入に失敗したと言わざるを得ない。「わきまえる」という言葉にその原因が隠れている、との仮説に基づいて記者は取材に乗り出した。
今回、複数の元理事が取材に応じてくれた。その一人である佐野道枝氏(仮名)は取材中、「理事会で積極的に意見を出さず、与えられた役割を果たさなかった。本当に情けなく、申し訳ない」と、率直に陳謝した。
「理事会で発言を控えたあなたは、『わきまえた女性理事』の一人だったと言えるのではないだろうか?」。記者のそんな質問に、佐野氏は「確かにそうだ」と吐露した。
佐野氏だけではない。性別にかかわらず、理事らの受け身の姿勢が、理事会の議事録からうかがえる。理事会は14年1月〜22年6月の8年半に50回開かれた。そのうち15年12月以降に開催された計42回分の議事録(要約版)が公開されている。
この間、森会長が理事会の議長として諮った議案は115件、後任の橋本聖子会長は22件に上った。決議に先立って、まず進行役や事務局の担当者が議案の内容を説明した。テーマは「組織運営改革に伴う体制整備について」「事業計画および収支予算などについて」「副会長の選定について」など多岐にわたった。ところが説明を受けても、理事らが活発に審議した様子はほとんど見受けられない。
理事会の出席者によると、開会時に「本日は2時間後の午後3時から記者団へのブリーフィングがあります」などと伝えられた。ブリーフィングが始まる時刻までに閉会することを意識させられ、審議に時間をかける雰囲気はなかったという。
たまに意見が出たとしても、「引き続き厳しく経費の精査に努めていただきたい」「パラリンピアンなどが意見を言える場を設定してほしい」といった無難なものばかりで、誰も議案の是非を問うことはなかったようだ。政治家や経営者、元官僚、元アスリート、文化人など多彩な背景を持つ、30人超の理事らがそろっていたにもかかわらず、自分の経験や知識を議案に反映しようとする者はいなかったと言っていい。
「国・都・JOCが決めていた」
議案の修正や、差し戻しを求めたことは一度もなく、森会長や橋本会長が諮った議案は一つ残らず、「満場一致の議決をもって原案どおり承認可決された」(議事録から)。議案が最初から完璧であるならともかく、原案の可決率が100%だと、そもそも理事会は意思決定機関として機能していたのかとの疑問が湧く。
佐野氏は「重要な事柄は国と東京都、JOCの協議ですでに決定していた」と明かす。理事会の実態は、ただの追認機関だったと言える。
その日の理事会で用意されたすべての議案について決議を終えると、残りの時間で「スポンサーの決定について」「選手村について」「マスコット公募選考について」といった職務執行状況について事務局の担当者が報告した。これは会長らが適切に職務を執行しているかを、理事会で監視するための報告である。
報告が全部済むと、理事らによる意見交換の時間となる。職務執行状況に不満があれば、ここで表明できたはずだ。
だが、この頃になると、もう記者ブリーフィングまで5分ぐらいしか残っていないことも少なくなかった。ある元理事は、「意味のある意見交換はほとんどなされなかったと私は認識している」と振り返る。
本来、理事らには「一般法人法」に基づき、ほかの理事や職員が不正を働かないよう内部統制システムを構築し、運用する義務があった。具体的には、理事会で実効性のある内部統制システムを審議・決議し、会長ら職務執行者が適切に運用しているかを監視することが求められていた。しかし、理事の多くが自己主張を控え、存在感を消していた。
多くの企業にとって対岸の火事ではない。組織委の理事会のように、追認機関に成り下がっている取締役会が少なくないのが実情だ。
スルガ銀の取締役会にそっくり
女性専用シェアハウス「かぼちゃの馬車」の運営会社の経営破綻をきっかけに、18年に多額の不正融資が発覚したスルガ銀行も、その一社だった。
「取締役会において議案が否決されたり、修正されたり、差し戻しとなったことはない。すべての議案が原案のまま承認可決されている」「取締役会が実質的に議論をし、物事を決めていく場ではなかったと評価せざるを得ない」。スルガ銀行の不祥事を調査した第三者委員会は、現場で不正が横行していることを察知できなかった取締役会を、報告書でこう断罪した。
取締役会は一方的に職務執行状況の報告を受けたり、議案を提示されたりするのではなく、取締役会側から能動的に報告を求める事項を指定したり、審議すべき議案を話し合って決めたりすべきであると第三者委員会は提言した。また毎回短時間で終わらせていた取締役会を延長し、審議に必要な時間を十分確保することも提案している。組織委の理事会もこうした措置を取っていれば、不正のリスクを減らせたに違いない。
名ばかりの意思決定機関は、決議の作法も変えねばならないだろう。そうした会議体では、議長が「ご異議ありませんか?」と問うて決議をとることが多い。すかさず理事や取締役の一部が「異議なし!」と叫んで承認可決する。意思決定方法としては一般的であり、組織委の理事会も例外ではなかった。
歌舞伎のような会議
問題は100回、500回、1000回と、何回決議を繰り返しても「異議なし!」という声しか上がらず、必ず原案通り承認可決している場合だ。このような会議体は、歌舞伎と一緒ではないだろうか。歌舞伎では役者が見えを切った時などに、観客が「成田屋!」「12代目!」などと叫ぶならわしとなっている。歌舞伎独特の様式美を崩さないためにも、掛け声は屋号や代数などに限られることが事実上決まっている。
同様に、原案に対して「異議なし!」と叫ぶことが決まっているような意思決定プロセスは、芝居に等しい。そうした体質の会議体に名を連ねる社会的地位の高そうな人々は、舞台の見栄えを良くするための役者だとの指摘は厳しすぎるだろうか。
逆に役者としての立場をわきまえずに、「異議あり!」などと、筋書きにないことを口にすると、それは会議を仕切る議長への挑戦になる。組織委のような団体の理事会であれば会長、民間企業の取締役会であれば社長か会長というように、組織の最高権力者が議長を務めることがほとんどだ。あなたが最高権力者の率いる会議体のメンバーだったら、どう振る舞うだろう。
「私なら、相手がどんなに偉くても立ち向かえる」と思っているのであれば、それは幻想かもしれない。長い進化の過程で、権威に従って組織的に動くことができる集団が生き残ったとされる。その子孫である私たちの心に潜む「服従本能」にあらがうには、相当の覚悟が求められる。
元公安警察のなれ合い防止法
「なれ合いの防止には、メンバーの定期的な入れ替えが有効だ」と語るのは、警視庁公安部出身で、在外公館の警備も手掛けたセキュリティー・コンサルタントの松丸俊彦氏である。「施設警備の現場では、警備員の顔ぶれが長く固定化されると、夜間の見回りなどを省いたりし始める恐れがある」と、人事ローテーションの重要性を訴える。「ただ一度に全員を異動させると、マニュアル化しにくいノウハウが失われるので、在籍期間が長い警備員から順次異動させるのが好ましい」と助言する。
「マニュアル化しにくいノウハウ」とは、例えば警備員2人でクレーマーに対処するのが望ましい場面であったとしても、2人がクレーマーにつきっきりになると、ほかの場所の警備が手薄になるケースがある。この場合、1人でクレーマーに対処し、待機中の警備員1人をクレーマー対応の応援として呼ぶといった、ケース・バイ・ケースの変則的な警備方法を指す。
マニュアル化できないノウハウを見極め、その知見が失われない範囲で人事ローテーションを組むという警備の眼目は、そのまま一般的な職場の不正防止策にも適用できる。(日経ビジネス 吉野次郎)