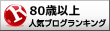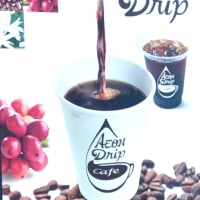神社仏閣にある古文書は字も今風でないので、素人が見ると、何が何だかさっぱり判らない。
そこのところをHくんは、相当な修練をへているから読解することができるのである。
道端にある道祖神とか、地蔵さんのかすかな彫ってある年代なぞもわかるはずなのだ。
古文書については、私はさっぱり、落ち着いて一字一字吟味するという根気がないのだ。
ひとつひとつ、じっくり解明しようとする心の平静さがとても及ばないんです。
そのHくんが平安末期の記録文学、鴨長明の方丈記について教えてくれた。
こういうの、高校ぐらいで習ったと思うのだが、昔のことで記憶がない。
方丈記というのは、一丈四方のあずまやに起居して、日常の様子を書き留めていた。
平安時代の大地震の酷いありさまが克明に書かれていて、地震学のうえからも貴重な文章らしい。
京都の下賀茂神社(昔、鴨神社といったものか)の神官の家系の出身だそうである。
鴨という名は、新羅か高句麗か、とにかく朝鮮渡来のその昔は先進知識を持った帰化人だったはずなのだ。
その鴨長明(ながあきらというらしい)が、屈折した人生のなかで無常観に浸りながら記録文学を書き残したのだとか。
フィクションではなくて、ありのままの昔語りというのは、Hくんに聞いた範囲だけでも面白いかなと思うのでした。
いずれそのうち、図書館ででも、そういうのを探してみることとするか。