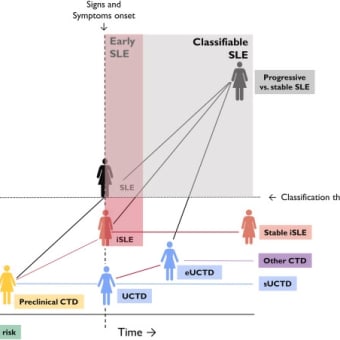認知症の予防、介入、ケア:ランセット常設委員会の 2024 年報告書
Lancet 2024; 404: 572-628
未治療の視力低下
眼鏡が必要となるような一般的な視力障害を含め、50 歳以上の成人における回避可能な視力低下と失明の世界的有病率は 12.6%と推定され、有病率は高所得国よりも低中所得国の方がはるかに高い。この有病率は、通常アルツハイマー病が原因であるが、しばしば眼疾患と誤診される後皮質萎縮症による皮質盲とは異なる。当委員会はこれまで、視力低下を認知症の危険因子とは考えてこなかったが、新たな証拠がかなり出てきた。
たとえば、3.7~14.5 年の追跡調査を行った 14 件の前向きコホート研究についてのメタ解析 (ベースライン時に認知機能に異常のなかった高齢者 6,204, 827 人を対象とし、そのうち 171,888 人が認知症を発症した) では、視力低下は、認知症のプールリスク比 1.47(95%CI 1.36-1.60)と関連していた (図 8)。
図 8. 視力障害のある人の視力障害がない人に対するあらゆる原因による認知症のリスク比についてのメタ分析
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)01296-0/fulltext?dgcid=twitter_organic_infocusbrainhealth_lancetdementia24_lancet#fig8
また、45,313 人が参加した 12 件の前向きコホート研究のメタ解析では、13,350 人が認知障害を発症し、視力喪失と将来の認知障害のリスク比は1.35(1.28-1.41)であった。
2 件目のメタアナリシスでは、視覚喪失に伴うあらゆる原因による認知症リスクの増加(RR 1.38, 95%CI 1.19-1.59, n=37,705)が同定された。眼の状態別にみると、認知症リスクの増加は、白内障(3 研究、6,659 人、1,312 例、HR 1.17, 95%CI 1.00-1.38, I2=0-0%)と糖尿病性網膜症(4 研究、43,658 人、7,060 例、1.34, 1.11-1.61; I2 = 63.9%)で認められたが、緑内障(6 試験;175 ,357人;44,144 症例;0.97, 0.90-1.04; I2 = 51.5%)や加齢黄斑変性症(3 試験;7,800 ,692 人;2,559 症例以上、正確な数は不明;1.15, 0.88-1.50; I2 = 91.0%)には認められなかった。
16,690 人の参加者を対象とした米国のある研究では、2020 年のランセット委員会に基づくライフコースモデルに、修正可能な潜在的危険因子として視力低下を追加することを検討し、その集団における視力障害の人口寄与割合(population attributable fraction: PAF)は 1.8%であったと報告している。視力喪失の有病率は非ヒスパニック白人集団よりもマイノリティ集団の方が高いため(非ヒスパニック黒人 3,660 人の9.9%、ヒスパニック 1,880 人の 11.0%に対して、非ヒスパニック白人 11,011 人の 7.7%)、これらの集団ではリスクも潜在的利益も大きくなる可能性がある。
この解析では、年齢、人種、APOE 遺伝子型、学歴、喫煙、および広範な併存疾患のリストが管理され、白内障摘出術を受けた人は、受けていない人に比べて認知症リスクが有意に減少したことが報告されている(HR 0.71, 95%CI 0.62-0.83、23,554 人年追跡)。300,823 人を対象とした UK Biobank 研究では、白内障の人は認知症リスクが高い(1.21, 1.01-1.46)と報告されているが、白内障手術を受けた人と健常対照者との間に認知症リスクに差はなかった。
これらの関連性の背後にあるメカニズムは、認知症の危険因子である糖尿病などの基礎疾患、視力低下そのもの、あるいは網膜と脳の両方における神経病理学的プロセスに関連している可能性がある。6,029,657人を対象とした韓国の縦断的健康保険データベース研究では、認知症リスクは視力喪失の重症度とともに増加することが報告されており、視力喪失それ自体が原因であるか、あるいは視力低下の原因となっている因子に対する用量反応効果があるのではないかという仮説が支持されている。糖尿病網膜症と認知症の関連を検討した研究では、糖尿病網膜症が 5 年以上経過した後、長期的な血糖値と腎機能で測定される糖尿病の重症度を調整しても、網膜症と認知症の関連は残ることが確認された。
未治療の視力低下と認知症リスクとの関連、および治療による改善の可能性を支持する証拠が増えている。したがって、本分析では視力低下を危険因子として含めた。しかし、世界中で、特に低中所得国では、視力低下はしばしば治療されていない。視力低下の治療は認知症予防につながり得る。
多要素認知症予防研究
多領域介入は、健康関連および行動の変化を通じて複数の認知症リスク因子に対処するものであり、原則として多因子性の状態に適している。これらの介入は、個人的な目標設定やデジタルプラットフォームやモバイルアプリと連動したものから、グループ活動に基づいたものまで、そのアプローチは様々である。2021 年のコクラン・レビューでは、認知症や認知機能低下の予防のための多領域介入に関する 9 件の RCT が同定され、18,452 人が参加している。特に APOE ε4 遺伝子型を有する人において、マルチドメイン介入による全体的な認知機能に対するわずかな有益性(複合 Z スコアの平均差 0.03, 95%CI 0.01~0.06, 3 件の RCT, n = 4,617, 追跡期間 18~36 ヵ月)が高い確度で認められた(保因者の平均差 0.14, 0.04~0.25; 非キャリアの平均差は 0.04, -0.02~0.10;2 件の RCT;n = 2,043;追跡期間 24~36 ヵ月)が、認知症発症に対する効果は信頼区間に幅があった(RR 0.94, 95%CI 0.76~1.18;2 つのRCT;n = 7,256;追跡期間 6~13 年)。 心血管危険因子を扱った DIVA 以前の試験(追跡期間中央値 10.3 年[IQR 7.0-11.0]、ベースライン時年齢 70-78 歳の参加者)でも、認知症発症に関して同様の結果が示された。さらに最近、Age Well 試験では、年齢、性別、生年月日、身長・体重、血清コレステロール、収縮期・拡張期血圧、身体活動状況、教育年数を組み込んだ認知症リスクカリキュレーターのスコアが平均より高い成人 1,030 人をドイツで募集した。介入には、栄養と服薬の最適化、身体的・社会的・認知的活動などが含まれ、参加者とともに個別の目標が設定されたが、一般的な健康アドバイスを受けた対照群と比較して、24 ヵ月間の認知機能に対する効果はみられなかった。研究者らは、介入は十分に的を絞ったものではなく、強度も十分ではなかったと結論づけた。SMARRT 試験では、ヘルスコーチングとナースビジターによる 2 年間の個人的なリスク低減目標(70〜89 歳の成人 172 人)が評価された。この介入により、複合認知スコアが改善し(平均治療効果は標準偏差 0.14, 95%CI 0.03-0.25)、認知症リスク低減に関する情報を含む健康教育対照と比較して 74%の改善がみられた。
MCI に対する多領域介入に関するシステマティックレビューとメタアナリシスでは、MCI の高齢者(n = 2,711)において最大 1 年間継続した非薬理学的多領域介入に関する 28 件の RCT が発見され、単一介入のアクティブコントロールと比較して、実行機能と記憶の改善を伴う、グローバル認知に対する中等度の効果(標準化平均差 0.41, 95%CI 0.23-0.59, I2 = 62%)が認められた。MCI 患者を対象としたライフスタイルに関する RCT の小規模なシステマティックレビューでは、3 件の小規模な RCT(n = 156)のみであり、異質性が低く認知機能に対する有意な有益性が報告されている。
システマティックレビューによると、マルチドメイン(すなわち、2 つ以上のドメイン)介入に関する 4 つの大規模試験の適格者の 10 年認知症リスクは、不適格と判断された者の 10 年認知症リスクと同程度であった。
行動変容を支援する介入コーチ、デジタル配信による個別化され計測可能な自己管理介入、社会経済的地位の低い人々や低中所得国の人々を対象とした介入など、介入の有効性やアドヒアランスを高めるための戦略を用いた研究もある。これらの研究により、既存の試験で報告された認知的ベネフィットを再現または増加させることができるかどうか、また、マルチドメイン介入が認知症予防において計測可能で臨床的に有意である可能性が高いかどうかが明らかにされるべきである。確認された認知的有益性が介入中止後も持続可能かどうか、認知症発症の減少につながるかどうか、低所得の設定や高リスクの集団において同様のアドヒアランスと有効性をもって実施できるかどうかは、現在のところ不明である。
認知症予防のための多領域介入試験のレビューによると、42 試験中 26 試験(62%)しか民族データが報告されておらず、その中で非白人少数民族の参加者の割合はわずかであった。白人は 23 試験で報告され、黒人またはアフリカ系アメリカ人は 15 試験で報告され、アジア人は 6 試験で報告され、アメリカンインディアンまたはアラスカ先住民は 3 試験で報告され、ハワイ先住民または太平洋諸島民の人種は 1 試験で報告された。FINGERS 試験では、民族や認知症発症率は報告されていないが、認知機能に対する介入の効果は、(かなり裕福なコホート内ではあるが)社会経済的カテゴリーにかかわらず同じであったと報告されている。HATICE 研究(すなわち、インターネットベースで、コーチが支援する目標設定アプローチ)の参加者 2,700 人のうち 61 人(2%)を除く全員が白人であった。結果は民族別に集計されていないが、介入の効果は、ベースラインの教育到達度が最も低い人で最大であった。
総じて、効果が緩やかな介入であっても、理論的には、裕福でない人や低所得の環境にいる人を含む集団レベルでは実質的な予防効果をもたらす可能性がある。個人への介入や複数のリスクに対する介入は費用対効果が高い可能性があるが、一般化は困難であり、持続的な効果を得るためには介入を間隔を空けて繰り返す必要があるかもしれない。
PAF 計算
高 LDL コレステロール血症と未治療の視力低下という 2 つの新しい危険因子と、以前のモデルにあった 12 因子を認知症のライフコースモデルに組み込んだ。危険因子の有病率とリスク比については、世界的に最大かつ最新のメタアナリシスを用いたか、入手できない場合は最良のデータを用いた。出典と根拠は付録に詳述されている。本論文で既に述べたうつ病と難聴のリスク比については、新たにメタアナリシスを行った。
ノルウェーの Nord-Trøndelag 県の 20 歳以上の住民を対象とした縦断的な集団ベースの健康研究である HUNT 研究の 45 歳以上の全参加者 37,000 人のデータを用いて、14 の危険因子の communality(すなわち、危険因子のクラスタリング)を推定した。付録には、PAF の計算式、危険因子の定義、communality と PAF を計算する Stata コードを含む手順が示されている。我々の分析では、5 つの主成分が同定され、14 の危険因子間の全分散の 54%を説明し、危険因子の有病率にかなりの重複があることを示した。14 の危険因子すべての PAF は45.3%と推定された。
図 9 は、潜在的に修正可能な 14 の認知症リスク因子のライフコースモデルを示している。
図 9. 潜在的に介入可能な認知症危険因子の人口寄与割合
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)01296-0/fulltext?dgcid=twitter_organic_infocusbrainhealth_lancetdementia24_lancet#fig9
表 1 は、潜在的に修正可能な 14 の認知症危険因子すべてについて、有病率、communality、リスク比、communality で調整した重み付けなしおよび重み付けした PAF を示したものである。
表 1. 潜在的に修正可能な 14 の認知症リスク因子毎のリスク比、有病率、人口寄与割合
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)01296-0/fulltext?dgcid=twitter_organic_infocusbrainhealth_lancetdementia24_lancet#tbl1
長所と限界
本論文は、認知症の潜在的に修飾可能な危険因子に関する PAF のこれまでで最も包括的な分析であり、説得力のあるエビデンスを持つ危険因子を新たに組み込み、危険因子のリスク比と有病率の世界的な推定値を更新して、これまでの計算を更新したものである。選択基準には常にある程度の主観性があり、結論に影響を与える可能性があるため、透明性を確保するために、選択基準の根拠となるエビデンスを提示した。リスクの大きさについては、現時点で最良のエビデンスを用いたが、このエビデンスがリスクを過大評価または過小評価している可能性もある。選択したリスク因子についてはシステマティックレビューを使用し、14 のリスク因子については communality を計算するためのデータを特定し、統合に必要な場合には新たなメタアナリシスを提供した。最近のレビューがなかったためうつ病と難聴についてのみ新しいメタアナリシスを行ったが、そのためいくつかの新しいエビデンスを見落とした可能性がある。これらの分析の実施方法については詳述したが、事前登録はしていない。認知症の半数近くが 14 の潜在的に修正可能な危険因子と関連していると推定され、希望に満ちた結果であった。
しかし、危険因子の有病率は国によって異なるというエビデンスが含まれている。ほとんどの世界的な研究は高所得国からのものであるため、低中所得国はデータが乏しく、十分な報告がなされていない。我々は、危険因子が認知症を引き起こすと仮定し、これらの危険因子を変化させることで、 認知症の有病率を変化させる可能性があるという追加的なエビデンスを含めた。エビデンスが一貫していないリスクは含めず、他のリスク因子が存在することを認めた。リスク因子と保護因子が、どのように国家内および国家間で集まったり変化したりするかについてのエビデンスは乏しい。HUNT 研究の参加者は、アルコール乱用の有病率が世界的な数値よりも低く、民族的多様性の少ない高所得国に住んでいた。さらに、LDL コレステロールの有病率に関する世界的な推定値を見つけることができず、単一のコホート研究からの推定値を使用することが理想的でないことを認めた。多くの危険因子は社会経済的貧困と関連している。例えば、人々がどこに住んでいるかは大気汚染への曝露と関連しており、また、歩いて行ける範囲に手頃な価格の健康的な食品があり、それを調理する資源と技能があるかどうかは肥満と糖尿病と関連している。社会経済的貧困 (Socioeconomic deprivation) は教育と強く関連しており、それを communality の計算に組み入れることで、個々の修正可能な要素を考慮することによる個々の影響を減らすことができる。大気汚染に関するデータは一貫して認知症のリスクであることを示唆しているが、メタ解析はできなかった。
さらに、あるリスクに長くさらされればさらされるほど、その影響は大きくなること(糖尿病など)や、リスクが一般集団よりも脆弱な人々に強く作用すること(大気汚染など)を示す証拠もある。従って、リスクのあるすべての人々にとって最善の方法で既存の病態を治療する努力を増やすことが重要である。しかし、このようなリスク修正は集団に影響を与えるが、どの個人も認知症を避けられるという保証はない。さらに、コミュニティや複数のリスクを抱える人々について考えることは極めて重要であり、そのような人々に対しては、個別の治療や行動変容の促し以上のアプローチが、長期的にはより大きな効果をもたらす可能性がある。変化をもたらすために介入に必要な期間や強度は不明であるが、喫煙に関連するリスクは長期的に減少させることが可能であり、実際に喫煙率の減少は、ある集団で見られる認知症有病率の減少に関連する要因の一つであるかもしれない。関連は因果関係ではないが、多成分介入、補聴器の提供、高血圧治療を評価した RCT で見られた認知への効果、および大気汚染、喫煙、社会的接触の減少、聴力・視力治療、仕事による認知刺激の増加にともなう認知症発症率の低下は、認知症の臨床的発現との因果関係を示唆し続けている。低中所得国でも高所得国でも、社会経済的地位の低い人々は、他の人々よりもリスクが高く、優先的に介入されるべきである。認知症の遺伝的リスクが高いかどうかにかかわらず、危険因子を減らすためのライフスタイルや政策の変更が重要であることを示すかなりの証拠が存在する。我々は、これまで紹介した文献に基づき、我々の提言を強調するために重要な点を要約した。リスクに対する理解には大きなギャップがあるが、認知症発症の可能性を減らす方法はあり、それは個人、家族、社会に利益をもたらすものであるため、行動は待ったなしである。
公衆衛生的アプローチ
認知症は公衆衛生の主要な課題であるが、公衆衛生の視点は認知症予防に対する極めて斬新なアプローチである。リスクは個人が変えられるものとして概念化することができるが、公衆衛生的アプローチは、社会経済的困窮に関連する不健康のライフコース的発生を認識するものである。教育への不平等なアクセス、健康的で安全な環境への不平等なアクセス、劣悪な職業環境などのリスク不平等の原因を理解することで、介入策の人口到達率、費用対効果、健康の公平性を最大化するための社会的条件の変化を促すことができる。心血管系の健康と喫煙は、社会経済的困窮と認知症との関連を部分的に媒介するので、ライフコース、身体活動、禁煙、肥満の原因とならず健康的な食事(これは糖尿病にも影響する)を支援する集団レベルのアプローチは、認知症有病率の不平等に大きな影響を及ぼすと予想される。
これらの危険因子の変化とその後の認知症リスクの減少との関連を証明することは、認知症リスクが生涯にわたって蓄積されるため困難である。また、認知症を発症する前に現れる病理学的変化も長い時間をかけて蓄積されるため、違いを示すには何年も何十年も研究が必要である。もう一つのアプローチは、認知症有病率の減少につながる因果関係を仮定して、リスク(および保護)因子を代理アウトカムとして使用することである。準実験的研究のような他の研究デザインも、認知症リスクに対する危険因 子の低減の効果を明らかにする可能性がある 。集団レベルの介入は、文化的・経済的背景に合わせて適切に行うことができ、理論的には認知症有病率、不平等、システム全体のコストを大幅に低減する ことができる。これらの介入策には、健康的な食品を購入しやすくするための補助金や、アルコール、タバコ、不健康な食品を購入しにくくするための課税などの財政政策、製品のリサイクルを奨励するための課税、継続教育やよりクリーンな燃料に対する経済的障壁の除去などがある。例えば、不健康な製品の広告にさらされる機会を減らしたり、社会文化的規範を転換させるようなマスメディア・キャンペーンをうまく利用したりすることである。法律や利用可能な政策としては、公共の場での禁煙、アルコールの販売時間の短縮、健康的な食品を現在よりも入手しやすくする、ファーストフード店の密度を下げる、安全で質の高い緑地やアクティブな移動のインフラを提供する、職場における騒音暴露の低減と聴覚保護具の提供、大気汚染を減らすための低排出ゾーン、アクティブな移動やスポーツにおけるヘルメットの使用の義務化などがある。WHO の『Global Age Friendly Cities Guide(高齢者に優しい世界都市ガイド)』 で推奨されているように、都市計画、アクセシビリティ、インフラを最適化することで、運動や社交を利用しやすく安全なものにす ることができる。喫煙、過度のアルコール摂取、肥満、高血圧、大気汚染、頭部外傷に効果があるとされる介入策を、認知症への影響についてモデル化したところ、すべてコスト削減と生活の質の改善が見られた。
モデルに含めるにはエビデンスが不十分な潜在的危険因子
他にも修正可能な危険因子が存在することは分かっており、これらの因子をいくつか検討したが、バランスから見て、修正可能な危険因子として含めるための高い基準を満たすだけの一貫したエビデンスが存在しないと判断した。これらの危険因子には、睡眠不足、不健康な食事、感染症、精神状態が含まれる。
睡眠
2020 年のランセット委員会で議論したように、睡眠時間が短い(すなわち、通常 5 時間以下と定義される)、または長い(すなわち、通常 10 時間以上と定義される)ことが、認知機能低下や認知症のリスク増加と関連しているのか、あるいは認知症を発症している人が前駆期に睡眠障害を起こしているのかは不明である。 2 つのメタアナリシスでは、睡眠時間の長さについて様々な定義を用いた研究が含まれており、短時間は 7 時間以下、長時間は 8 時間以上であることが多く、認知症発症までの追跡期間が 10 年未満であることから、睡眠時間と認知症リスクとの逆 U 字型の関連という知見は、逆因果バイアスの可能性がある。
いくつかの研究は、長期間の追跡調査を行っている点で注目に値するが、睡眠時間の把握後すぐに認知症を発症した人のデータと、睡眠測定が記録された時点から 5~10 年後に認知症を発症した人のデータを別々に報告した研究はない。逆因果仮説は、健康な成人 3893 人を対象とした縦断的脳 MRI 研究によって支持されている。この研究では、BMI、社会経済的状態、気分をコントロールした場合、脳萎縮率は睡眠時間の長さ(すなわち、 7 時間以上)、短さ(すなわち、7時間以下)、睡眠の質のいずれとも関連しなかったと報告している。しかし、横断的には、睡眠時間は皮質の厚さと関連しており、著者らは健康な脳が健康な睡眠時間を支えていることを示唆している。
830,716 人 の女性(ベースライン時の平均年齢60.0歳[SD 4.9])を 17 年間追跡調査した Million Women 研究では、睡眠時間が 7-8 時間と報告した人よりも、睡眠時間がやや短い(すなわち、7 時間未満)と報告した人の方が認知症のリスクがわずかに高かった(RR 1.08, 95%CI 1.04-1.12)。 Whitehall II 研究では、50歳、60 歳、70 歳において 6 時間以下の短時間睡眠が持続することは、通常の睡眠時間が持続すること(すなわち、7 時間)と比較して、社会人口統計学的、行動学的、心臓代謝学的、精神衛生的要因とは無関係に、認知症リスクが 30%増加することと関連していた。
シフト勤務は、通常の勤務日以外に働くことがあるため、概日リズムを乱し、心血管疾患やその他の疾病のリスクを高める可能性がある。その後の UK Biobank 研究では、シフト勤務が認知症に関係するかどうかを検討し、170,722 人を中央値 12.4 年間追跡調査し、そのうち 27,450 人(16.1%)がシフト勤務をしていた(ベースライン時の平均年齢はシフト勤務者で 52.8 歳[SD 7.1]、非シフト勤務者で 51.8 歳[SD 7.0])。交代勤務は認知症リスクの増加と関連していた(HR 1.30, 95%CI 1.08-1.58)。ただし、検出力は低いものの夜勤者は日勤者よりリスクは高くなかった。
65 歳以上の 28,775 人を対象としたスウェーデンのコホートでは、13 年間の追跡調査における長時間睡眠(すなわち、9 時間/夜を超える睡眠)と認知症との間の関連は、追跡調査の最初の 5 年間に発生した症例を解析から除外した後に完全に減弱し、逆因果バイアスの影響が大きいと結論された。同様に、米国の Million Women 研究では、最初の 5 年間の追跡調査後、長時間睡眠(すなわち、8 時間以上)または日中の昼寝と認知症との間に関連は見られなかった。UK Biobank のメンデルランダム化研究では、習慣的な昼寝と脳容積の増加(非標準化 β 15-80 cm3, 95%CI 0.25-31.34)との間にわずかな関連は見られたが、海馬容積や認知機能検査では差は見られなかった。
睡眠時間とともに、睡眠の質、特に睡眠時無呼吸が認知症と関連する可能性を示唆する新たなエビデンスがある。最長 14~9 年間追跡調査された 1,333,424 人を含む 11 件の研究のシステマティックレビューとメタアナリシスでは、睡眠時無呼吸の人は認知症発症リスクが高いことが確認されている(HR 1.43, 95%CI 1.26-1.62) 。睡眠時無呼吸症候群の人に認知症に関するスクリーニング質問を実施することを検討する価値があるかもしれない。
睡眠時間とともに、睡眠の質、特に睡眠時無呼吸が認知症と関連している可能性を示唆する新たなエビデンスがある。最長 14~9 年間追跡調査された 1,333,424 人を含む 11 件の研究のシステマティックレビューとメタアナリシスにより、睡眠時無呼吸の人は認知症発症リスクが高いことが明らかになった(HR 1.43, 95%CI 1.26-1.62)。睡眠時無呼吸症候群の人に認知症に関するスクリーニング質問を実施することを検討する価値があるかもしれない。
睡眠障害は、いくつかの過程を経て認知症リスクを増加させると仮定されている。睡眠障害は、認知症リスクに影響する他の疾患(例えば、糖尿病、うつ病、アルコール摂取)と併発することが多い。さらに、睡眠障害のある人はベンゾジアゼピン系薬剤による治療を受けている可能性があり、それが認知機能の低下に関係している可能性もある。あるシスシテマティックレビューとメタアナリシスでは、ベンゾジアゼピン系薬剤を服用している人において認知症リスクが増加するという非常に質の低いエビデンスが、追跡期間が 72~264 ヵ月に及ぶ 11 件の研究において確認されている(OR 1.38, 95%CI 1.07-1.77, I2 = 98%, n = 980,860)。ある前向きコホート研究では、ベンゾジアゼピン系薬剤の服用量が少ない人では、服用量が多い人と比べてリスクが高いことが報告されており、この関連は因果関係ではないことが示唆されている。実験的研究では、一時的な睡眠不足が直後の認知能力に有害な影響を及ぼすことが支持されている。
睡眠不足と認知機能低下を関連づける生物学的メカニズムとしては、神経炎症、アテローム性動脈硬化症、α-シヌクレイン病変(レビー小体型認知症やパーキンソン病性認知症など)、睡眠時間が短くなることによるアミロイド β のクリアランス障害などがある。 また、アミロイド β の蓄積と、認知的に健康な成人における概日リズムや睡眠パターンの乱れとの関連性を示す証拠もいくつか存在する。
2020 年のランセット委員会以来、認知症やその前駆症状は睡眠時間の延長を引き起こすかもしれないが、睡眠時間の延長は認知症の危険因子ではないことが、さらなる証拠によって示されている。認知症リスクを低減するために睡眠を抑制すべきではない。ベンゾジアゼピン系薬剤は認知症の原因とはならないようである。
総じて、睡眠時間が短いと認知症のリスクがわずかに上昇することを示す証拠があるようである。 しかし、短時間睡眠が認知症発症リスクに与える影響についてのエビデンスは乏しく、睡眠の長さよりもむしろ認知症発症リスク上昇に関連する因子である可能性のある睡眠の質や概日リズム障害に関する情報は存在しない。そのため、短時間睡眠に関するエビデンスは、因果関係を確信できるほど明確になっていない。我々は、危険因子としての睡眠について推奨することはできない。
食事
先に述べたように、栄養と個々の食品の認知機能への影響についての研究は難しく、認知や認知症との関連については矛盾した結果が得られている。食事は健康的なものから不健康なものまで様々なタイプの食品や飲料を含み、多くの場合、生活習慣の一部であるため、観察された影響は生活習慣に関連するものかもしれないし、生活習慣とは無関係のものかもしれない。
地中海食に類似した食事には、DASH(Dietary Approaches to Stop Hypertension)食や、地中海食に特定の健康食品を加えた MIND(Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay)食がある。2019 年、世界保健機関 (World Health Organization: WHO) は認知症リスク軽減のために地中海食の条件付き推奨を行ったが、これは望ましい効果と望ましくない効果のエビデンスのバランスについて確信が持てないという意味であった。あるシステマティックレビューとメタアナリシスでは、追跡期間が 2.2 年から 41 年の 16 件のコホート研究が特定された。食事の質が高いことは低いことと比べて認知症リスクの低下と関連していた(RR 0.82, 95%CI 0.70-0.95, n = 66,930, 12 研究)。このリスクは、10 年以上追跡した研究(0.78, 0.62-0.99, 6 研究)またはアルツハイマー病という結果に限定した場合(0.61, 0.47-0.79, 6 研究)でも同様であった。対照的に、連続的な地中海食スコアを用いた研究では、地中海食のアドヒアランスと認知症リスクとの間に有意な関連は認められなかった。その後、224,049 人の参加者を対象とした3 つのコホート研究の大規模なメタアナリシスにより、MIND 食スコアの遵守率の増加が認知症リスクの低下と関連することが確認された(3 ポイント増加ごとに HR 0.83 [95% CI 0.72-0.95], I2 = 0%)。第 3 のシステマティックレビューでは、21 研究中 10 研究において、グローバルな認知機能低下に対する地中海食の予防効果が報告され、8 研究中 3 研究において認知症の発症に対する予防効果が報告され、4 研究中 2 研究においてアルツハイマー病に対する予防効果が報告された。
これらのレビュー以降、中年期の 28,025 人(すなわち、最初の評価時の平均年齢 58.1 歳 [SD 7.6]、追跡調査期間中央値 19.8 年 [IQR 4.8])を対象としたスウェーデンの前向きコホート研究では、食事に関する推奨事項の遵守も、修正地中海食(すなわち、伝統的な地中海食に基づくが、文化的差異に対応するためなどに調整された食事)の遵守も、認知症、アルツハイマー病、血管性認知症、またはアルツハイマー病の病像のリスクを減少させなかったことが報告された。これらの結果は、ベースライン後の 5 年間に認知症を発症した人を除いても変わらなかった。対照的に、UK Biobank 研究(n = 60,298, ベースライン時の平均年齢 63.8 歳 [2.7]、平均追跡期間 9.1 年 [1.7])では、APOE の状態とは無関係に、地中海食のアドヒアランスが高いことは、アドヒアランスが低いことと比較して認知症リスクの低下と関連することが報告されている。高齢者を対象とした米国のコホート研究(n = 581, 初回評価時の平均年齢 84.2 歳 [5.8])では、MIND と地中海食のパターン、特に緑葉野菜の摂取が、死後のアミロイド β 負荷、リン酸化タウのもつれ、アルツハイマー病の病態と逆相関していたことが報告されている。
超加工食品 (ultraprocessed food) とは、加工食品物質 (food processed substance)(すなわち、油脂、糖類、デンプン、タンパク質分離物)を配合したもので、食品 (whole food) をほとんど、あるいはまったく含まないものである。定義が曖昧なため、食品の分類は様々である。60 歳以上の参加者 3,632 人を対象とした米国の横断研究では、交絡因子で補正した後、全体的な認知能力および記憶力は、1 日の食事エネルギー摂取量のうち超加工食品からの割合とは関連しなかったと報告している。ブラジルで行われた縦断的研究(n=10 775;ベースライン時の平均年齢 51.6歳[SD 8.9];追跡調査期間中央値 8 年[範囲 6-10])では、関連する社会人口統計学的変数および臨床的変数で調整した後、超加工食品の摂取量が最高四分位値から四分位値までの 3 段階にある人では、最低四分位値の人に比べて、全体的な認知機能の低下速度(β -0.004, 95%CI -0.006~-0.001)が 28%速く、実行機能の低下速度(β -0.003, -0.005~0.000)が 25%速いことが報告された。これらの研究は、逆因果バイアスを除外するのに十分な期間ではない。
フランスの研究(n = 1,279, ベースライン時の平均年齢 74.3 歳[SD 4.9]、追跡期間 17 年)では、血漿中のオメガ 3 インデックス濃度の上昇が認知症リスクの低下(1 SD に対して HR 0.87[95%CI 0.76-0.98])と関連し、内側側頭葉容積の減少が少なかったことが報告されている。
腸内マイクロバイオームには、腸内のすべての微生物が含まれる。腸内細菌叢の変化は、加齢や肥満、食事、感染症、心血管疾患、睡眠の問題、運動不足の結果として起こる。マイクロバイオームの変化は、食事が脳に及ぼす影響を媒介し、神経炎症や細胞死を促進し、認知症の危険因子となる可能性がある。
食事介入
食事介入の設計は、適切な量、形態、生活上のタイミング、期間が不明確であるため困難である。本稿で以前に概説した、実用性、倫理性、バイアスの観点からの長期 RCT における注意点は、食事介入については特に顕著である。欧州委員会は以前、WHO と同様に、ビタミンが一般集団における認知機能の低下を予防しないという説得力のあるエビデンスを明らかにした。それ以来、さらなる研究でも説得力のある有益性は得られていない。
認知障害はないが、認知症の家族歴があり、BMIが25より高く、食事が最適でない高齢者604人を対象とした食事教育介入(食事カウンセリングとMIND食または軽度カロリーコントロール食のいずれか)の3年間のRCTでは、全般的な認知および脳MRIの二次アウトカムに群間差はなかったと報告されている369。
COSMOS-MINDは、2262人のボランティア参加者(平均年齢72-97歳[SD 5-63])を対象とした、心血管COSMOS RCTにネストされた3年間のRCTである。この試験では、ココアフラバノールを含むココア抽出物(すなわち、一次分析)とマルチビタミンミネラルを別々に毎日摂取した。370 ココア抽出物(マルチビタミンミネラルのプラスまたはマイナス)は、全体的な認知に影響を及ぼさなかったが、マルチビタミンミネラルの補充のみでは、記憶と実行機能において、臨床的ではないが統計的に有意なわずかな全体的認知の利益(平均Zスコア0-07、95%CI 0-02-0-12)をもたらした。著者らは、観察されたマルチビタミンミネラルサプリメントの認知機能への有益性は、心血管疾患を有する高齢者では、そうでない高齢者よりも顕著である可能性があり、より多様なコホートでさらなる研究を実施すべきであると示唆した。それ以来、さらなる研究でも説得力のある有益性は得られていない。
認知障害はないが、認知症の家族歴があり、BMI が 25 より高く、食事が最適でない高齢者 604 人を対象とした食事教育介入(食事カウンセリングと MIND 食または軽度カロリーコントロール食のいずれか)の 3 年間の RCT では、全般的な認知および脳 MRI の二次アウトカムに群間差はなかったと報告されている。
COSMOS-MIND は、2,262 人のボランティア参加者(平均年齢 72-97 歳[SD 5.63])を対象とした、心血管 COSMOS RCT にネストされた 3 年間の RCT である。この試験では、ココアフラバノールを含むココア抽出物(すなわち、一次分析)とマルチビタミンミネラルを別々に毎日摂取した。ココア抽出物(マルチビタミンミネラルのプラスまたはマイナス)は、全体的な認知に影響を及ぼさなかったが、マルチビタミンミネラルの補充のみでは、記憶と実行機能において、臨床的ではないが統計的に有意なわずかな全体的認知の利益(平均 Z スコア0.07, 95%CI 0.02-0.12)をもたらした。著者らは、観察されたマルチビタミンミネラルサプリメントの認知機能への有益性は、心血管疾患を有する高齢者では、そうでない高齢者よりも顕著である可能性があり、より多様なコホートでさらなる研究を実施すべきであると示唆した。
認知障害はないが、認知症の家族歴があり、BMI が 25 より高く、食事が最適でない高齢者 604 人を対象とした食事教育介入(食事カウンセリングと MIND 食または軽度カロリーコントロール食のいずれか)の 3 年間の RCT では、全般的な認知および脳 MRI の二次アウトカムに群間差はなかったと報告されている。
COSMOS-MIND は、2,262 人のボランティア参加者(平均年齢 72-97 歳[SD 5.63])を対象とした、心血管 COSMOS RCT にネストされた 3 年間の RCT である。この試験では、ココアフラバノールを含むココア抽出物とマルチビタミンミネラルを別々に毎日摂取した。ココア抽出物(±マルチビタミンミネラル)は、全体的な認知に影響を及ぼさなかったが、マルチビタミンミネラルの補充単独では、記憶と実行機能において、臨床的ではないが統計的に有意なわずかな全体的認知の利益(平均 Z スコア0.07, 95%CI 0.02-0.12)をもたらした。著者らは、観察されたマルチビタミンミネラルサプリメントの認知機能への有益性は、心血管疾患を有する高齢者では、そうでない高齢者よりも顕著である可能性があり、より多様なコホートでさらなる研究を実施すべきであると示唆した。
COSMOS-WEB は、COSMOS-MIND と実質的に重複する COSMOS のサブセットであったが、ココアフラバノールを含むココア抽出物を投与する群とプラセボを投与する群に無作為に割り付けた人のみを調査し、ココア抽出物の介入では 1~3 年間にわたり記憶力が向上しなかったと報告している。認知症のない 60~80 歳の 206 人を対象としたアントシアニン(すなわち、ベリー類や果物に含まれるフラボノイドで、抗炎症作用、抗酸化作用、脂質プロファイルの改善作用があると考えられている)の 24 週間の RCT では、認知アウトカムに差は認められなかった。著者らは、認知機能低下の傾きに群間で差があったことから、この効果の欠如は検出力と期間が不十分であったためではないかと示唆している。
結論として、栄養疫学研究では、食事とバイオマーカー、認知機能低下、認知症、またはアルツハイマー病との関連を報告することが多いが、一貫していない。食事に関する研究はほとんどなく、野菜、ナッツ類、ベリー類、豆類、魚介類、全粒穀物を豊富に含む地中海食または類似の食事からなる高所得国の食事に焦点が当てられている。臨床試験では一般に、栄養および食事介入は認知障害を減少させないことが報告されている。介入結果は小規模で不均一であり、通常は有意ではなく、主要な仮説を支持するものではない。いくつかのサブグループで肯定的な結果が得られたことから、今後の調査結果が期待されるが、効果を示すには長期的な介入が必要であろう。
果物や野菜を多く摂り、超加工食品を控えた食事は、多くの健康状態によく、肥満、糖尿病、高血圧の認知症危険因子に影響を与えるが、この食事が認知症予防に直接役立つと言うには十分な証拠がない。幼少期の栄養不良の影響に関するデータについて不足している。
感染症および全身性炎症
個々の参加者データのメタアナリシスでは、入院を必要とする重度の (中枢神経系に限らない) 全身性感染症は認知症リスクの増加と関連しており、年齢、性別、社会経済的状態、健康行動、BMI、高血圧、糖尿病、APOE 遺伝子型で調整した後もその関連は持続した(HR 1.22, 95%CI 1.09-1.36)。 この結果は、年齢をマッチさせた入院していない対照群と比較して、感染症で入院した人では脳の脆弱性を示す脳の容積が小さく、白質の完全性が低いことで一部説明できるかもしれない。その後行われた英国の成人約 100 万人を対象とした電子登録研究によると、プライマリケアで治療を受けた人ではなく、入院に至った感染症のある人は、感染症のない人に比べて認知症やアルツハイマー病のリスクが高いことが示された。いくつかのウイルスや細菌が認知症リスクと関連しており、リスクは、感染症のない人や他のタイプの感染症のある人に比べて、中枢神経系感染症だけでなく中枢神経系外感染症でも高かった。Baltimore Longitudinal Study of Aging (n = 1009) では、症候性ヘルペス感染歴のある人では、白質萎縮の促進が観察された。しかし、別の研究では、単純ヘルペス感染と認知機能低下や脳萎縮との関連はないと報告されている。
敗血症、肺炎、下気道感染症、皮膚・軟部組織感染症、尿路感染症はすべて、ヒトおよび動物実験において認知症発症率の上昇と関連している。同様に、末梢の炎症マーカー濃度の上昇も認知症リスクの上昇と関連している: 10 件の研究のメタアナリシス(追跡期間は 2 年から 25 年)では、CRP 濃度が最も高い四分位の人は最も低い四分位の人よりも認知症リスクが高い(HR 1.34, 95%CI 1.05-1.71)ことが報告されており、IL-6 では 4 件の研究(1.40, 1.13-1.74)、ACT では 3 件の研究(1.54, 1.14-2.08)で同様の結果が得られているが、PAF アセチルヒドロラーゼ(1.06, 0.94-1.18)では同様の結果は得られていない。 炎症マーカー濃度の上昇も認知機能低下と関連している。
COVID-19 の長期的な影響に関する縦断的なエビデンスはほとんど存在せず、この分野のエビデンスは認知機能やバイオマーカーに対する COVID-19 の影響に関するものであり、認知症リスクに関するものではない。COVID-19 は認知機能障害のリスクを増加させる可能性があり、あるメタアナリシスでは、COVID-19 感染 7 ヵ月後のグローバル認知機能障害が、認知機能障害の既往歴のない健常成人対照群よりもわずかに多いことが確認されている(Montreal Cognitive Assessment score 平均差 -0.94, 95% CI -1.59 to -0.29)。さらに、SARS-CoV-2 に感染していない人と比較して、SARS-CoV-2 感染後 6 ヵ月後の UK Biobank 参加者785人において、灰白質の厚さと脳全体の大きさの減少が報告されている。COVID-19 はまた、人々の習慣を変化させることによって認知症のリスクを増加させた可能性がある。例えば、COVID-19 感染とパンデミックの後期は、感染していない人やパンデミックの初期に比べて、運動量の減少と肥満の高リスクに関連することが研究で示されている。
感染と炎症の影響のメカニズム
感染症が認知症リスクを高めるメカニズムは十分に理解されておらず、認知障害や認知症のある人は、認知症のない人よりも感染症により重篤な影響を受け、入院する可能性が高いという双方向性が考えられる。血液脳関門は脳を保護するが、血液脳関門を介した末梢免疫細胞浸潤の直接的な経路や、全身性炎症が中枢神経系ミクログリア機能を調節する間接的な経路など、末梢と中枢の免疫伝達には複数のメカニズムが存在する。動物実験や in-vitro の研究から、炎症刺激がミクログリアや末梢の CD4+ や CD8+ T 細胞を長期的にプライミングし、炎症亢進状態に導く可能性があることが示されている。
長期にわたる免疫活性化や全身性の炎症は、脳毛細血管にも悪影響を及ぼし、血液脳関門の透過性を高め、神経毒性のある血漿成分、血液細胞、病原体の脳への侵入に関連する可能性がある。
病院での感染症治療がアルツハイマー病よりも血管性認知症と強く関連していることから、そのメカニズムには血管炎症経路が関与している可能性がある。血液脳関門の機能不全は微小出血や血管周囲の浮腫と関連しており、微小循環を悪化させ虚血性障害を引き起こす。
ワクチン、抗炎症薬、抗生物質による介入
観察研究のメタアナリシスによると、狂犬病、破傷風、ジフテリア、百日咳、帯状疱疹、インフルエンザ、A 型肝炎、腸チフス、B 型肝炎の予防接種は、認知症リスクの低下と関連することが示唆されているが、この関連は、予防接種を受けている人は、受けていない人に比べて、健康行動が異なっていたり、医療へのアクセスが良好であったりする可能性があるため、交絡因子による部分もあるかもしれない。
あるシステマティックレビューとメタアナリシスは、感染と炎症を修正するために非ステロイド性抗炎症薬を用いた介入が、認知機能障害や認知症進行リスクの減少をもたらすという強力なエビデンスは、大規模 RCT からは得られなかったと結論づけた。アルツハイマー病に対する非ステロイド性抗炎症薬、例えばナプロキセンやセレコキシブを 1~3 年間、またはアスピリン 100 mg を 9~6 年間、アルツハイマー病の第一度近親者のいる高齢者(70 歳以上)に投与しても、認知症リスクは減少せず、またこれらの薬剤は有害事象を増加させた。ミノサイクリンは、試験管内およびアルツハイマー病の動物モデルにおいてアミロイド β の毒性作用から保護するテトラサイクリン系抗生物質であるが、多施設共同臨床試験において、軽度アルツハイマー病患者の 2 年間の認知機能障害の進行を遅らせることはできなかった。
予防接種、手洗い、換気などの感染回避に役立つ介入は、一般的な健康には良いが、認知症リスクへの影響は不明である。
歯科疾患
歯肉の炎症(歯周病 [periodontal disease])を含む歯科疾患は、慢性的な炎症性疾患と関連しており、認知症の危険因子である可能性がある。小児期の認知機能が良好な人は、歯の健康状態も良好であり、生涯を通じて、予防歯科治療をより多く利用し、歯を失う本数も少ない。これは、栄養状態の悪化、慢性歯周炎、歯科疾患に関連する炎症といった潜在的なメカニズムに何十年も先行している。
40~80 歳の人口統計学的因子、社会経済的因子、その他の健康状態をコントロールしたスウェーデンの全国的な研究では、う蝕と歯周病を有する 7,992 人の認知症発症率は、7~6 年間にわたりマッチさせた 2,918 人の対照群と比較して高くはなかった。人口統計学的因子、血管の健康状態、社会経済的状態をコントロールした米国の研究では、65 歳以上の 3,521 人において、さまざまな歯周病原菌が、26 年間の追跡調査において、あらゆる原因による認知症、アルツハイマー病、または死亡診断書に記載された死因がアルツハイマー病であることのいずれかと関連していたことが報告されている。歯科疾患群は、歯科疾患のない群に比べ、教育水準が低く、可処分所得が低く、併存疾患が多かった。歯と歯周病が認知症の危険因子であるという一貫した質の高い証拠は乏しい。
感染症や炎症がどの程度認知症の修飾可能な危険因子であるかは、ほとんどの研究が高齢者を対象に行われ、追跡調査期間が短かったため不明である。梅毒、HIV、ヘルペスなど、特定の病原体が血液脳関門を通過し、直接認知症を引き起こすが、これは感染症そのものが危険因子であるということとは異なる。炎症は認知症の多くの危険因子に共通する経路かもしれない。
双極性障害 (bipolar disorder)
追跡期間が 4~11 年の 5 件の縦断的研究のレビューで、双極性障害と認知症との関連が検討された。いくつかの研究は同じデータベースを使用し、すべて 2 つの集団ベースのコホート(オーストラリアまたは台湾)のいずれかに基づいていたため、メタ解析は行われなかったが、双極性障害と認知症リスクとの間に一貫した関連が同定された(HR は 2.31~4.55)。1 件の研究では、双極性障害の重症度(精神科への入院回数で測定)が高いほど、精神科への入院を必要としない双極性障害よりも認知症リスクが高いことが報告されている。認知症の発症率は、1 年に 1〜2 回の精神科への入院(RR 2.4, 95%CI 1.9-3.1)および 2 回以上の入院(5.7, 4.8-6.8)をした人で高かった。心血管リスク、併存疾患、アルコール摂取などの因子をどの程度調整するかについては異質であった。
統合失調症 (schizophrenia) を含む精神病性障害
1,300 万人を含む 11 件の集団ベースのコホート研究を対象とした 2022 年のシステマティックレビューでは、異質性は高かったが(I2 = 99.7%)、中央値 11 年間におけるあらゆる原因による認知症の全体的なリスク増加が同定された(RR 2.52, 95%CI 1.67-3.80)。 ほとんどの研究は統合失調症患者を対象としたものであった。早期発症の統合失調症(すなわち、40 歳未満)についての知見を報告した研究は 1 件だけであり、統合失調症でない患者よりも認知症リスクが高かったが、高齢発症の統合失調症(すなわち、40 歳以上)よりはリスクが低かった。 今回のレビューに含まれた別の長期研究も、若年(すなわち 18〜49 歳)の統合失調症患者と高齢(すなわち 50〜64 歳および 60 歳以上)の統合失調症患者では認知症リスクが低いことを報告している。しかし、3 件目の長期研究では、精神病性障害の発症年齢が若い人(18〜60歳 )の方が高齢者(41〜80 歳、51〜90 歳)よりも認知症リスクが高いことが報告されている。年齢、性別、併存疾患、アルコール、喫煙、薬物、収入、教育レベルに対する調整の程度は研究によって異なり、特定の併存疾患や抗精神病薬が認知症リスクや特定のタイプの認知症リスクに及ぼす潜在的な影響に関する決定的なエビデンスはなかった。
統合失調症患者では、発症時の脳容積が年齢をマッチさせた集団よりも小さいことから、神経発達に原因があることが示唆されている。また、統合失調症の中心的な特徴である認知機能障害は、発症時にすでに存在している。この認知障害とアルツハイマー病に関連する特異的な神経病理学との間に明確な関連はなく、中年期の認知機能については加齢に伴う典型的な経過をたどるが、統合失調症の患者は健常対照者やうつ病や双極性障害の患者と比較して(神経画像上)脳の老化が加速している。あるシステマティックレビューでは、メタボリックシンドローム(13 件の研究;n = 2,800;効果量 0.31, 95%CI 0.13-0.50)、糖尿病(8 件の研究;n = 2,976;0.32, 0.23-0.42)、高血圧(5 件の研究;n = 18,99;0.21, 0.11-0.31)などの心血管危険因子を持つ統合失調症患者は、心血管疾患危険因子を持たない統合失調症患者に比べ、認知機能が有意に悪いという結果が出ている。
元論文
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)01296-0/abstract?dgcid=twitter_organic_infocusbrainhealth_lancetdementia24_lancet