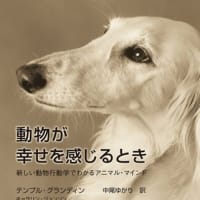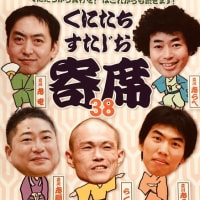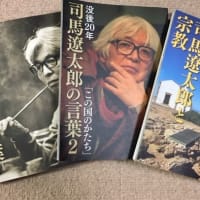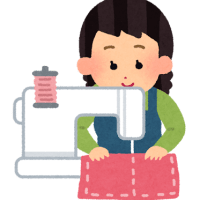コロナ禍で外出がままならない今、本を読む時間が増えています。
今回は、「読書について」1)という本を紹介します。
本の著者、アルトゥール・ショーペンハウアー(ショーペンハウエルともいう)は、デカンショ節2)に出てくるドイツの哲学者です。
この本で、ショーペンハウアーは、読書がよいことは認めていますが、その危険性を指摘しています。
●自分で考えることと、本を読むことでは、精神におよぼす影響に信じがたいほど大きな開きがある。
●本を読むとは、自分の頭ではなく、他人の頭で考えることだ。
●読書は、自分の思索の泉がこんこんと湧き出てこない場合のみ行うべき。
●きわめてすぐれた頭脳の持ち主でさえ、いつでも自分の頭で考えることができるわけではない。
そこで思索以外の時間を読書にあてるのが得策だ。
など、終始、読書の「罪」について指摘されています。
確かに、ただ単に多読するだけの読書を繰り返していたのでは、「物知り」にはなるかもしれませんが、
さまざまな分野にわたる、しなやかな知性を発揮するようにはならないと思います。
ただ「読むために読む」のではなく、読んで得られたものは「著者の考え」であることを理解し、きちんと
自分の頭で批判的な批評を加え、また、自分の経験を合わせて、初めて自分のものにしていく…このことを
しっかりと考えさせられた本でした。
ただ、「本は自分の好きに読むもの」…このことを明らかに否定されると、無性にいろんな本を自分の好き勝手に読みたくなってしまいます…。
1)ショーペンハウアー:読書について.光文社古典新訳文庫.2013
2)「デカンショ」とは、デカルト、カント、ショーペンハウアーの名前の頭をつなげたもので、かつての旧制高校の学生歌として歌われたもの。「デカンショ、デカンショで半年暮らす、後の半年寝て暮らす」
地域リハビリテーション推進部
中間浩一