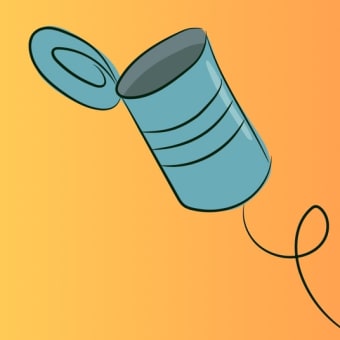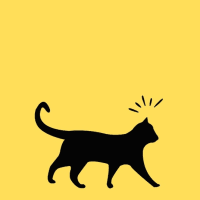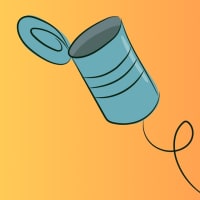1,
ぼくと嫁さんの相性は、すこぶるいいのだそうだ。波長が合っているらしいのだ。
しかし波長が合うというのは実に抽象的だ。
いったい、どの時期のどの場面の波長が合っているというのだろうか。
これまで何度も別れそうになったことがあるが、それでも別れなかったというのが『波長が合う』と言うのだろうか。
さらに、それと“運命の赤い糸”は、どういう関係があるのだろうか。
2,
その“運命の赤い糸”に関しては、思い当たる節がないではない。
あれは初めて嫁さんを見た時のことだった。
昭和56年のこと、その年の4月下旬に創業する会社に、ぼくと嫁さんは入社した。その創業の2日前に、ぼくは初めて嫁さんに会ったのだった。
その日ぼくは、所属している部署で、開業に向けての準備をしていた。仕事が一段落した頃だった。隣の部署の女の子が、じっとこちらを見ているのに気がついた。目が合うと、その子はぼくにニコッと微笑みかけた。
その時だった。その子が赤いエプロンをつけて、台所の向こうに立っている姿が、ぼくには見えたのだ。
ぼくはハッとした。だが、すぐに現実に戻った。
『何か用なんだろうか?』と思っていると、その子は、大きな声で「すいませーん」と言った。
「は?」
「あのー、後ろのテレビの音、大きくしてもらえませんかー?」
「テレビ?」
ぼくの部署にはテレビがあった。後ろを振り向いてテレビを見てみると、そこに田原俊彦が映っていた。
『ああ、俊ちゃんか。今時の子やのう』と思いながら、テレビの音を大きくしてやった。
言うまでもなく、その子が今の嫁さんである。
テレビを見ている嫁さんを見ながら、ぼくは『あのエプロン姿は何だったんだろう?』と思っていた。が、あまり深くは追求しなかった。その当時、ぼくには好きな人がいたし、高校出たての若い娘なんか興味がなかったからだ。
ただ、その時ぼくはうっすらと、嫁さんに恋愛とは違った何かを感じていたのは否めない。今になって考えると、あれが“運命の赤い糸”というものかもしれない。
3,
結婚した後、その時のことを嫁さんに聞いたことがある。
「おれはあの時、赤いエプロンをつけて台所に立っている、おまえの姿が見えたんやけど、おまえはどうやったんか?」
「・・・・」
「なんか、おまえは最初におれと会った時のことを覚えてないんか?」
「いや、覚えとるよ」
「じゃあ、何で黙り込むんか?」
「それは・・・・」
やはり、記憶にないのだ。
ただ、その時にテレビの音を大きくしてくれと言ったのは覚えていたらしく、「あの頃の俊ちゃんはカッコよかったよね」と言っていた。
もしかしたら、あの時、嫁さんは俊ちゃんに“運命の赤い糸”を感じていたのかもしれない。そして、いつしかそれが、ぼくにすり替わったのだろう。ぼくは俊ちゃんの身代わりである。