ネットで叩かれるものの定番といえば盗作。
最近だとaikoのジャケットとかね。
で、そのちょっと前には木村伊兵衛賞に輝いた本城直季なんてーのがあった。
この坊やの写真を使ったシティバンクなどの広告は新聞にもよく載ってたから見た人も多いことだろう。
ピントが合う場所を小さくして景色がミニチュアっぽく見せるという技法を使ったものだ。
ネットで叩かれてるって聞いたときは、別に構図とかぢゃなくって「技法」だからいいんぢゃないの?しかも先例は一人ってわけでもないし、Flickersとかのぞくと海外でも流行ってるみたいだし。
と思いながらも
ああ、でも“受賞”ってことになるとビミョーかもなぁ、だってこの作品群の価値って技法が8割、いや9割?みたいなとこあるしなぁ…
と「やや難あり」とも思った。
でも、新聞や雑誌などで本人サイドの発言を知ったら、
「やっぱダメぢゃんもこのガキ」と呆れた。
その時ふと昨年の村上隆の件を思い出した。
ナルミヤという子供服の会社にキャラクターをパクられたと訴えた事件だ。
村上隆といえば
「美術家はコンテクストで勝負する」などと豪語していたっけ。
それって言い換えれば、個々の作品そのものだけで完結しているのではなくそれらをつなぐコンセプトこそが重要だということなのだろう。
たしかにヤツの成功の転機は「スーパーフラット」とかいう“説明書”だった。
ということはヤツの発言やら行動やらも評価の対象になりうるということで、それこそ、それらのコンテクストに一貫性がなければヤツの価値も一巻の終わりってなことになる。
まさにナルミヤの一件は
「言ってることとやってることが違うぢゃん」と突っ込みたくなりるようなコンテクストの破綻ともいうべきものだった。
私が生きている現代アートの世界はオリジナルであることが絶対的な生命線です。
だってさ。
借り物の切り張りみたいなコンセプトで製作してきたオッサンが「オリジナルであることが絶対的な生命線です」…って(笑)
アンディ・ウォーホルが草葉の陰で噎び泣いていることだろう(笑)
で、本城直季の話題に戻ると坊やマネジメント会社によると
「2002年、大判カメラを使う中で偶然、こうした写真が撮れたことから試行錯誤を重ね、撮りためてきた。海外の作品は図書館で目にしたことがあるが、誰の写真集なのか覚えてないほど淡い記憶だという」
(2007/03/22讀賣新聞)
なんだよ、この言い方って自分でも「ボクの作品群の価値って技法がすべてなんです」って認めちゃってるようなものぢゃないか。ぢゃなかったら“先例”に対してこんなにビクつくことはない。
で、さらに
海外にも似た手法を使う写真家がいるという指摘もあるが、
「都市をミニチュアとして撮っているようには感じられないので、 別物だと思っています」
と説明する
(2007/03/16朝日新聞)
↑ここまでくると呆れるというか、開いた口がふさがらないというか…。
するとなにかい坊や?
Marc RaderだのOlivo Barbieriはパース補正のためにアオリを使ったとでも言うのかい?
wikipediaによればアオリを使ったミニチュア・フェイクは今世紀初頭からポピュラーになったそうだ。
確かに
「Tilt shift Miniature」
のキーワードでネットを探せばプロアマ問わずうようよ出てくる。
本城の坊やもネットで発見したんぢゃねーの?って疑いたくもなるよなぁ
まぁ、賞に関してはやるほうが悪いんだろうけど、この坊やの姿勢も卑しいなぁ。
ポストカード大賞くらいだったらまーるく収まったのにねぇ(笑)
他にろくなのがいなかったんだろうか
世の中慢性的にネタ不足なのかね
とりあえずネットで日本ではまだ流行ってないようなことを見つけてパクってみる
これ成功の秘訣あるね
いやいや、コンセプチュアルアートの時代だからシーンをリードできるのはアーチストではなく屁理屈に長けた物書きかもしれんぞ。
C級でいいからアーチストを雇ってパクりオンリーでいろいろ作らせて、それにいろいろゴタク並べて時代を風刺してみたとかなんとか言い張る。
これできまり。
今日からキミも村上隆(笑)
最近だとaikoのジャケットとかね。
で、そのちょっと前には木村伊兵衛賞に輝いた本城直季なんてーのがあった。
この坊やの写真を使ったシティバンクなどの広告は新聞にもよく載ってたから見た人も多いことだろう。
ピントが合う場所を小さくして景色がミニチュアっぽく見せるという技法を使ったものだ。
ネットで叩かれてるって聞いたときは、別に構図とかぢゃなくって「技法」だからいいんぢゃないの?しかも先例は一人ってわけでもないし、Flickersとかのぞくと海外でも流行ってるみたいだし。
と思いながらも
ああ、でも“受賞”ってことになるとビミョーかもなぁ、だってこの作品群の価値って技法が8割、いや9割?みたいなとこあるしなぁ…
と「やや難あり」とも思った。
でも、新聞や雑誌などで本人サイドの発言を知ったら、
「やっぱダメぢゃんもこのガキ」と呆れた。
その時ふと昨年の村上隆の件を思い出した。
ナルミヤという子供服の会社にキャラクターをパクられたと訴えた事件だ。
村上隆といえば
「美術家はコンテクストで勝負する」などと豪語していたっけ。
それって言い換えれば、個々の作品そのものだけで完結しているのではなくそれらをつなぐコンセプトこそが重要だということなのだろう。
たしかにヤツの成功の転機は「スーパーフラット」とかいう“説明書”だった。
ということはヤツの発言やら行動やらも評価の対象になりうるということで、それこそ、それらのコンテクストに一貫性がなければヤツの価値も一巻の終わりってなことになる。
まさにナルミヤの一件は
「言ってることとやってることが違うぢゃん」と突っ込みたくなりるようなコンテクストの破綻ともいうべきものだった。
私が生きている現代アートの世界はオリジナルであることが絶対的な生命線です。
だってさ。
借り物の切り張りみたいなコンセプトで製作してきたオッサンが「オリジナルであることが絶対的な生命線です」…って(笑)
アンディ・ウォーホルが草葉の陰で噎び泣いていることだろう(笑)
で、本城直季の話題に戻ると坊やマネジメント会社によると
「2002年、大判カメラを使う中で偶然、こうした写真が撮れたことから試行錯誤を重ね、撮りためてきた。海外の作品は図書館で目にしたことがあるが、誰の写真集なのか覚えてないほど淡い記憶だという」
(2007/03/22讀賣新聞)
なんだよ、この言い方って自分でも「ボクの作品群の価値って技法がすべてなんです」って認めちゃってるようなものぢゃないか。ぢゃなかったら“先例”に対してこんなにビクつくことはない。
で、さらに
海外にも似た手法を使う写真家がいるという指摘もあるが、
「都市をミニチュアとして撮っているようには感じられないので、 別物だと思っています」
と説明する
(2007/03/16朝日新聞)
↑ここまでくると呆れるというか、開いた口がふさがらないというか…。
するとなにかい坊や?
Marc RaderだのOlivo Barbieriはパース補正のためにアオリを使ったとでも言うのかい?
wikipediaによればアオリを使ったミニチュア・フェイクは今世紀初頭からポピュラーになったそうだ。
確かに
「Tilt shift Miniature」
のキーワードでネットを探せばプロアマ問わずうようよ出てくる。
本城の坊やもネットで発見したんぢゃねーの?って疑いたくもなるよなぁ
まぁ、賞に関してはやるほうが悪いんだろうけど、この坊やの姿勢も卑しいなぁ。
ポストカード大賞くらいだったらまーるく収まったのにねぇ(笑)
他にろくなのがいなかったんだろうか
世の中慢性的にネタ不足なのかね
とりあえずネットで日本ではまだ流行ってないようなことを見つけてパクってみる
これ成功の秘訣あるね
いやいや、コンセプチュアルアートの時代だからシーンをリードできるのはアーチストではなく屁理屈に長けた物書きかもしれんぞ。
C級でいいからアーチストを雇ってパクりオンリーでいろいろ作らせて、それにいろいろゴタク並べて時代を風刺してみたとかなんとか言い張る。
これできまり。
今日からキミも村上隆(笑)










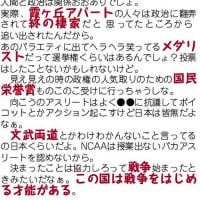
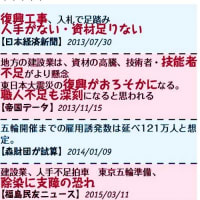







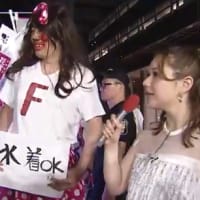





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます