遅くなりましたが…
7月24日の記事です m(_ _)m
17日のブログでご紹介した
ソウルアートシネマでの
ユ・ジテさんのお話です。
マイラティマの事が
より 理解出来た気がします。
seoulartcinema: [#Tistory]
“人々が予想できないものを出して
映画の中に入れたかった”
<マイラティマ>ユ・ジテ監督
<作家に会う>の7月上映作は
ユ・ジテ監督の<マで帯びますよ>
ユ・ジテ監督は
“映画を愛する一人として
監督や俳優という名称区分は
重要ではないようだ”
という話で始めた。
毎カットごとに
真心を込めて
映画を作ったという自信を
映って、次の映画で
何ができるか苦悩中である
という彼は監督としての
‘新しい人生
(マイラティマの意)’に
すでに飛び込んだように見えた。

Q: キム・ソンウク
(ソウルアートシネマ プログラマー)
映画を見れば男と女、
二人の話が繰り広げられる。
その二人で会うということと
別れることを繰り返すことに
なる。
初めに移住女性に対する話から
出発しながら男の話が入るが、
‘スヨン’という人物だけ
でも一つの話がよいという
気がする。 言ってみれば
青年失業者の話もあって、
社会人に成長するひとりの
成長痛に対する話もできる。
二人の話が初めから
ついていたスープの具でなければ
‘マイラティマ’という
女性に対する話をして
スヨンのキャラクターが
一緒に関連して入ったことが
気になる。
A: ユ・ジテ(映画監督)
大学時代から考えた話だ。
その当時は漁村の少年少女の
話であった。 少年少女が
子供ができることによって
おとなに成長する話であった。
それから15年が流れながら
私の考えが変り、
社会に対してもう少し
責任意識ができるようになり
社会反映に対して
深いと考えることになった。
色々な面でさらに深く考えて
みるから移住女性という
素材も登場することになり
青年失業者も登場した。
青年失業者は最終的に登場した
素材だ。
本来は十九才スヨンという
キャラクターだったが、
ペ・スビン氏を十九才にする
には無理があった(笑い)
どのようにすれば彼を
ドラマに自然に溶かして
出すことができるか悩んで
青年失業者と移住民の
愛の物語として、最後に
脚色することになった。
Q: キム・ソンウク
映画序盤に漢江(ハンガン)
高水敷地で自転車に乗る場面が
ある。 二人が自転車に乗って
後から夕陽がさしたが
場面が終わってしまい、
続けてペ・スビン氏が
働き口を調べに通う場面が
出てくる。 見る瞬間は
特異だったが、映画の最後に
同じポーズで自転車に乗る
場面が出てきたよ。
二つの場面がどのように
関連したことか。
A: ユ・ジテ
俳優生活をしながら、
どのようにすれば現場で
コミュニケーションが上手く、
現場をよく導いて行くことが
できるかを非常に悩んだ。
その悩みの結果は
徹底した‘持続性’だった。
私の映画や今後作られる映画も
徹底して計算をたくさんする方
なのに、(この映画でも)画面
ディゾルブ効果を念頭に置いた
部分がある。 その理由は
人生を入れた映画、
成長を入れた映画になるために
歳月の流れを描写できる装置が
必要なようだと考えた。
Q: キム・ソンウク
スヨンが初めて登場する時
家の中が出てくるが、
昔のアルバムを見せる場面で
卒業式写真を撮る瞬間がある。
スヨンの過去の女性に対する
説明は出てこないけれど、
先立って話した
二つのイメージが
これと関連があるのでは
ないだろうか。
A: ユ・ジテ
人に付いて回るトラウマは
何かという考えた。
スヨンはマでラティマと
違う欲望を追いかける
失業者気質なのに、
なぜ彼が青年失業者に
転落したかを考えた時
彼にトラウマがあると考えた。
彼とともに愛を分かち合った
過去の女性、彼を捨てた周辺の人々
彼を放置した家族が
トラウマとして作用しただろう。
マイラティマのディテールな
描写でない、画面転換方式と
同じイメージを通じて、
画面の中で説明できる方式を
選んだのだ。
Q: キム・ソンウク
映画でスヨンは他人の仕事に
関与しながら暴力を行使する
瞬間が多い。
前半部では浦項(ポハン)
出入国事務所で
マイラティマがおじさんに
暴力にあう時関与して、
後半部ではソ・ユジン氏が
暴行にあう時関与する。
スヨンという人物が自身と
関係ないことに関与する
場面がたくさん登場する
という気がした。
A: ユ・ジテ
韓国男性の典型的な面を
入れたかった。
否定的な面と良い面.
干渉が上手で、
自分の仕事でもないのに
熱情的で、反面良い点は
穏やかで情が多いことだ。
このような点が韓国の
人々が持っている
情緒の側面ではないか。
この頃の友人は違うことも
あるが30台中後半の人々の
そういう面を入れようとした。
Q:キム・ソンウク
浦項(ポハン)出入国事務所
場面でおじさんと戦って
バイクに乗って二人が
逃走する場面につながる。
突然の瞬間に広がること同じだが
その場面が全体的に
映画を見た時に跳躍を感じる。
A: ユ・ジテ
そうですね。 ある者は
この部分で可能性が落ちると
話すが、そのように考えない。
映画を見る時に可能性を
持って見る方式にだけ
慣れているのではないか。
突然の登場、他の叙事構造を
見せたかった。
独特さということもできる。
B級映画で見ることができる
方式だと考える。
突然登場するのがさらに
魅力的であることもあると
考えた。
可能性が落ちることができる
ということはシナリオ段階から
知っていた。 ここに代入して
みることができる映画の方式を
全部適用してみた。
違うものはつまらなかった。
日本映画<バイブレーター>の
ように即刻に会って離れてしまう
方式が一番気に入った。
今より若い時、映画には
とんでもないということが
なければならないと信じた。
ポール トーマス・アンダーソンの
<鷹その遊ぶだろう>のような論理や
アレクサンダーペインの
<サイド ウェイ>のような視線話だ。
映画で一般的でないこと、
独特で、人々が言う
‘可能性が落ちる’ということに
さらに興奮を感じた。
そのような部分で開始したり
もする。
B急映画や低予算映画で
このような独特さを
たくさん実験しなければ
ならないと考える。
監督が思う存分作家性を
発揮できる機会が
システム化されていれば
良いという風がある。
Q: キム・ソンウク
地下鉄でキスする場面も
例外的だ。 なぜよりによって
地下鉄か?
A: ユ・ジテ
韓国の人々は公共場所で
愛を表現するのをなじまない。
地下鉄で相手の映った姿を見て
震える気持ちで
初めてのキスをすれば、
独特の場所なので
人々に呼応を得ることが
できそうだった。
ところで地下鉄中に
照明器を持って行くことが
できなくてさらに美しく
撮れなかったのが惜しい。
三角海苔巻きの
キスシーンだとか、
人々が予想できない行動を
出して映画の中で
してみたかった。
Q: キム・ソンウク
愛を分かち合う場面で
カメラ動きが特異だ。
外側に出て行って
ひと回り帰ってくれば、
二人が横になって花の話をする。
カメラの動き、
オーバーラップなどが多いが
この場面で
カメラの動きをどんな方法
で構想されたのか。
A: ユ・ジテ
映画俳優として
映画を作るのに
理由がなければならないと
考えた。 どんな次元で
映画を作る理由があるか
考えた時、現在の韓国映画は
マルチプレックスで上映する
商業映画と初め低予算映画で
両極端化されている。
私は中間級の予算で
作ることができる、
低予算映画版ができなければ
ならないと考えた。
5億未満の映画を見れば
後れていたり技術的に
落ちる場合が多い。
そのような限界を
越えてみたかった。
限界を移りながらも
観客と疎通するのに
遊離することを願った。
それでできるだけ
うっとうしい編集でない
ダイナミックな編集と
カメラワークを駆使しようと
努力した。
その場面を演出する時
インスピレーションを得た
映画はカスパノーへの
<元に戻すことはできない>だ。
その理由は二人の異常な愛と
彼らの愛を隔離させる
社会の姿を見せたかった。
カメラワークが
二人が生きている所を
明らかにして、
窓向こう側で死んでいる都市と
生きている都市が分けられた
社会を遊泳する姿を
画面の中に入れたかった。
サンスベリア花の場合は
移住女性が書いた
色々な文を探してみながら、
‘サンスベリアが
自分と同じだ’という文を見た。
サンスベリアは
自活力が強くて
一月に一度ずつだけ
水を与えれば砂漠でも
生きられる強力な植物だ。
ところで人々が陰地植物だと
分かったため水を与えなくて
寿命よりはやく死ぬという。
無関心の中に孤立している
サンスベリアと自分が
似ていたという
移住女性の文を読んで
感動して映画に
入れることになった。

Q: 観客1
韓国人俳優が
マイラティマ役をしたが、
どんな理由なのか。
A: ユ・ジテ
タイ俳優もいたが、
映画予算がそんななかった。
俳優に航空料、宿泊料などの
お金を与えながら
製作できない状況だった。
韓国に住んでいる移住女性を
救うべきであった。
イメージと符合する人々は
放送局で全部キャスティングした
状況であったし、
ビザ問題などの
現実的な問題に直面した。
それで低予算映画が
韓国新人の登竜門になると
考え、そのような方式を
<よろしく>のような映画で
ヒントを得た。
人々がびっくりする程
演技をよくさせようと考え、
その考えが的中したようだ。
Q: 観客2
最後に出てくる
タイの伝統踊りが
象徴するところは何か。
A: ユ・ジテ
マイラティマを描く時、
ラティマの色を
明らかにしたかった。
監督として彼女の人生を
祝福したかったし、
希望を描きたかった。
事実最後にラティマが
韓国に定着している場面は
偽りだ。 不法滞留者になれば
無条件追放されなければ
ならないから、その部分は
事実と違うようにさせた。
私の風でもある。
サンスベリアの花言葉が
‘寛容’という。 韓国社会が
冷静で排他的な指向が
強くなったが、
人権の立場で寛容を
施すようにならなかったか
と考える。
Q: 観客3
この映画の中で監督様が
私が考えることぐらい
美しく出てきたかと思った
場面は何か。
そして‘このような映画作りたい’と
考えることがあるのか。
A: ユ・ジテ
毎カットが私には美しい。
カット、カットを
手工芸のように作った作品だ。
限界を破るのは結局労働だ。
私は早くプロセスするのを
好まない。 よく整列してない
作品を出すのが好きでない
ためにプロセスが遅い方だ。
映画とドラマの差異点は
誠意があると考える。
今後ていねいな映画を
作りたい。
画面やテクニックに
執着する時期は過ぎたし、
今は私がドキドキする素材と
主題が重要だ。
整理|
観客エディターチ・ユジン
写真|
資源活動街キム・ユンツク
ちなみに…
こちらがサンスベリア

で…
そのサンスベリアの花が

こちらです。
可愛い花ですね!
ユ・ジテ監督のお話を
聞けば聞くほど、
知れば知るほど〈마이라띠마〉を
もう一回観たくなりますね。
今月号の T・O・P でも
ぺ・スビンさんのインタビューは
マイラティマ一色でしたから
日本でも上映される可能性が
あるのでは…?
と、期待を持っています。














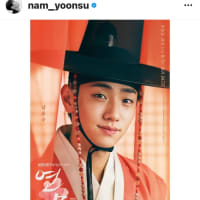







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます