<響板の製作>
先の表面板を,ランダムサンダーと手作業で削ります。
厚みを大体2.5mm程度にします。
実際は,音んも反応を見ながらの作業となります。
(写真を撮り忘れました。)

補強板を接着し、厚み調整を行った。

ブレージング作業中。
先に和材のギターを作っているが,響板に力木の無い構造を実験的した。重要な力木は、写真の、柾目に沿ったものであることを確認した。と同時に、ヴァイオリン属におけるバスバーの意味も理解力することができた。

接着中
私の場合、響板面積の活用,音源位置との関係から、有効な振動部分を確保し、如何にその振動を制御するのかということを念頭に構成することにしている。だから実験製作においては、既成の構造に囚われることなく、自由にやっている。

響板ができた。
強度的に弱いと思われる方いるかも知れない。
その理由は,製作を進めていく中で明らかになる。
先の表面板を,ランダムサンダーと手作業で削ります。
厚みを大体2.5mm程度にします。
実際は,音んも反応を見ながらの作業となります。
(写真を撮り忘れました。)

補強板を接着し、厚み調整を行った。

ブレージング作業中。
先に和材のギターを作っているが,響板に力木の無い構造を実験的した。重要な力木は、写真の、柾目に沿ったものであることを確認した。と同時に、ヴァイオリン属におけるバスバーの意味も理解力することができた。

接着中
私の場合、響板面積の活用,音源位置との関係から、有効な振動部分を確保し、如何にその振動を制御するのかということを念頭に構成することにしている。だから実験製作においては、既成の構造に囚われることなく、自由にやっている。

響板ができた。
強度的に弱いと思われる方いるかも知れない。
その理由は,製作を進めていく中で明らかになる。












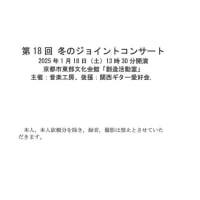



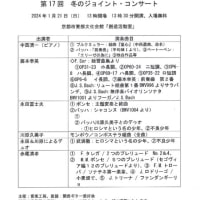
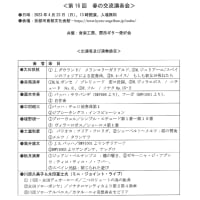

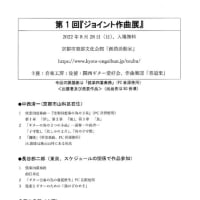






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます