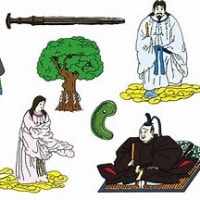山岳信仰とは山を神聖視する信仰だ。その基盤には、巨大な造作や自然の脅威への畏怖、水・動植物・資源などの恵みへの感謝、死者や祖先の魂の依り所としての敬拝などがある。加えて、世俗との隔絶、霊や神仏の臨在感、冷気や清流の清浄感が、山行に伴う身体的な活動と共に精神を高揚させる。
この山岳信仰を元に山中で修行する行者(役小角など)が現れ、仏教(特に密教)だけでなく陰陽道や道教の神秘性も取り入れ、修行様式や教義を整備して他の宗教とは異なる教団を組織した。これが修験道だ。古来の山岳信仰と仏教などの外来の宗教を習合させた日本独自の宗教なのだ。
修験道場には神社(鎮守社)と寺院(別当寺、神宮寺)があり、本地仏とそれが権(かり)に神の姿となった権現・明神が祀られる。修験者(山伏、法印)は山中で修行し、擬死体験で験力を得た。その力で加持祈祷や卜占託宣などを行い、衆生の救済(菩薩道)を目指した。彼らは在家の身近な宗教者であった。
その教えは「人や万物には本来仏性が備わる」という性善説に立つ。教団は中世に武力集団となり、江戸時代には熊野の本山派(天台系、総本山は聖護院)と吉野の当山派(真言系、醍醐寺)の二派に集約された。各山では講を組織して信仰登拝を催し、独自の神楽や謡・祭礼も発展させて隆盛を極めた。
ところが、維新早々の明治元年には神仏分離令が発された。この背景には、江戸時代に国学の隆盛から尊王思想が高まり、明治政府が国家の精神的支柱を仏教ではなく神道に求めたことがあった。この発令に、寺檀制度に対する民衆の反感や神官の仏教側への鬱憤が加わり、廃仏毀釈が起こった。
毀釈は全国に広がり、修験道を含む仏教関係の建築物、鐘楼、仏像などが破却された。これを機に金属の略奪を謀り寺院が消滅した藩もある。その結果だろう、現代の山岳信仰には仏教の影が薄い。更に明治5年には修験禁止令が発された。権現は廃され、修験道の布教や祈祷も禁止されてしまった。
禁止令は壊滅的だった。山伏は身分を捨て、権現は不動などに名を変え、各派は仏教色を薄め教派神道となった。戦後は宗教法人として復活したが、往時の勢いはない。ただ見方を変えれば、日本人の世界観・精神性や日本の近代化を理解する上で、修験道は重要な視点を与えているとも言える。(続く)