スピーカーの片チャンネルを数ヶ月前の状態に戻してみました。
中・高域が弾ける音!
当時は3WAYですが、高域ユニットは周波数レンジを伸ばすよりも中・低域のレスポンスを上げるように使っていた様です。
低域も中域に追従するために控え目。バスドラの存在感が希薄です。
でも、チェンバロ最高!ギターもシビレる。全ては中・高域のために!だったんですね。
思い返すに、セッティングする、その時にフェイバリットな音楽の影響甚大です。
しかし、高域の周波数レンジは伸びていないようで伸びている。
ALTEC A5相当の構成、2WAYでは聴けない音が出る。
スピーカーセッティングを記録しておいて、変更後ある程度落ち着いてきたところで比較する事は非常に意義があるんですね。
僕はALTECに何を求めるか?
「QUEENにすべてを!」っという志は今もあるものの、心の比重は新しい出会いに割かれています。
スピーカーセッティングを終結させようとすればするほどに無理が出てくる。
終わりは無いんでしょうかね?
常に流動的なのがむしろ自然なんでしょうか?
オーディオは終わりの無い旅のようです。
中・高域が弾ける音!
当時は3WAYですが、高域ユニットは周波数レンジを伸ばすよりも中・低域のレスポンスを上げるように使っていた様です。
低域も中域に追従するために控え目。バスドラの存在感が希薄です。
でも、チェンバロ最高!ギターもシビレる。全ては中・高域のために!だったんですね。
思い返すに、セッティングする、その時にフェイバリットな音楽の影響甚大です。
しかし、高域の周波数レンジは伸びていないようで伸びている。
ALTEC A5相当の構成、2WAYでは聴けない音が出る。
スピーカーセッティングを記録しておいて、変更後ある程度落ち着いてきたところで比較する事は非常に意義があるんですね。
僕はALTECに何を求めるか?
「QUEENにすべてを!」っという志は今もあるものの、心の比重は新しい出会いに割かれています。
スピーカーセッティングを終結させようとすればするほどに無理が出てくる。
終わりは無いんでしょうかね?
常に流動的なのがむしろ自然なんでしょうか?
オーディオは終わりの無い旅のようです。












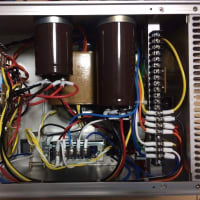
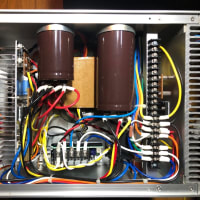







音を聞かずに音楽を聴く。歌手の歌い方、演奏者の演奏方法等が見えるのが理想では?
今迄のセッティングと現在のセッティングを比較する手法は重要だと思います。
過去と現在を冷静な視点で見る事が出来る様になったんですね。
楽音のプレゼンスを求める場合中高音を持ち上げるよりも透明な音色を狙うセッティングの方が有効でしょう。
けっしてチープではなく,ロックとはそういうものです。
Nong-Khaiさんの様に目的がハッキリしていると悩むことも少なそうですね。
僕はまだ成長段階で、あっちにフラフラこっちにフラフラですw。
>みけねこさん
たまにフォスのフルレンジで聴くと“ハッ!”っとすることがあります。
BBCモニターなどは聴き手の立場に立った理想的なものなのかも・・・っと思ったりもします。
A5級のシステムで聴くことは、油絵を顕微鏡で観る様なものなんでしょうかね・・・。